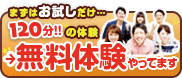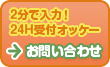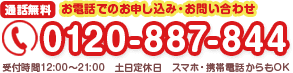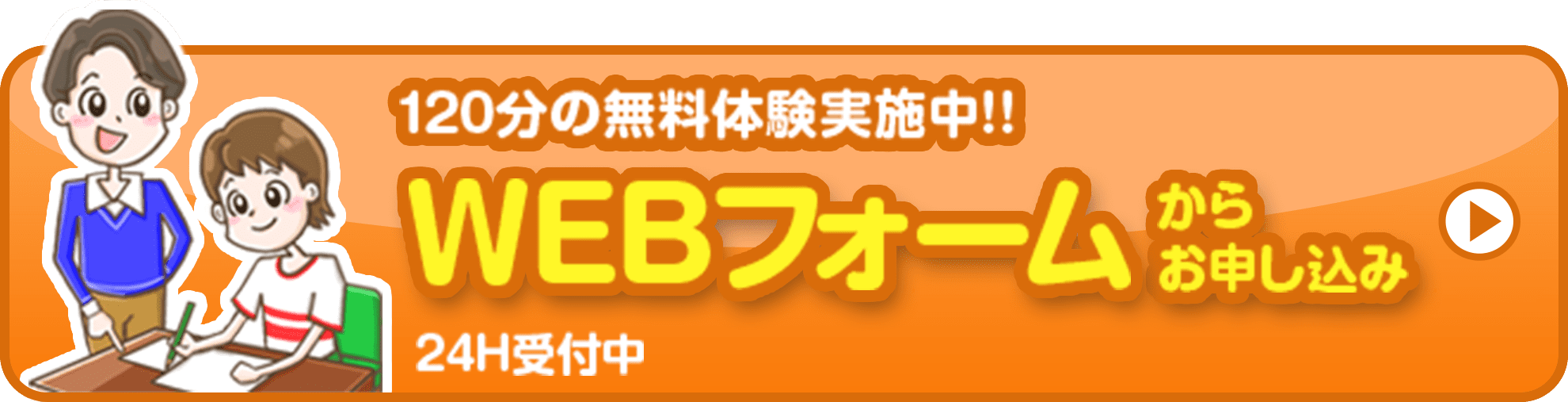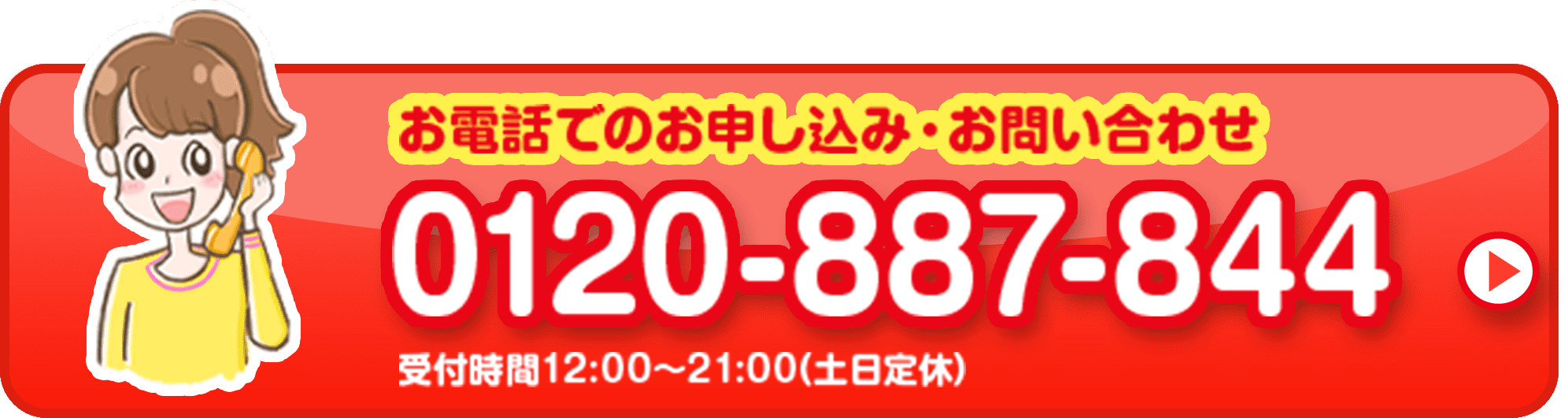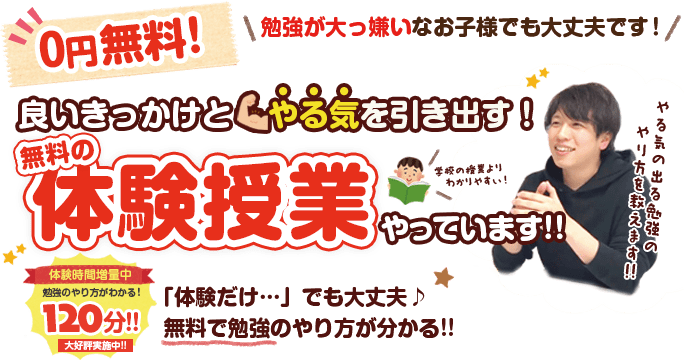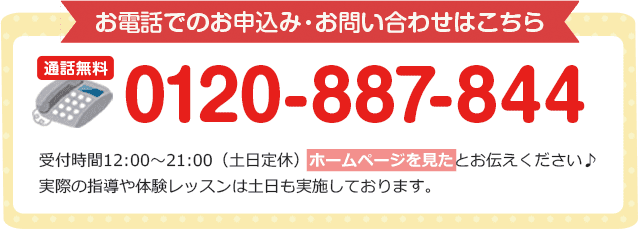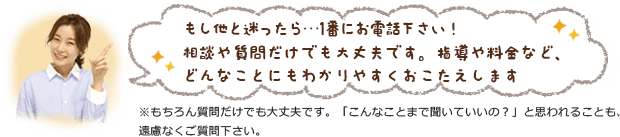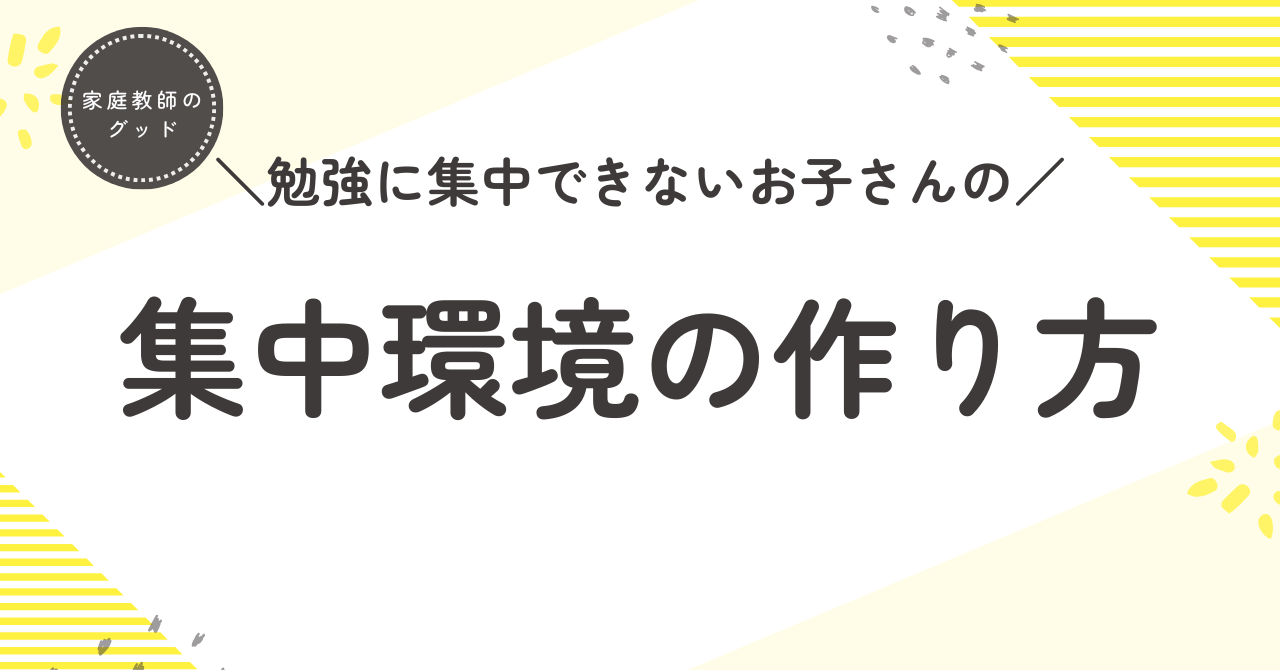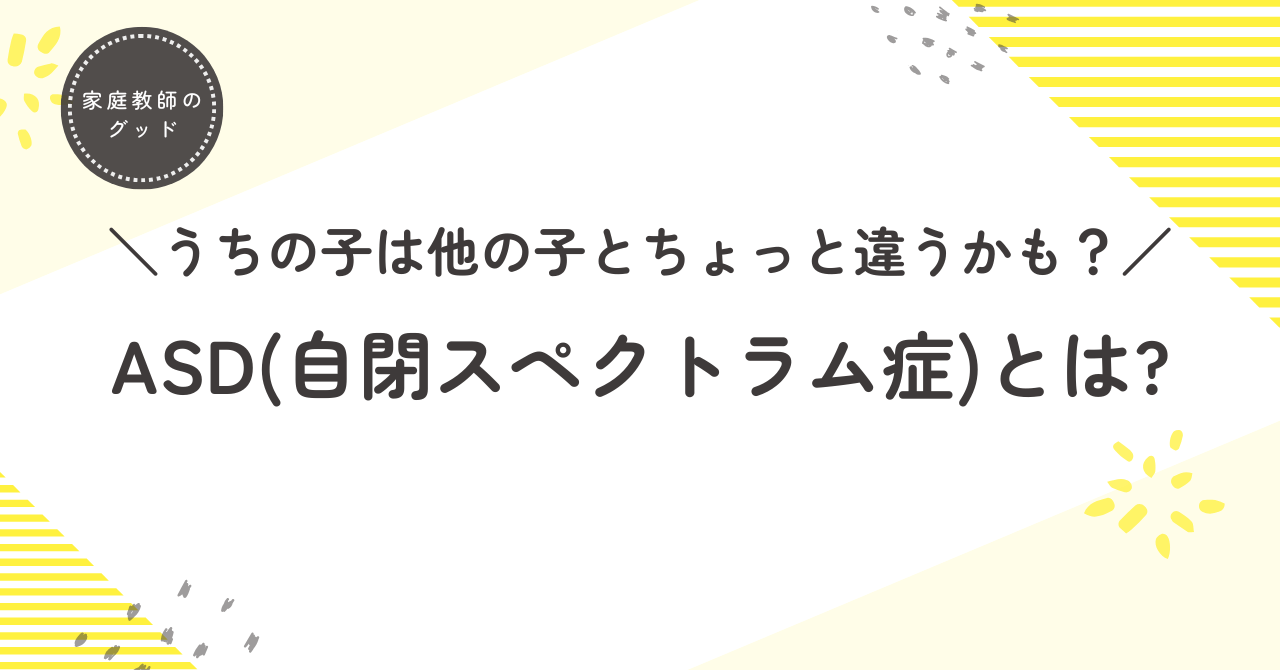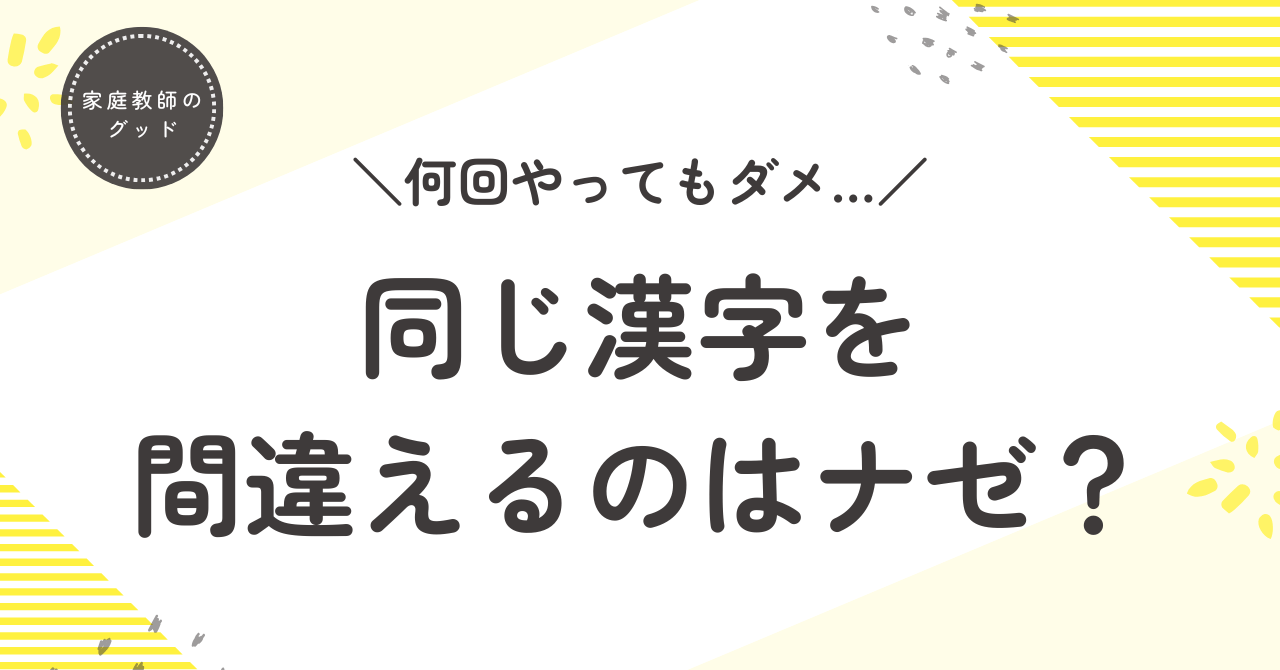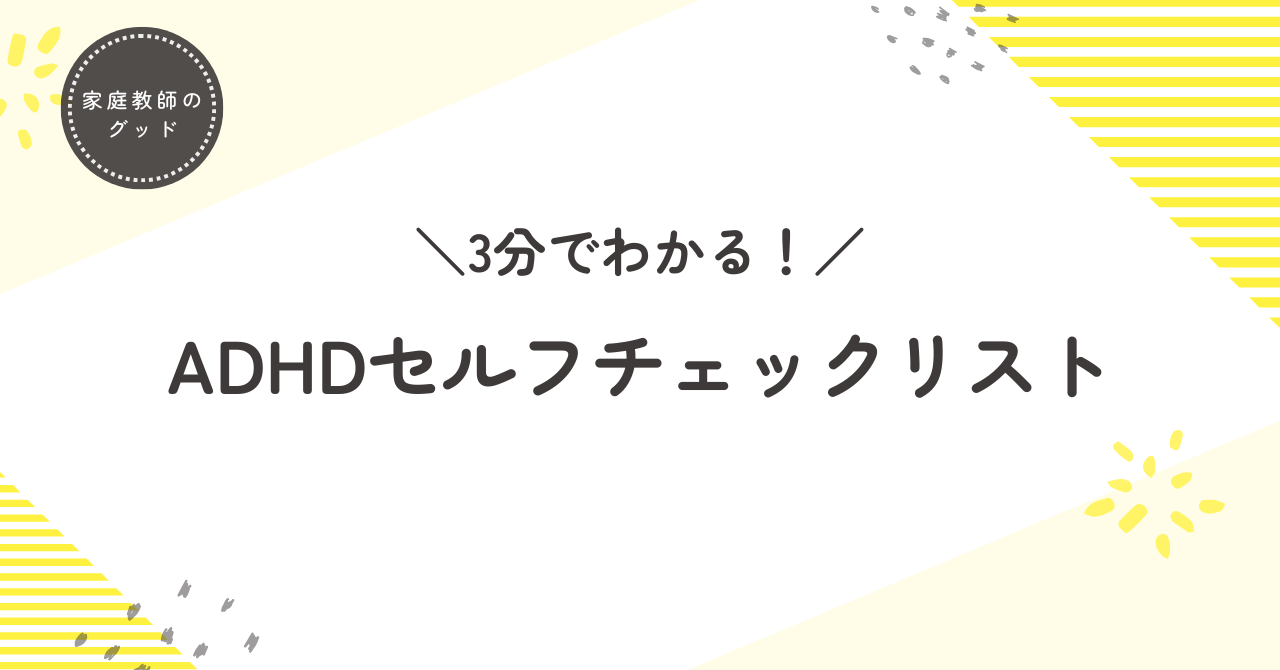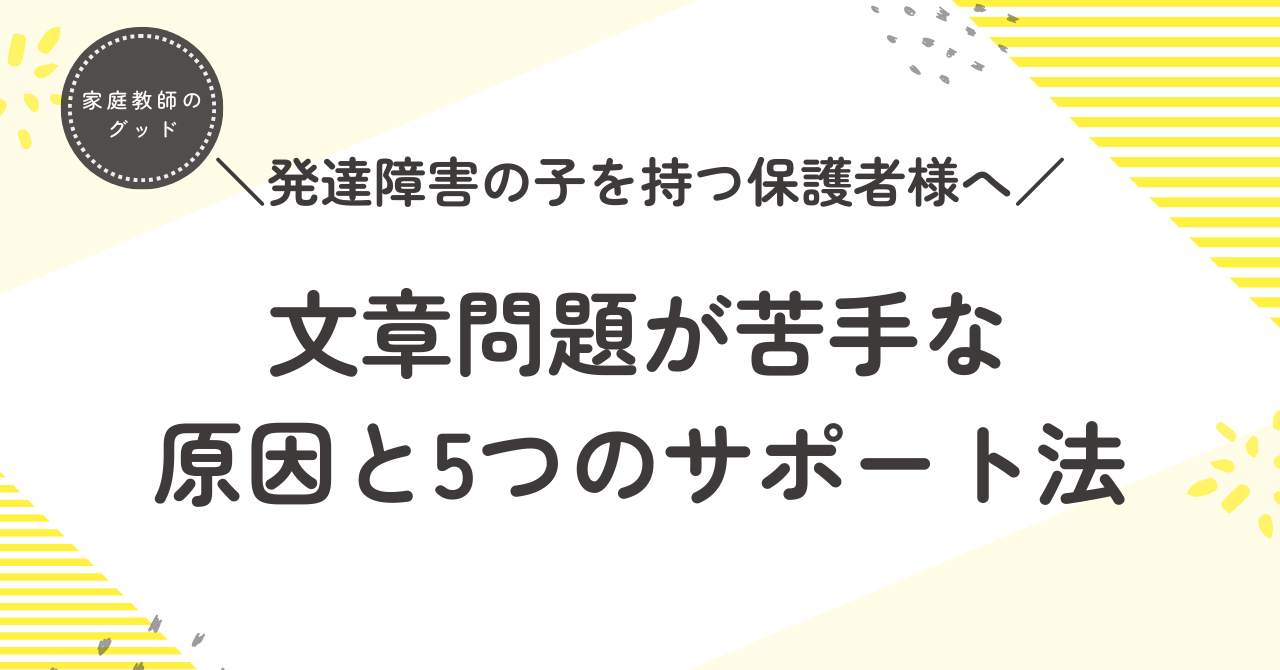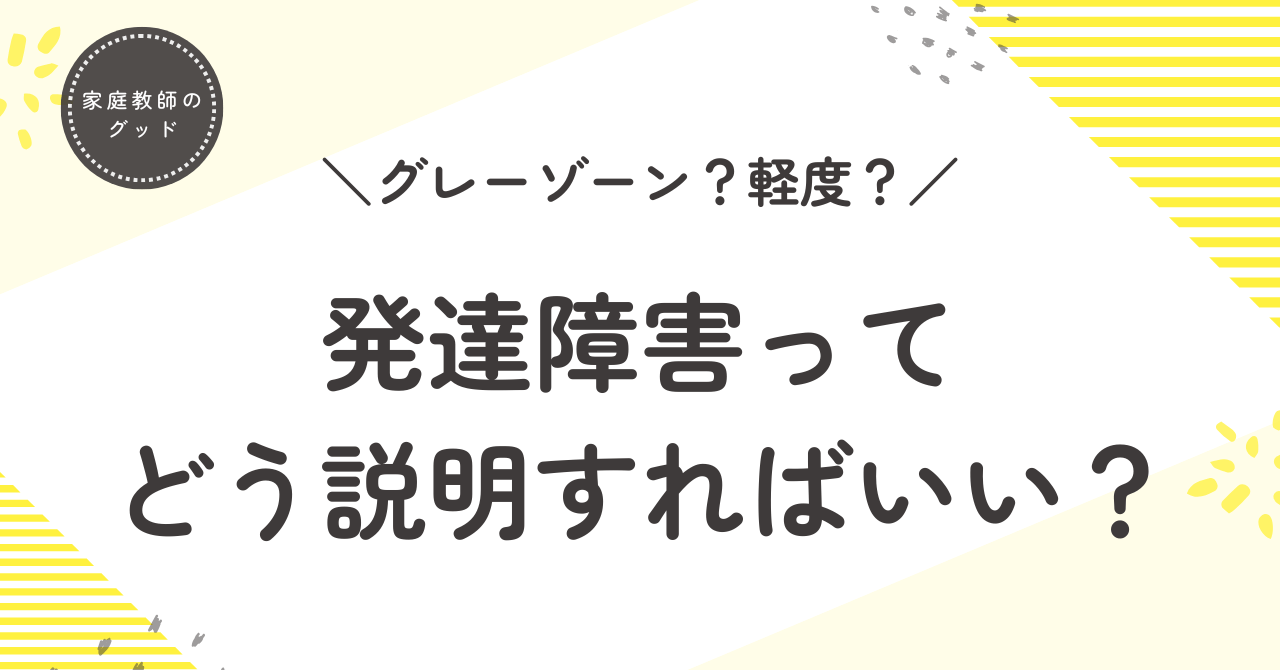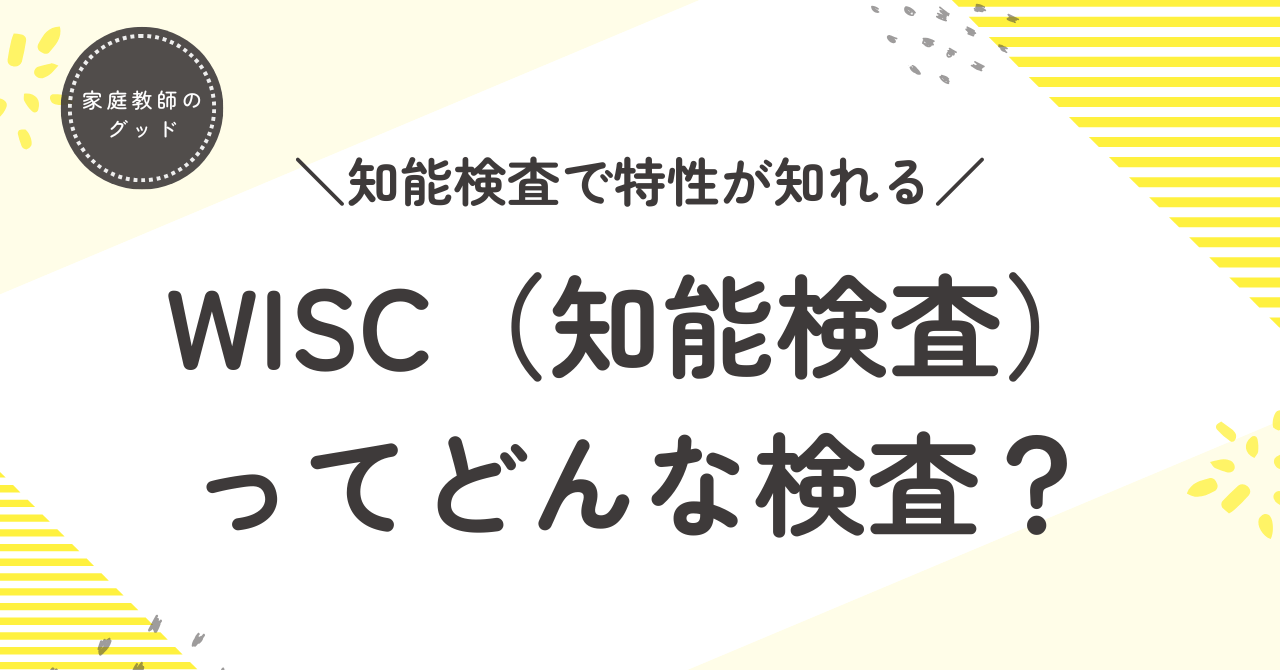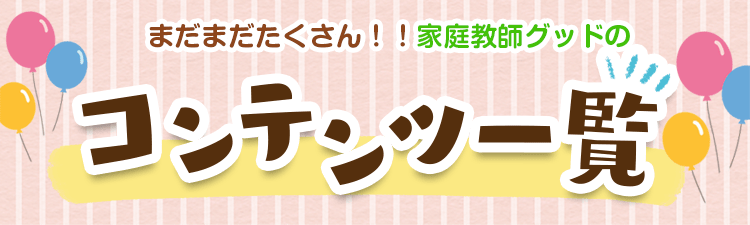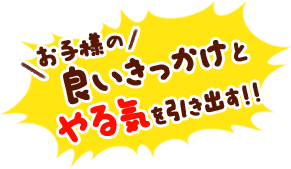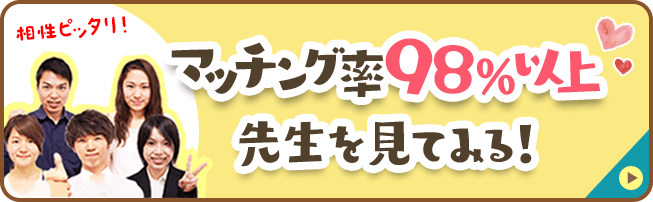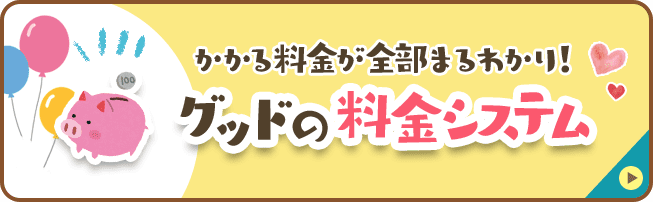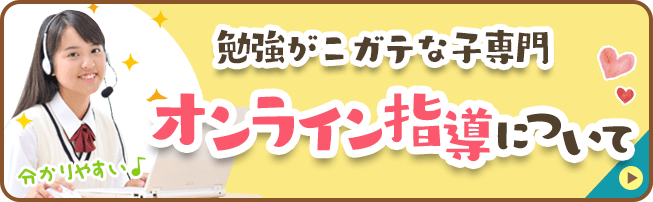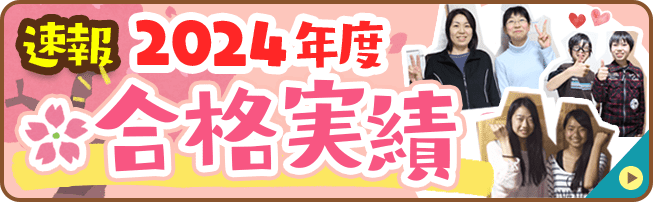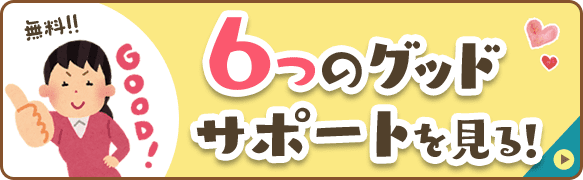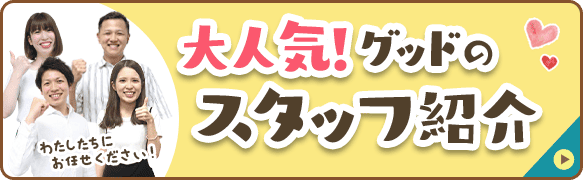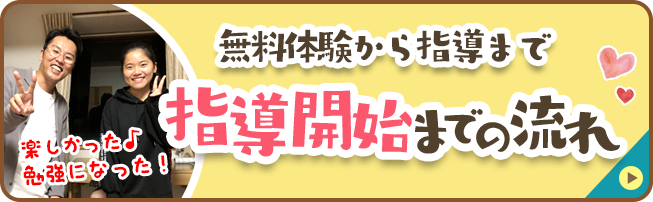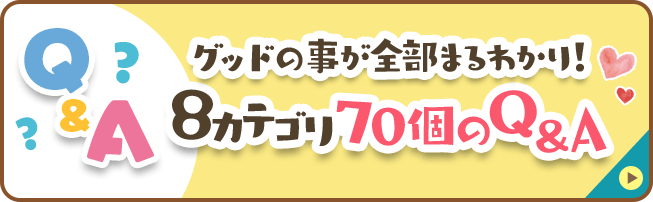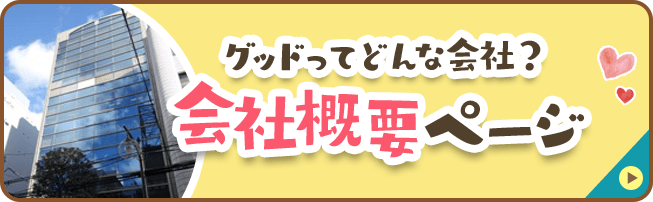発達障害の子どもはどうして怒りっぽいの?理由と接し方のポイントを紹介
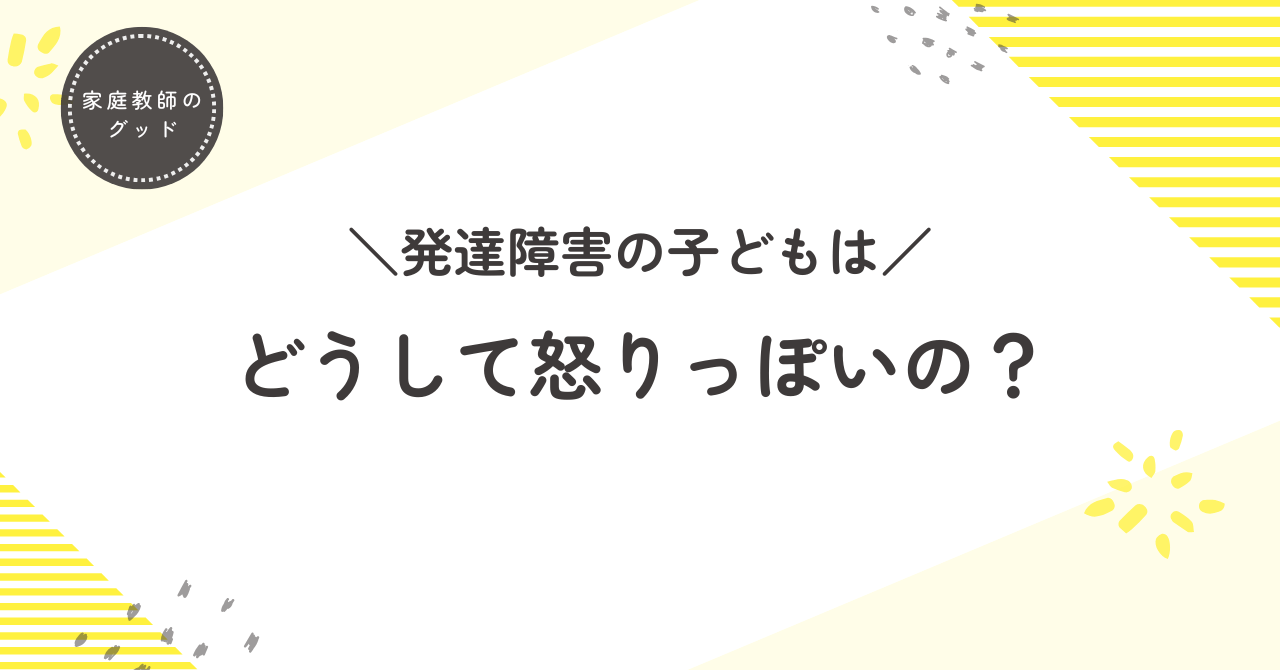
想定外のできごとや思いどおりにならないと、すぐにイライラする。暴言を吐いたり、物を投げたり攻撃的になる。
発達障害のお子さんは感情のコントロールが苦手で、怒りの制御がききにくい傾向があります。
こんな時、どう接したらいいのか悩んでいる親御さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、発達障害のお子さんの怒りっぽい理由と関わり方のポイントを紹介します。悩んでいる親御さんに少しでも参考になれば幸いです。
発達障害の子どもの特性と困り感について

発達障害は生まれつきの脳機能の発達に関係する障害で、主に3種類に分類されています。 (単独、あわせもつ場合もあります。)
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
それぞれが特性をもっており、日常生活で様々な困難を感じています。怒りは、その困り感を伝える感情表現のひとつと考えられます。
怒っている状態は周囲に誤解されがちですが、けっして本人のわがままや努力不足、親のしつけの問題ではありません。
「問題のある子」ではなく、「困っている子」と認識し、家庭だけではなく、周囲の理解や適切なサポートが必要です。
どうして怒りっぽいの?発達障害の子が怒りっぽい理由
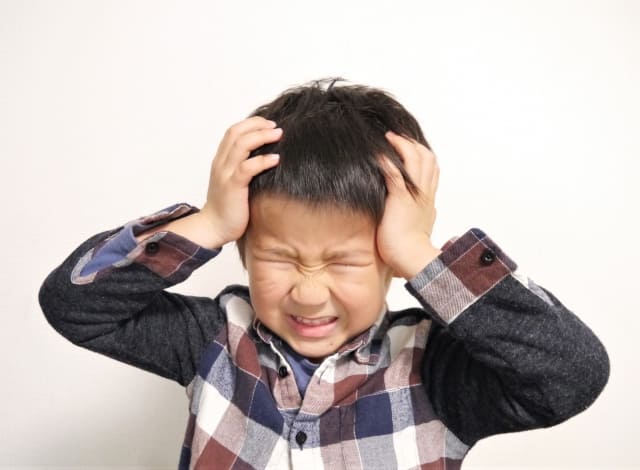
まずは、発達障害の特性と困り感を理解することが大切になります。
ここでは特性がどのように怒りの感情に繋がるかを、原因ごとに説明していきます。
※特性は子どもによって違い、必ずしもそうとは限りません。
疲れている状態
ADHDの特性に「多動性」、「不注意」、「衝動性」があります。
思いついて衝動的に行動してしまう。身体のどこかを動かし続けることは安心感となります。
無理にじっとしてようと思えば神経をすり減らします。
これは身体だけではなく脳内もで、気が散りやすく、常に脳を使っている状態です。
発達障害の子どもは、日常生活で多くのエネルギーを消費しており、疲れていることで怒りのス イッチが入りやすくなります。
苦手な環境のストレス
ASDの特性に「コミュニケーションの難しさ」、「感覚過敏」があります。言葉をそのまま受け取ったり、思ったことを口にしてしまう。
相手側にたって考えることが苦手です。
そのため、うまくコミュニケーションがとれず、お友達関係に悩むことがあります。
音や光、匂いなど、繊細で感覚過敏がある子は、その場所にいるだけでストレスがかかります。
学校では、グループ活動や集団行動が求められます。
苦手な環境でのストレスの積み重ねも怒りっぽくなる原因になります。
不安や混乱からくるパニック
ASDの特性に「こだわりの強さ」があります。
特定のものや同じ状態、決まったルーティンを好みます。これは安心するからです。
その逆で、先が見通せないことや曖昧なことは、とても不安になります。
こだわりの強さは悪いことばかりではありません。興味のあることには並外れた集中力を発揮し、才能豊かなお子さんも多いです。
ただ、過集中となることで周りが見えなくなり、注意される場合もあります。 このコントロールがうまくできないんですよね。
急な予定変更は、うまく気持ちの切り替えができず、癇癪や怒りっぽさに繋がります。
また、複数の作業を同時にすること(マルチタスク)が苦手で、途中で別の指示をされると混乱し パニックになります。
学習障害への無理解
学習障害(LD)は医学的にはSLD(限局性学習症)と言われています。
知的能力に問題はないものの、学習における困難さがあり、主に3種類に分類されています。 (単独、複数をあわせもつ場合もあります。)
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュア)
読むこと、書くこと、計算や数の概念など特定分野に困難を抱えています。 同じスピードで進んでいく授業についていくことが大変になります。
宿題にも時間がかかります。
本人は頑張っているのに先生に叱られたり、同級生にバカにされることもあります。 自信をなくしたり、わかってもらえない状況に反抗的になることもあります。
怒りっぽいお子さんへの接し方のポイント

怒りっぽさの原因には、特性からの苦手、嫌なこと、困っていることがあることがわかりました。 ここからは対策について説明していきます。
ゆっくり話を聞いてみる
振り回されてしまう気持ちもわかりますが、こちらも怒ったら逆効果となります。 まずは、静かな落ち着ける場所に移動し、ゆっくりと話を聞きましょう。
発達障害のある子どもは、自分の感情をうまく言葉で表現ができません。 本人が気づいていないことも多いです。
こういう状態なんだねと優しく説明することで、本人も認識し、少しずつ言葉で伝えられるように なっていきます。
休息をとる
「ここまでよく頑張ったね。疲れたよね。ゆっくり休もう」と話します。
できていることに目を向けて頑張ったことを褒めます。
そして、休むことが必要なことを伝えます。
だらけているように見えても、実は疲れていることも多いです。
疲れている場合は心身ともに休むこと、充電が必要です。
発達障害の子どもには、睡眠の問題を抱えている子も多くいます。
睡眠問題が疲れの原因となっているようでしたら、医師に相談してみましょう。
環境調整をする
まずは、どんなことに不快感があるかを知ることで対策を考えます。
例えば、聴覚過敏で騒がしい音が苦手な場合は、静かな場所に移動したりイヤーマフを使用しま す。
視覚過敏で光が苦手であればサングラスを使用します。
触覚過敏で服のタグが嫌であれば取り除く。苦手な素材は避けます。
このように刺激を避けたり、道具を活用することで不快感を軽減させることができます。
視覚化し、見通しをわかりやすく説明する
予定変更は、それによってどう変わるのか、先の見通しまで具体的に説明します。
事前に、変更があった時を想定して伝えておくのもいいですね。
イメージしやすいように紙に書いて残すとわかりやすいです。スケジュールを時系列で記載したり、イラストのカードを使うのもおすすめです。
学習障害の合理的配慮
学習障害も感覚過敏と同じように、勉強方法を工夫すれば負担を軽減することができます。 今はICT教材、タブレット、音声付きのデジタル教科書など便利なアイテムがあります。
例えば、わかっていても書くことができない場合、タブレットなら入力ができます。 フォントが変われば読めるようになります。
これは特別扱いではなく、合理的配慮となり、学校側にも求めることができます。
子どもの学習意欲を失わせないことが大切です。
できないことで自己肯定感が下がり、不登校に繋がる場合もあります。
少しでも学校で過ごしやすくなるように学校側に相談しましょう。
まとめ
発達障害の子どもの怒りっぽい理由と接し方について説明しました。突然の激しい感情表現に戸惑いますよね。
でも、理由があり、子どもなりに困っていることを必死に伝えています。
お子さんは苦手な環境の中で頑張っているんですよね。
それは親御さんも同じです。きっとここまで頑張られてきたことでしょう。何もかも一人で抱えることはありません。
まだまだ成長過程のお子さんは、周りの理解や適切な支援で変わっていきます。
家庭教師のグッドは発達障害を理解し、お子さんの特性に合わせた学習方法でやるきを引き出します。
お気軽に学校での困りごともご相談ください。