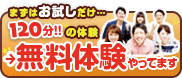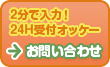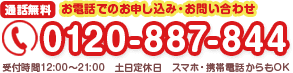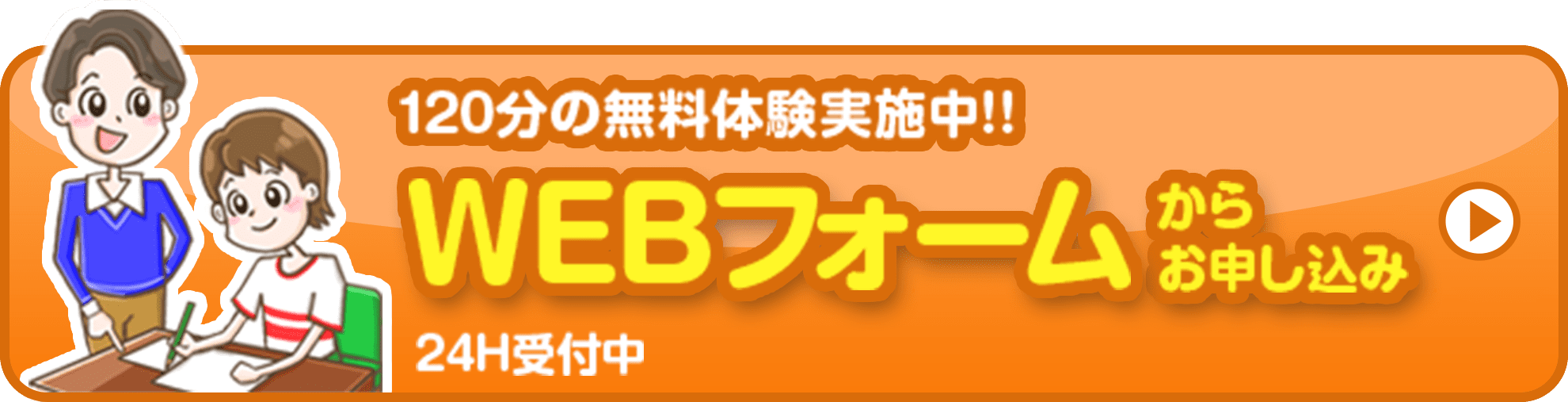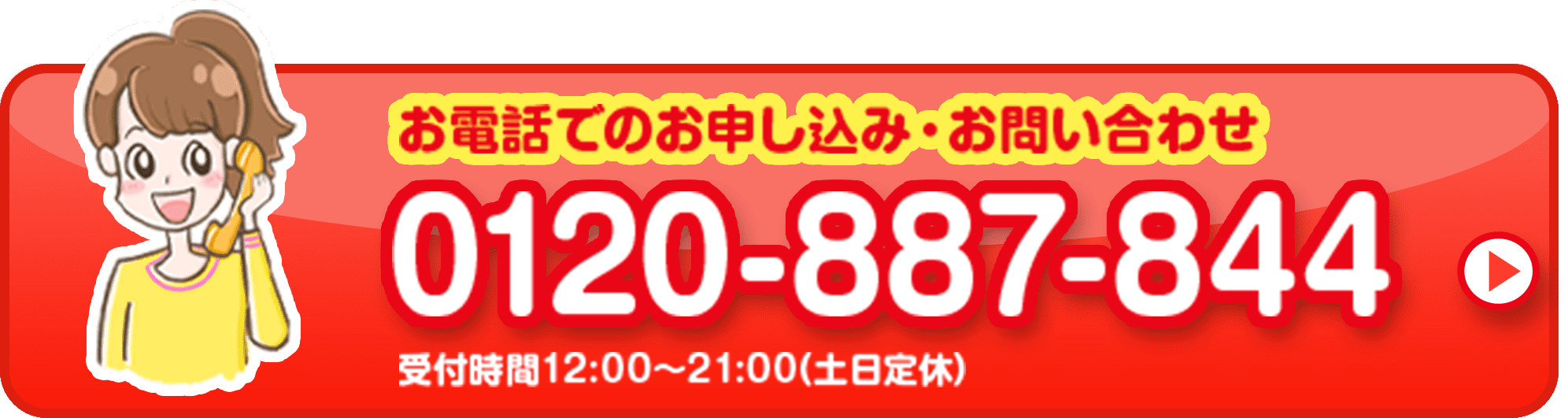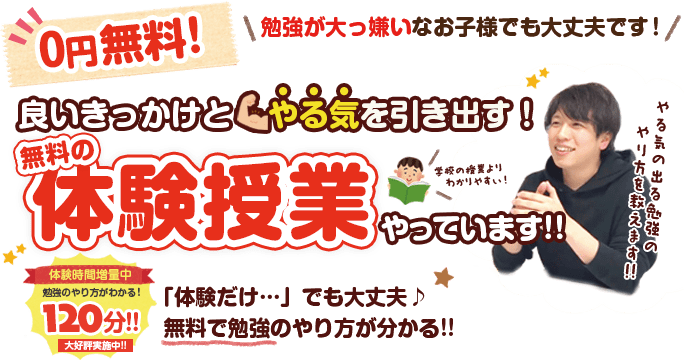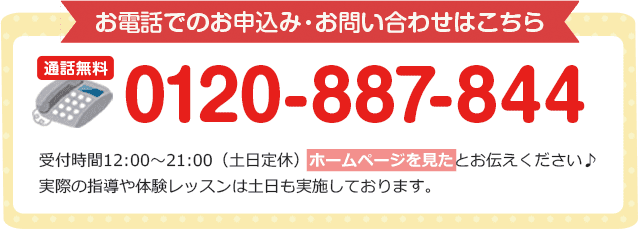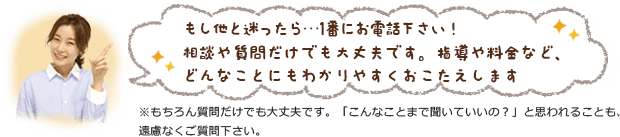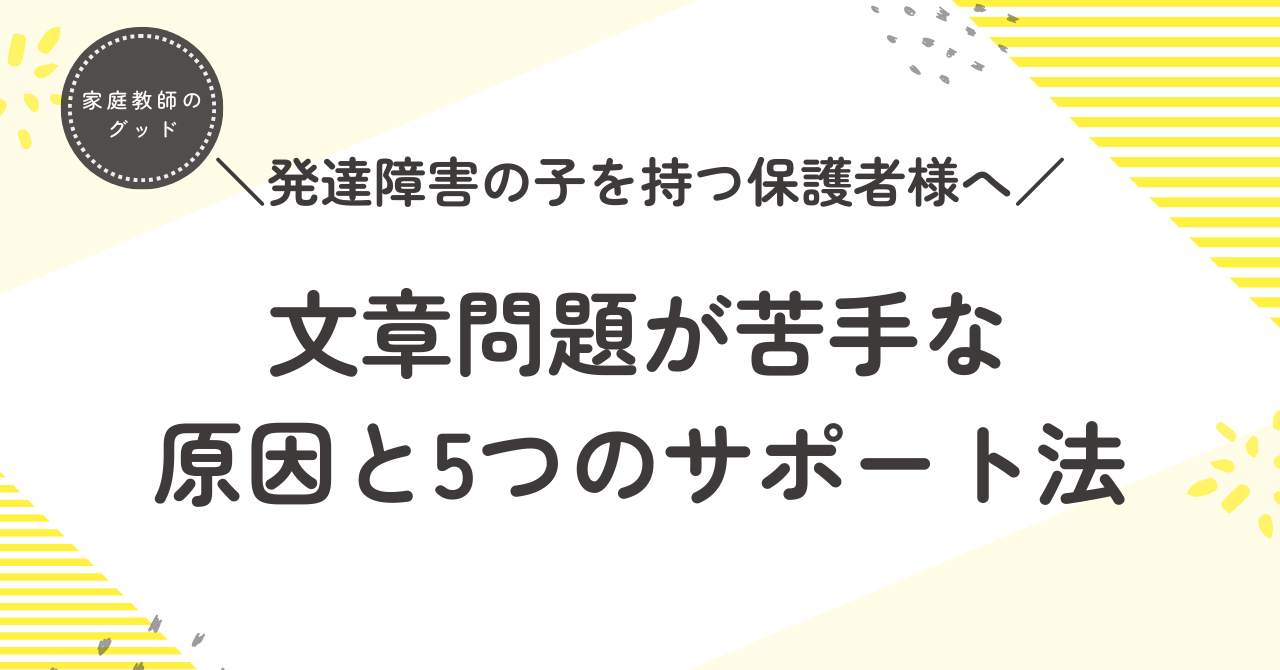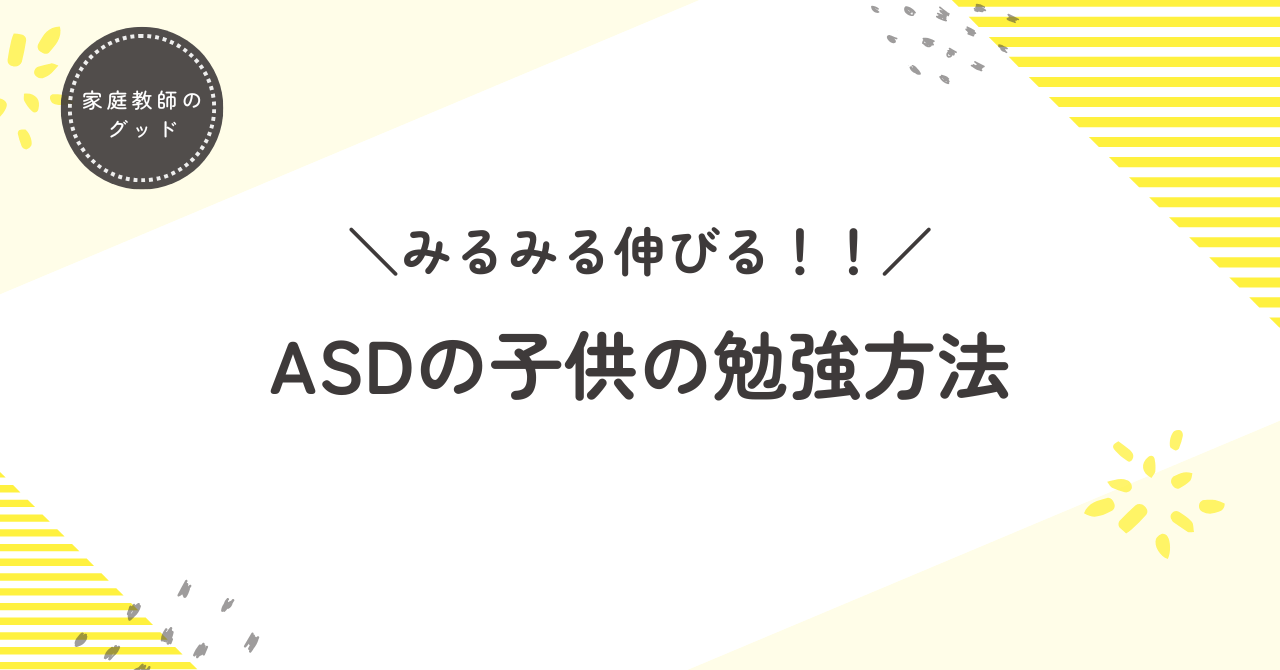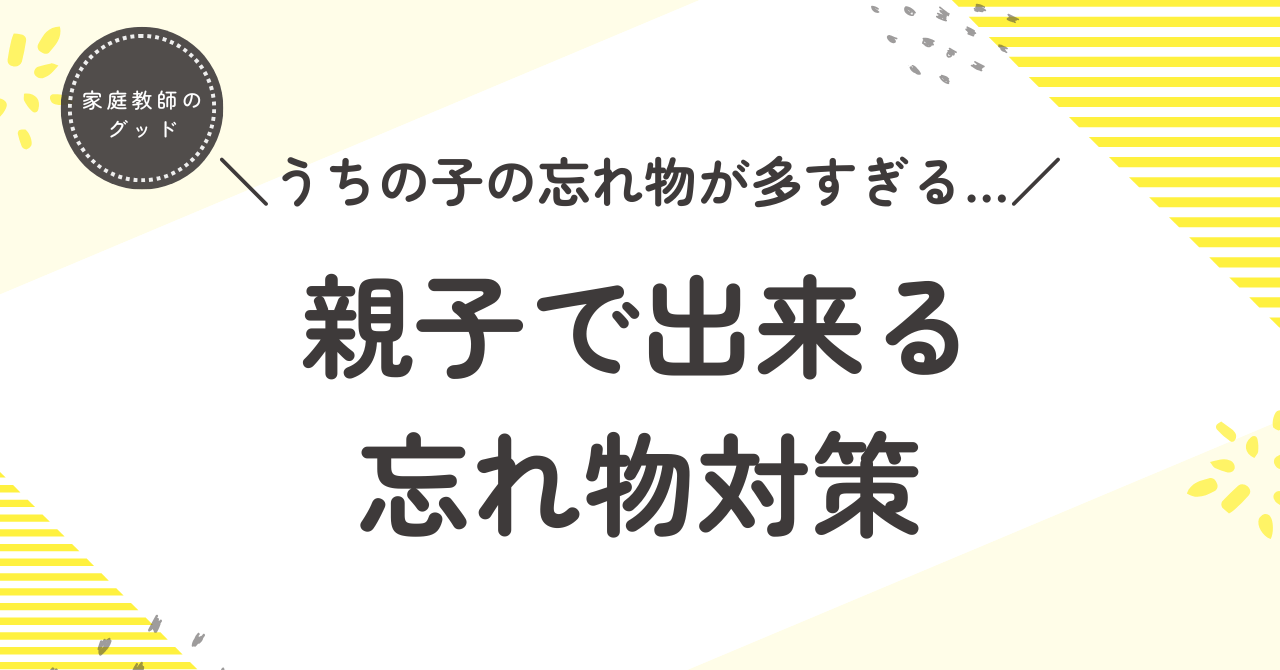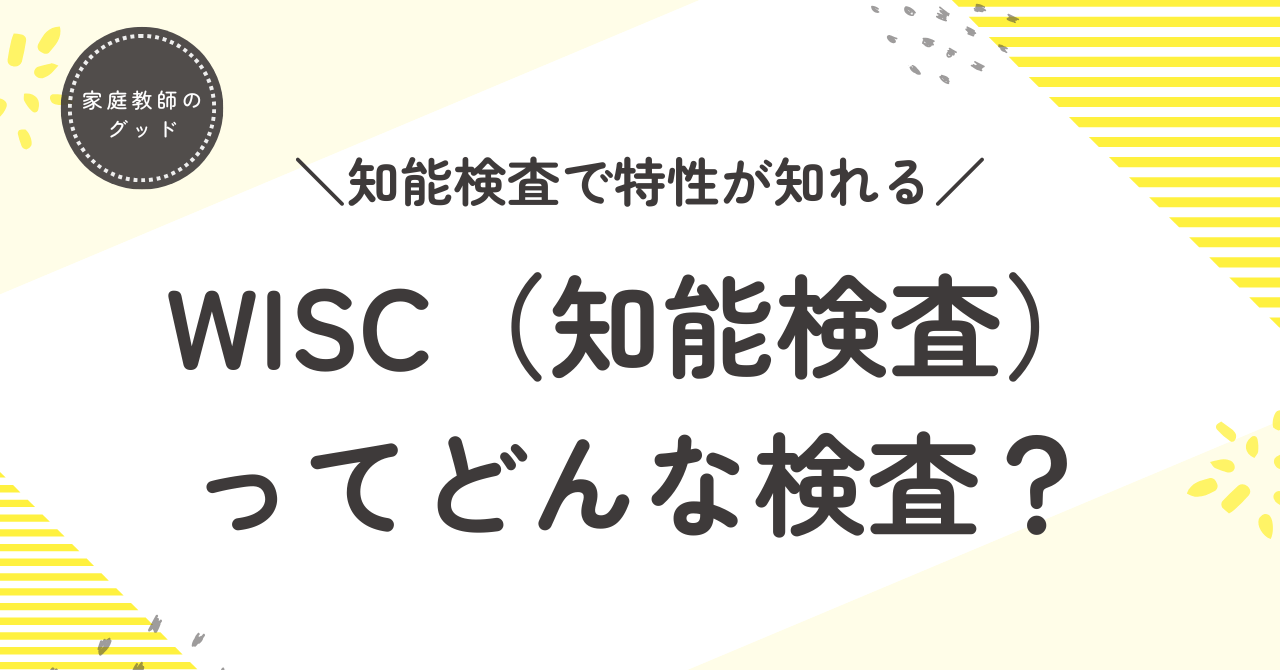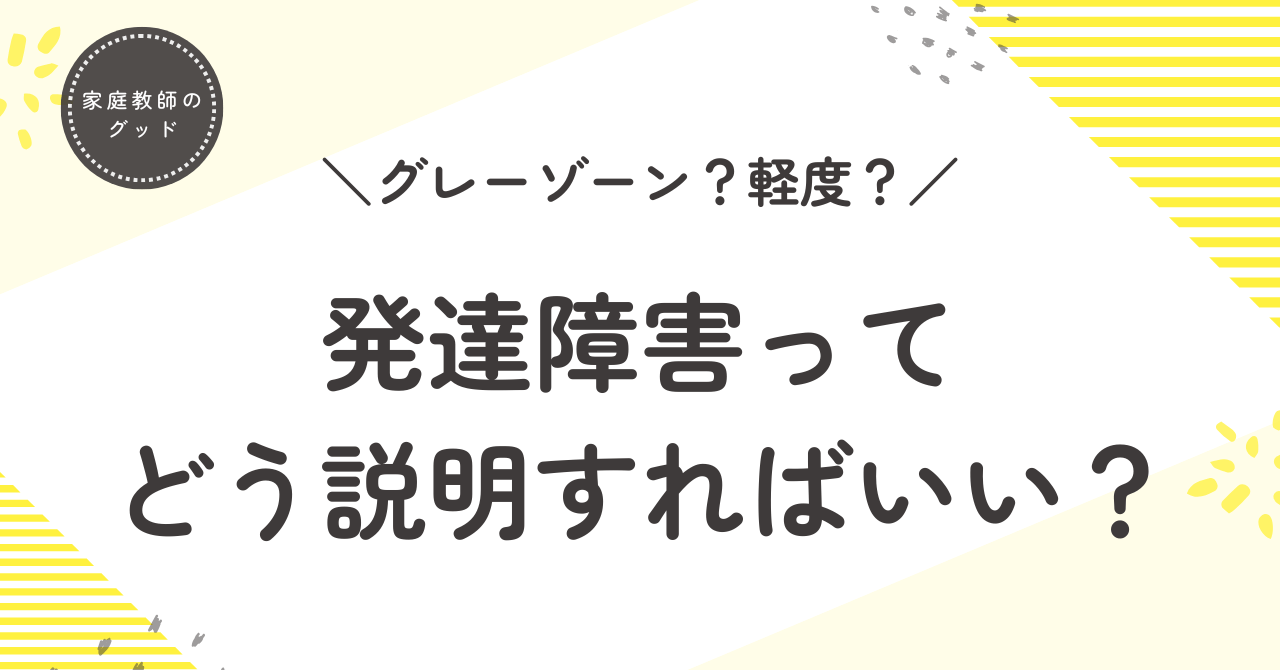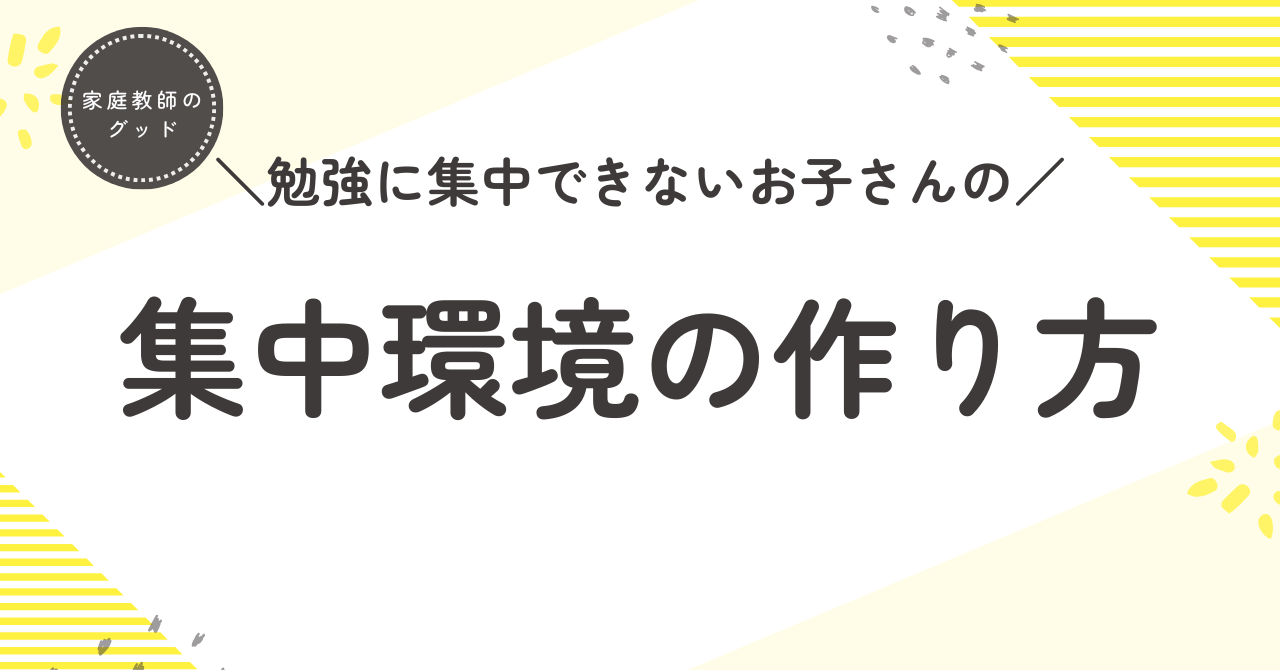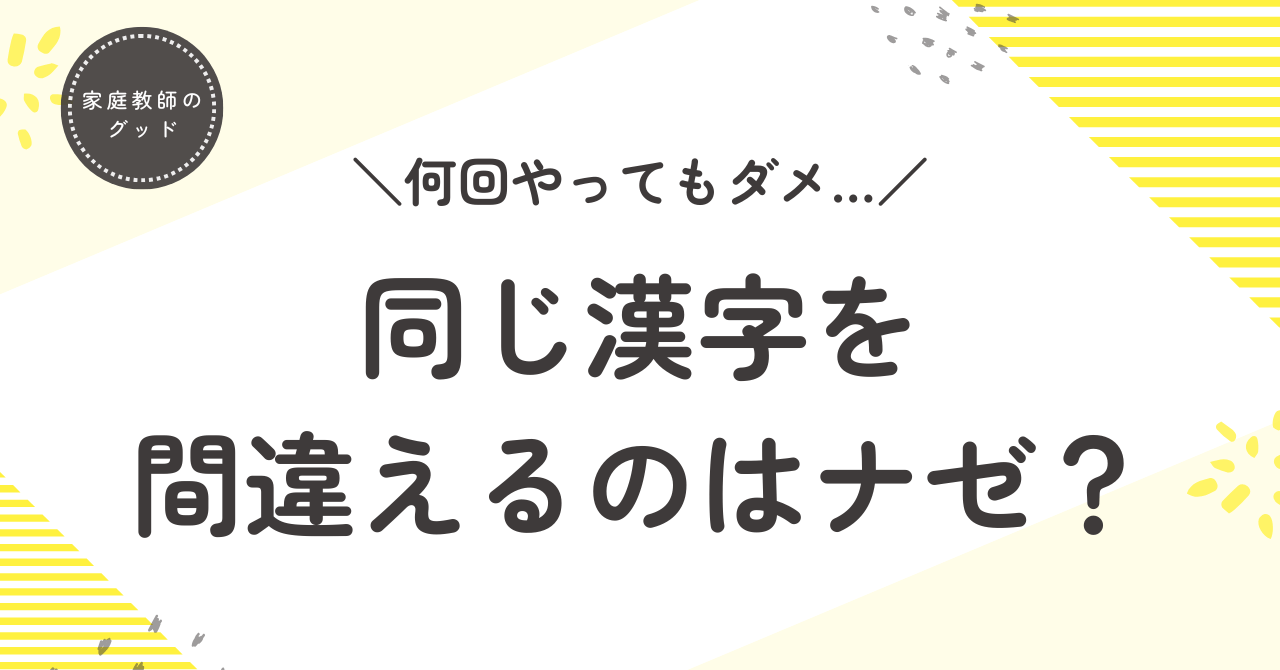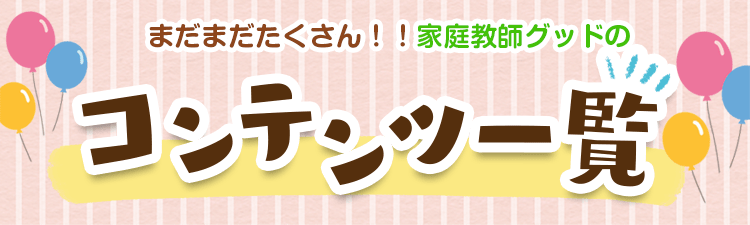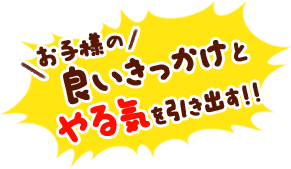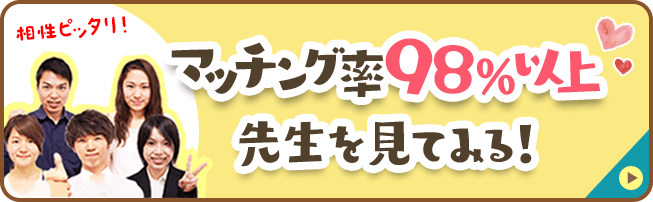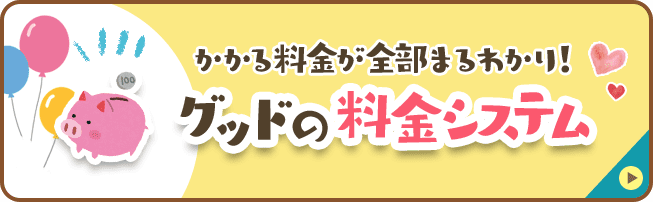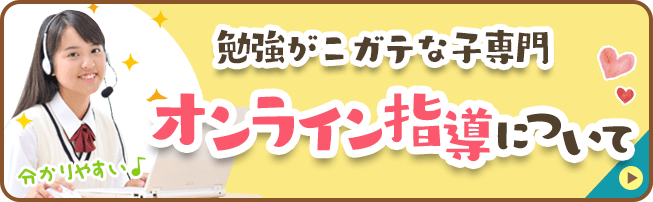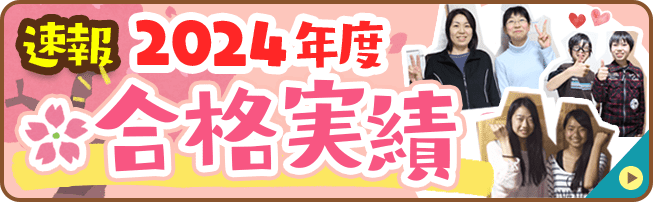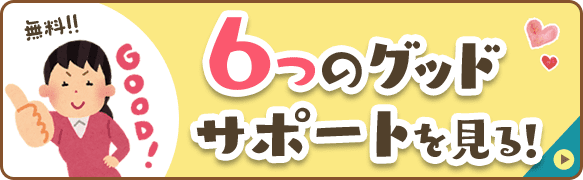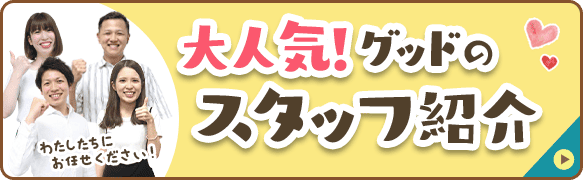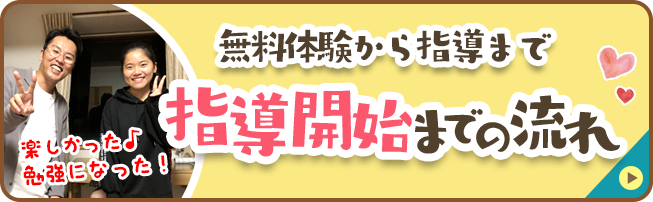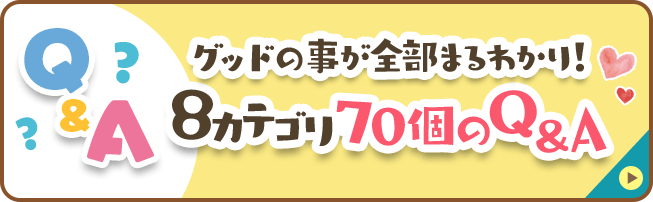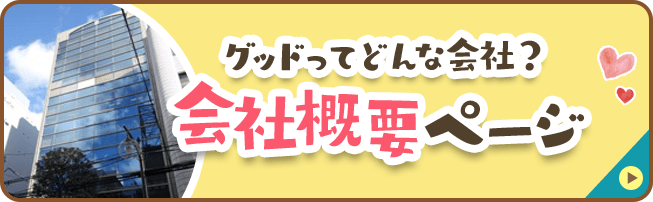ASD(自閉スペクトラム症)の子どもとの接し方
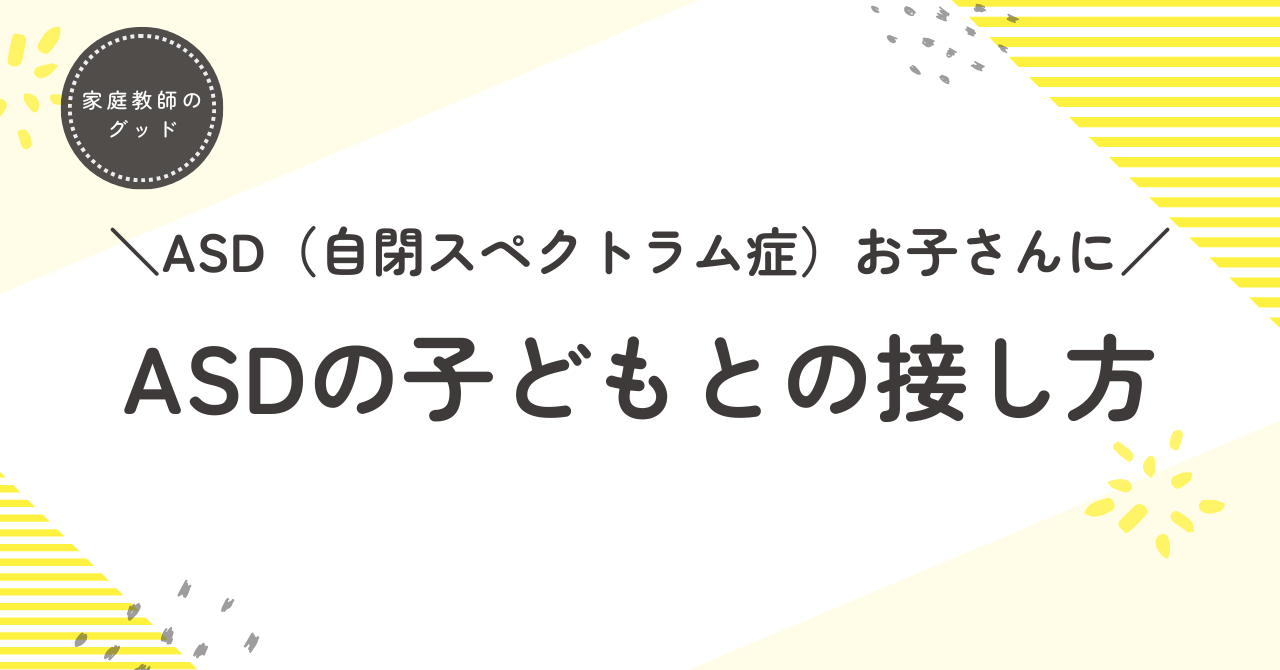
「ASDって、聞いたことはあるけど何?」「ASDの診断が出たけど、まずはどうすればいいの?「勉強はどうやって進めればいけばいい?」
今回は、ASD(自閉スペクトラム症)について、お話します。ASD(自閉スペクトラム症)は、発達障害のうちのひとつです。
発達障害には、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動性障害)、SLD(限局性学習障害)といったものがあります。
発達障害の特徴は、それぞれの特徴が強く出ることや弱く出ることがあります。
発達障害と診断されていない人でも、大人になって、「私も、もしかして?」と思うほど、その特性の出方はさまざまです。
自分に置き換えてみるとわかりやすいのではないでしょうか?
「私はこれが好き」「私はこうありたい」という気持ちがあったとします。
だんだんと「私はこうじゃないと嫌!」という思いが強く出れば、こだわりと捉えることもできます。
一概に言えませんが、大人のASDは、職場や近所のコミュニティなど、人間関係に苦労することが多い印象です。
だからこそ、大人になるまでの間、「どのような経験をしてきたか」ということが本人の生きやすさを決定づけるものと言えるでしょう。
子どものASDは、大体3歳頃までに、子どもの行動などから、違和感を感じるため、他の発達障害に比べると早期に以下のような特徴が出ると言えるでしょう。
- つま先歩き、ジャンプを好む
- こだわりがある(ガーゼやタオルの生地、おもちゃの種類、服の好み)
- 一定の動きをするものへの執着(回るものやオンオフの切り替えできるもの)
- 目を合わさない
- 抱っこや接触を嫌がる
- クレーン現象(子どもが自分の要求を表現するために、親や先生の手を使ってそのものへと誘導しすること)
- マネやごっこ遊びができない
特に、成長していく中で、困りを感じやすいのが、社会性(対人関係)・コミュニケーションといった特性です。
相手の気持ちや言葉の先の想像力が足りないため、人間関係をこじらせやすいのです。
では、どういった特徴が主にあるのか具体的に見ていきましょう。
「自分の好きなことや興味のあることを一方的に早口に話してしまって、相手に話す余裕を与えていないように感じます」
「何を話す時間なのかわからず、雑談や話し合いの時間が苦痛だと言っています」
「運動会や音楽会といった行事で、時間割が急に変わると、パニックになってしまいます」
「運動会のダンスが苦手で、学校に行きたくないと話しています」
「ちょっとした遊びのルールがわからなくて、自分の思い通りにやりたい気持ちを抑えきれないときがあります」
このような、相談者様からの声をよく聞きます。その子の特徴を理解した上で、コミュニケーションの機会をつくっていくことが大切です。
注意点や接し方
- 頭ごなし否定するのではなく、その子自身を認めて一緒に考える
- 子どもの興味関心のあることを探り、共に楽しみ、喜び合う
- 学校のことや友達のことを話す機会をもち、その時その時の感情を切り取って考える
- 絵本や動画、イラストなどを使って、誤解やすれ違いがあった場合はすぐに理由がわかるよう説明する
- 見通しをもたす
家庭教師のグッドでは、その子の興味関心に合わせた、学習の見通しをもたせる指導を行っています。
例としては、まず、今日の学習内容を、①番目→②番目→③番目というように提示します。
順番がわかると、何からやっていけばいいかがわかり、終わりがみえます。学習時間も合わせて伝えることで、時間の感覚や自分の進めるペースをつかむこともできます。
このとき、内容的に基礎から応用にいくようにする場合もあれは、とっつきやすい学習やその子にとって楽しい学習から始める場合、好きな順番を決める場合もあります。
自分の意思で決めることで意欲を高めることができます。
こういった学習計画は、なかなか自分一人で立てることが難しいことが多いのです。
学習計画をともに作る際に、どんなことが好き?だとかどんなことに興味がある?などと質問をしていく中で、自然とコミュニケーションを図ることができます。
次に、学習目標です。「〇〇ができるようになる」という目標を立てて、勉強を進めることでゴールが明確になります。
例として、「漢字を書いて覚える」という学習に、目標を立てて挑んでみてはどうでしょう。
漢字学習は苦手意識が強い子が多いのですが、目標を設定すると変わってきます。
目標→「漢字の部首や辺に気をつけて書く」「部首や辺って聞いたことがある?」「聞いたことはあるけど〜」「このくさかんむりっていう部首は知ってる?」「あ!花にもついてる!たしか、前にも〜」といって漢字ドリルや教科書のページをめくる。
「そういえば、さっき飲んでた飲み物にもついてるんだけどわかる?」「えー、あーーー!お茶??」「これは難しいけど、わかるかな?赤くてつぶつぶで、おいしいフルーツなんだ?」「そう!いちご(苺)も、くさかんむりに母って書くんだ。お母さんの母は、漢字で書けるかな?」
こういった調子で、今まで意識していなかった、部首や辺をとらえることで、部首や辺が同じ違う漢字の復習や予習にもなります。
漢字を絵のように説明したり、部首や辺といった漢字の部分を色で分けて説明することで、驚くほど早く幅広く覚えることができるのです。
最後に、振り返りです。振り返りと聞くと、「楽しかった?」「できた?」「難しかった?」などといった感情に意識が向きがちです。
もちろん、そういった感情に寄り添うことも大切ですが、ASDの子どもたちには、漠然と「どうだった?」「どう思った?」などの感想を聞く際には、注意が必要です。
何をどう答えていいのか、わからず会話が止まってしまうことがあるからです。そんなときには、具体的に質問しています。
「今日の目標は何だったか覚えてるかな?」「正解!漢字の部首や辺に気をつけて書くだったね」すかさず、ほめる。ノートを見返して目標を確認していても、正解!はなまる!なんです。
目標を達成できたかどうかに目を向けていれば、褒めるポイントが少なくなってしまいます。
目標が何だったかがわかれば、「今日はとんな部首があったかな?」「どんな漢字がでてきたかな?」「この漢字は、画数が多いのに書けたね」などとたくさん振り返りができ、同時にほめるポイントも出てきます。
「今日は覚えた漢字が多いからお母さんやお父さんに教えてあげてね」「他にも、くさかんむりの漢字があったら、先生(担当の家庭教師)にもぜひ教えてね」と言って、次の褒める機会を増やす仕掛けを作ります。
このように、たった一つの授業の中に、ほめるための仕掛けをたっぷり用意しておくのです。そして、すかさずほめる。
これは、もちろん、ご家庭でもできることではあります。わかってはいても、忙しい日常で、早くして!と急かしたり、あれもこれもできていないとがっかりしたり。
「ほめるポイントなんて、ありません」なんておっしゃっている保護者の方もたくさん見てきました。
毎日、やらなければいけないタスクが多すぎて、ご家庭ではそんな余裕なんてないですよね。
学習というのは、成長が目に見えてわかりやすいものと言えるでしょう。
家庭教師グッドと一緒に、ほめるポイントを見つけてみませんか?