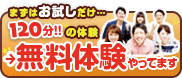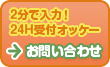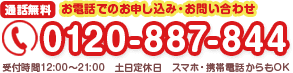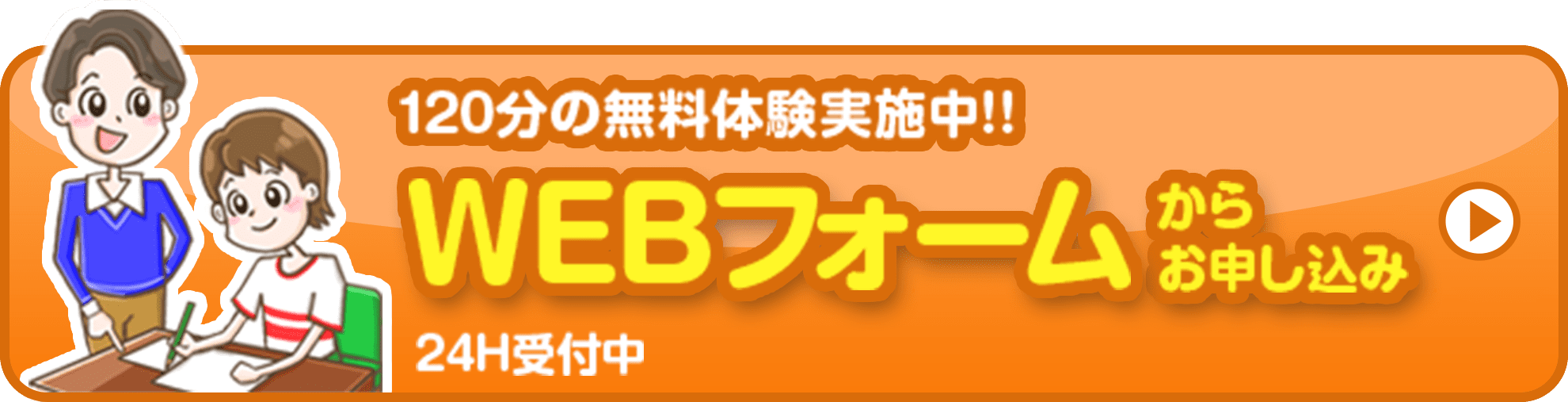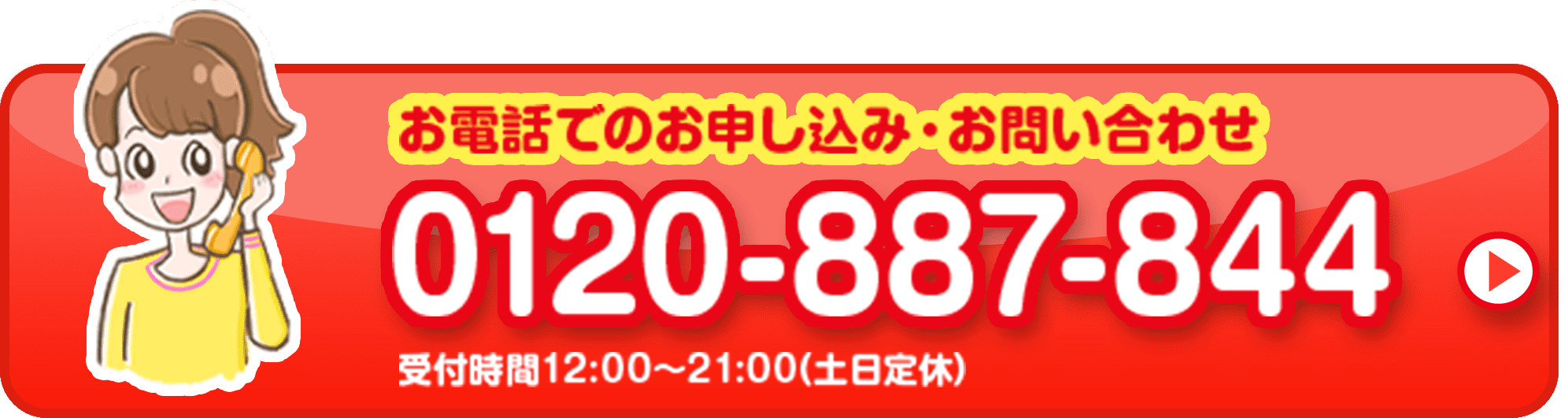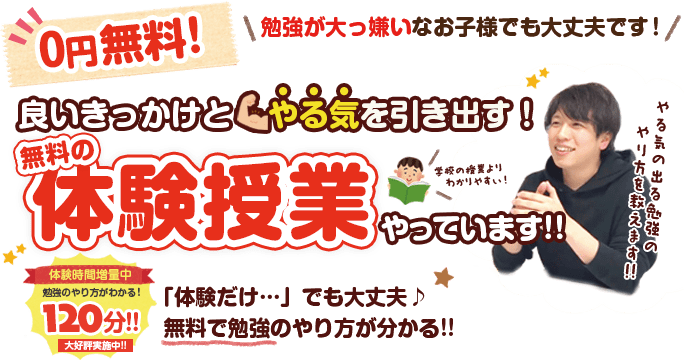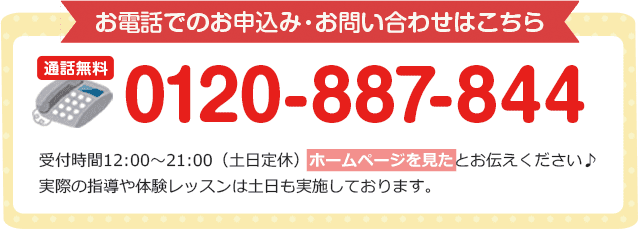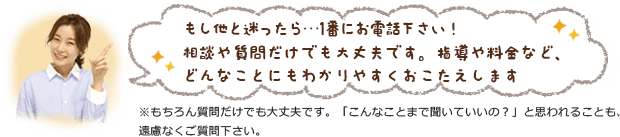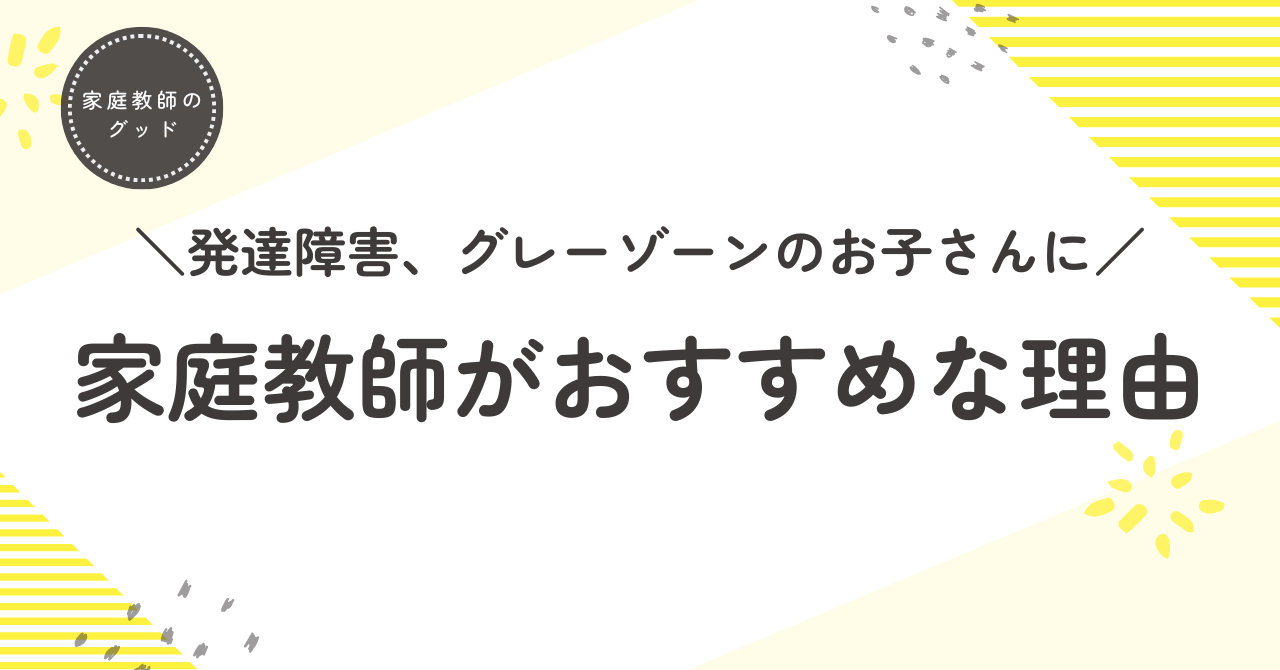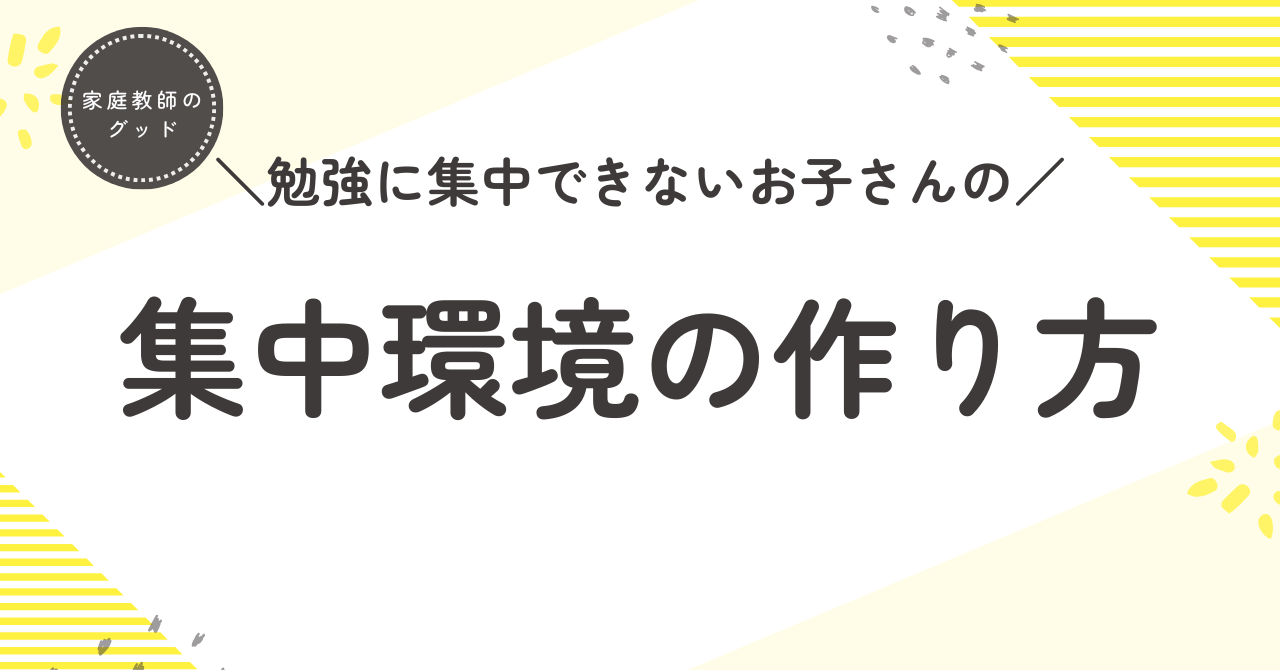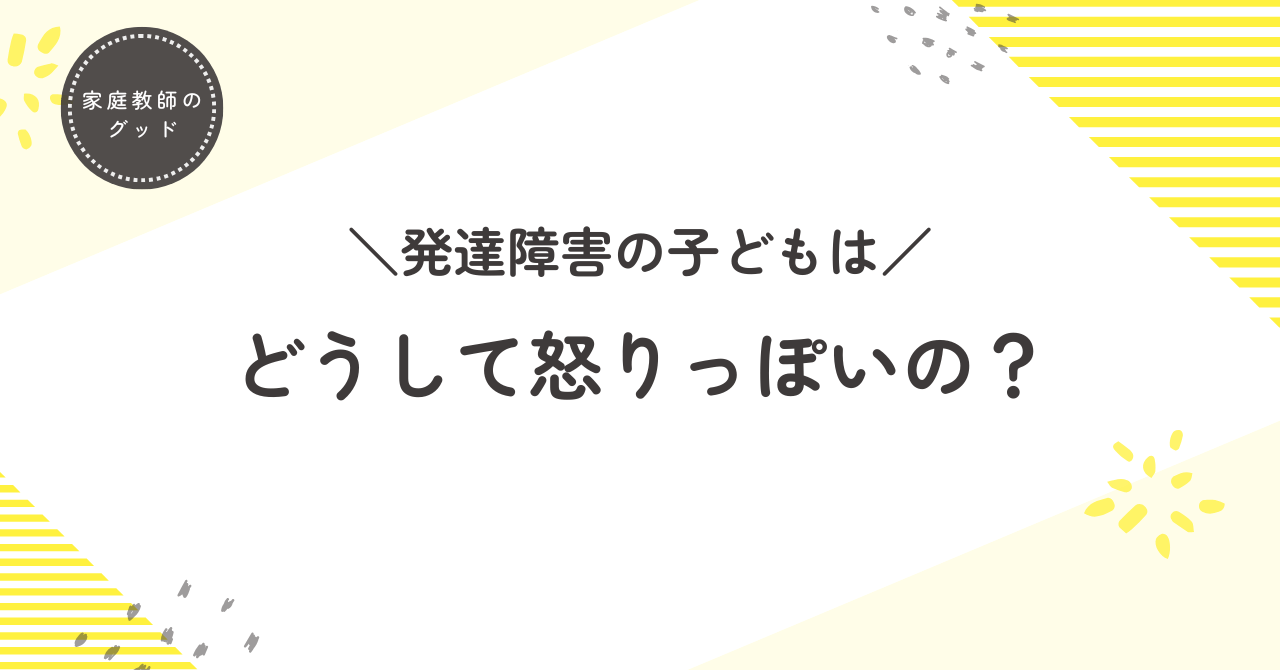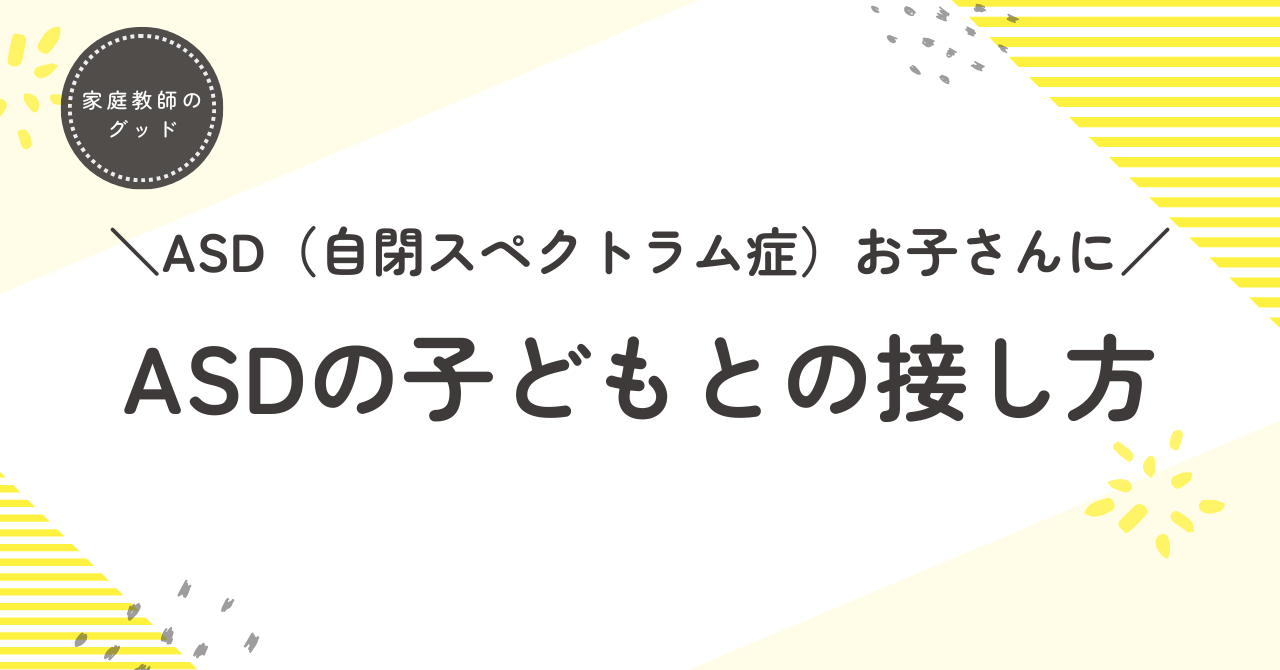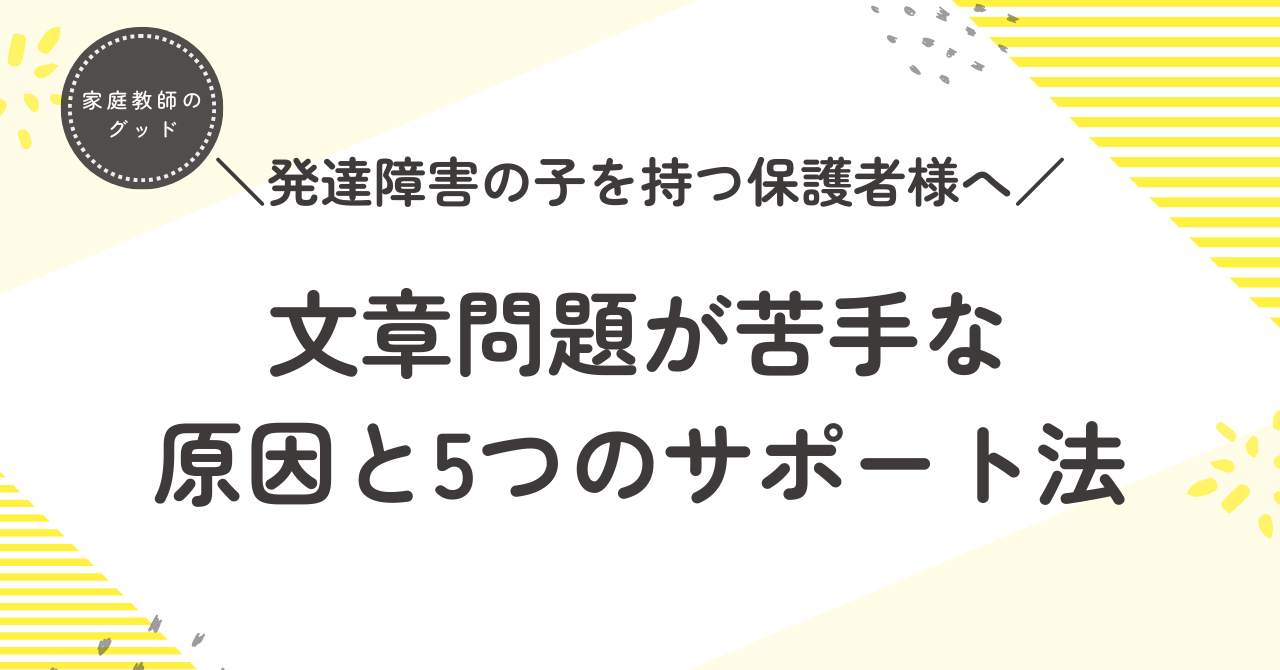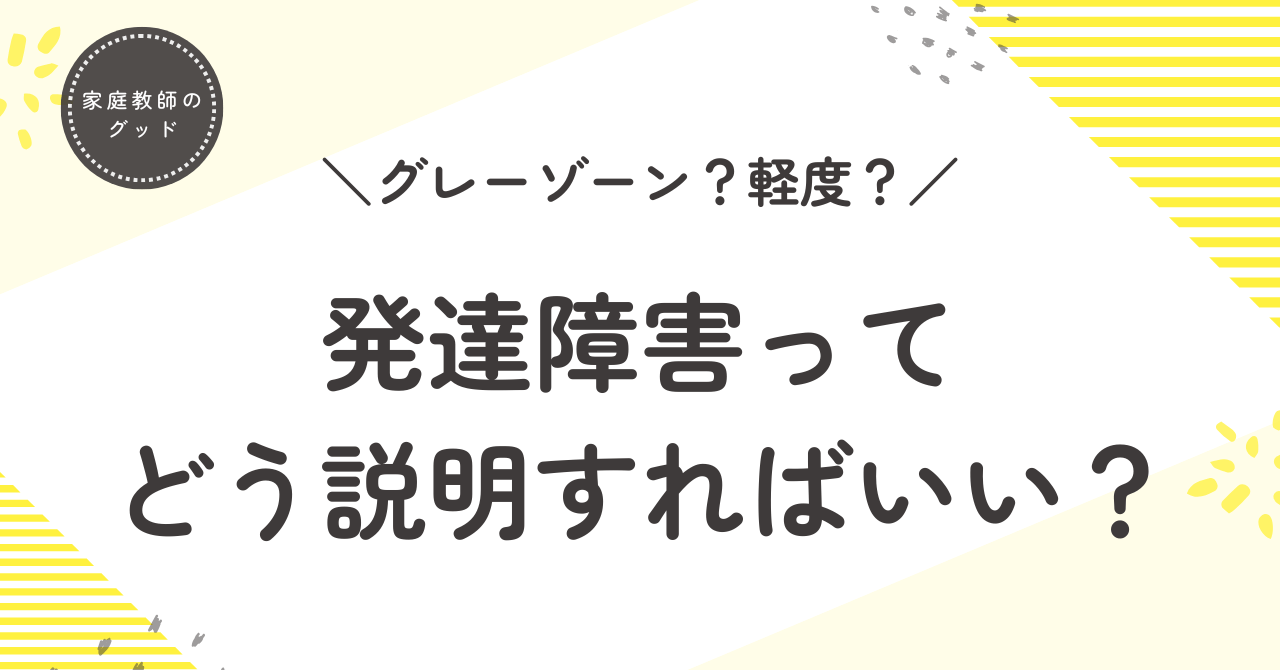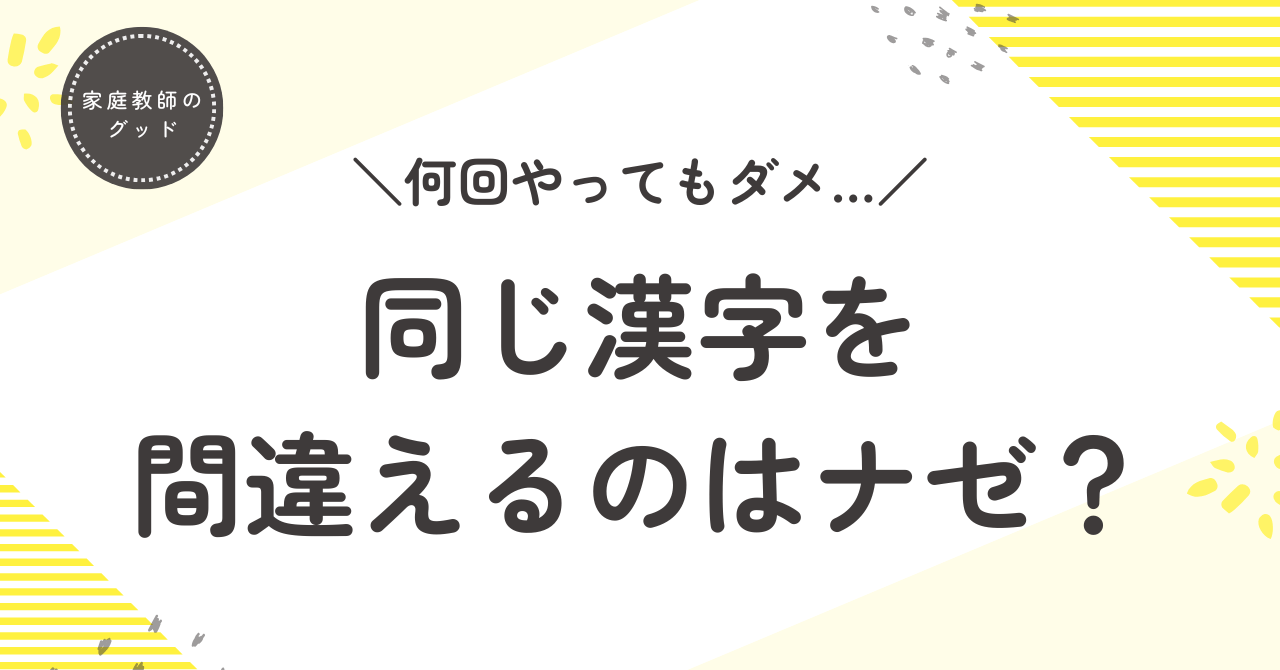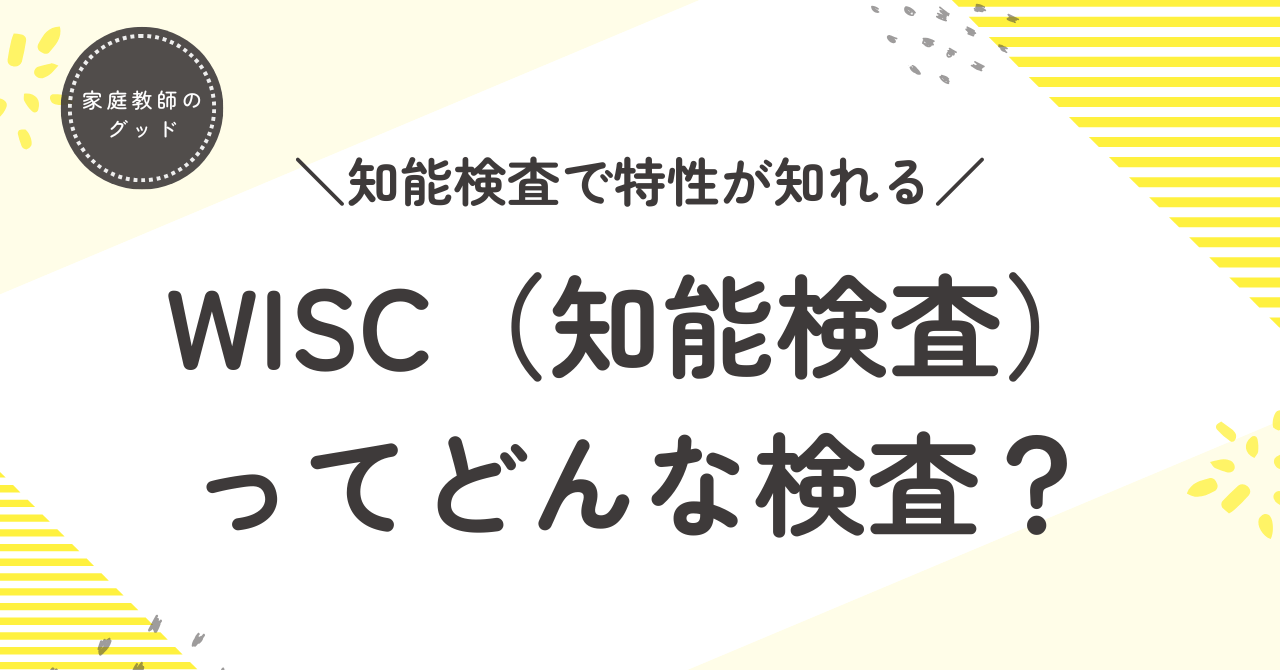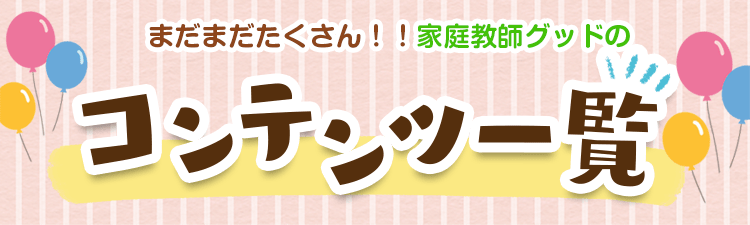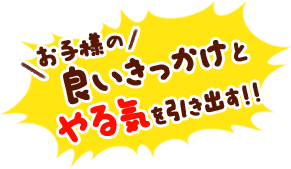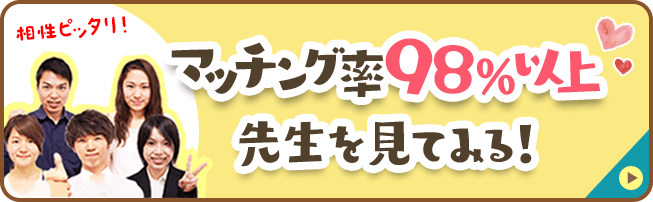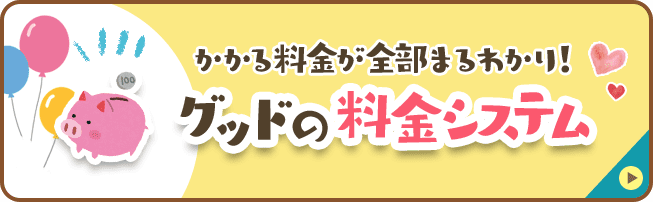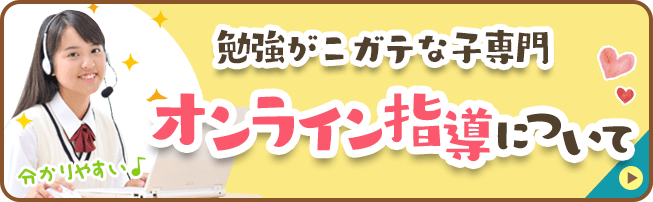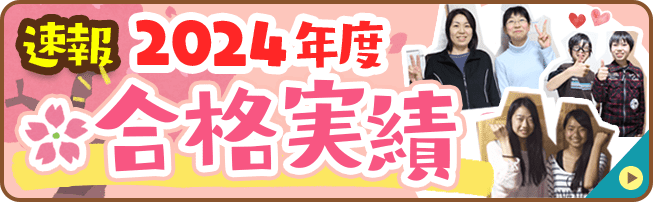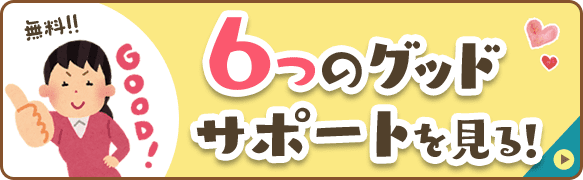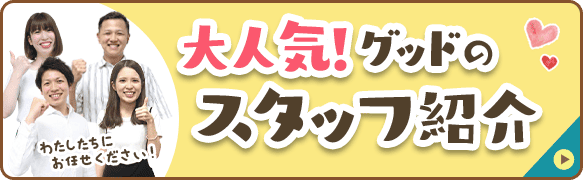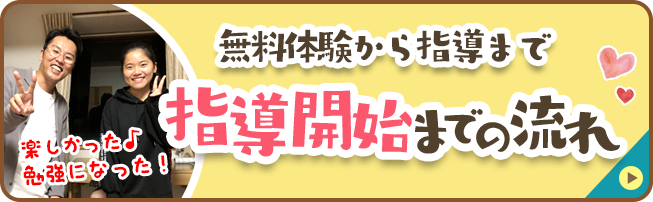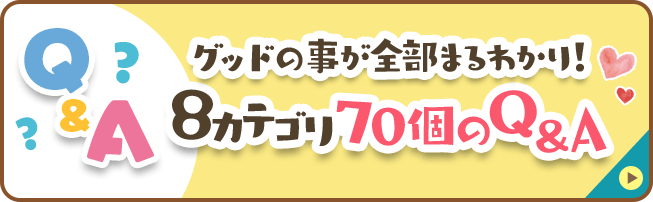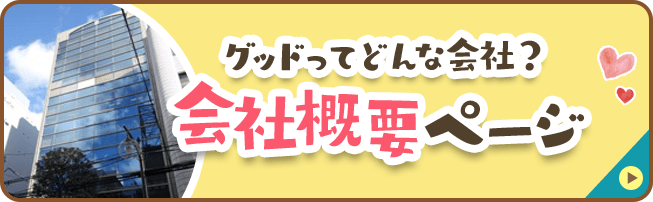みるみる伸びる!ASDの子供の学力を向上させる勉強方法をご紹介
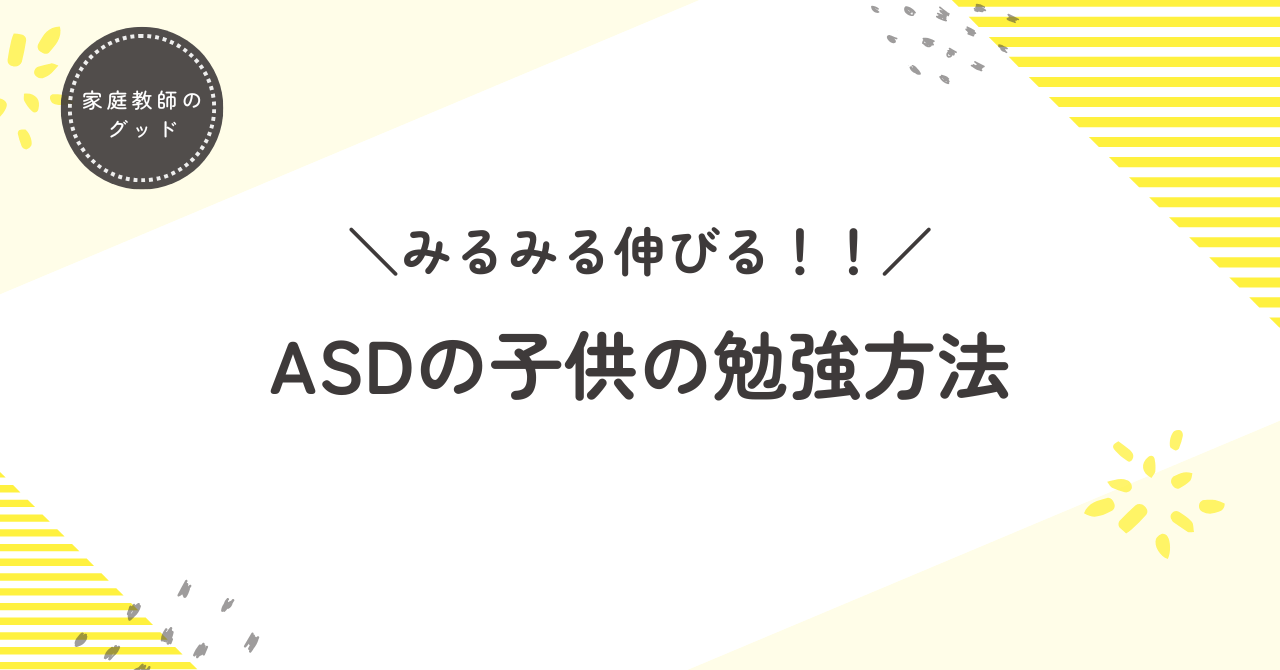
「ASDの子供が勉強に集中してくれない」
「ASDの子供の学力を向上させたい」
ASD(自閉スペクトラム症)の子供には対人関係や社会的なやりとりが苦手な傾向があり、勉強に悪影響が出ることも少なくありません。勉強を前向きに取り組んでもらえず、悩んでいる親御さんも多いはず。
この記事ではASDとはどのようなものなのかを解説し、ASDの子供の学力を向上させる勉強方法もご紹介します。ASDの子供の学力に不安を感じている方はぜひじっくり読んでみてください。
ASDとは?
ASDとは自閉スペクトラム症のことであり、発達障害の1つです。相手の考えていることを読み取ったり自分の考えていることを伝えたりが苦手といった特徴があります。こだわり行動があることでも知られています。
ASDには、学力の低下が見受けられることも少なくありません。一方で、特定の強化については強い関心を示し、驚異的な学力が見られることもあります。
ASDの代表的な症状
ASDの代表的な症状には、以下のものがあります。
- 場の空気を読み取れない
- 比喩や皮肉が伝わらない
- 相手の気持や暗黙のルールが理解できない
- 言われたことを表面的に受け取ってしまう
- こだわりが強い
- 手先が不器用
- 感覚刺激に敏感(鈍感)
ASDといった同一の診断をされたとしても、その症状には個人差があります。
たとえば、物事の順番に強い執着がある子供もいれば、勝敗にこだわる子供も。勉強が苦手な子供もいれば、昆虫や機械系など特定のものに強い興味を示し、周囲から一目置かれるようなタイプも少なくありません。
ASDの診断方法

アメリカ精神医学会が発行している『「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版』に記載されている診断基準に従って、ASDの診断がされています。
なお、『「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版』では、
- 「対人関係や社会的なやりとりの障害」および「こだわり行動」による問題が複数起きている
- 日常生活・社会生活で影響が出ている
- 6か月以上症状が継続している
の3つを満たした人をASDとしています。
ASDの原因
ASDの原因は脳にあるとされています。生まれつきのものであり、脳の機能に何かしらの不具合があると考えられていますが、まだ詳しくは分かっていません。
なお、親のしつけ方や育て方はASDとは無関係であることがわかっています。
ASDの治療方法

ASDは脳の機能の不具合が原因であるため、完治することはないとされています。したがって、本人の特性にマッチした療育や教育が基本となります。
癇癪(かんしゃく)などの症状によっては、抗精神病薬などが使用されることもあるようです。
ASDの子供の学力を向上させる5つの勉強方法
ASDの子供も勉強方法によっては、学力が格段に向上することがあります。
こちらでは、ASDの子供の学力を向上させる5つの勉強方法をご紹介します。
- その子供に適した言葉で指導する
- 本人のこだわりを尊重する
- 指示や予定を明確に伝える
- 「なぜ?」に丁寧に答える
- 予習に力を入れる
この機会に、自分の子供にマッチした勉強方法を探してみてくださいね。
その子供に適した言葉で指導する
ASDの子供と接するにあたって特に重要になるのが、その子供に適した言葉を用いるというもの。
そもそも、ASDの子供はイントネーションや雰囲気で物事を察するのが苦手です。なので、どちらともとれる言葉は使わないようにしましょう。語尾も曖昧にせずに言い切るのがおすすめです。
大きな声が苦手、早口が苦手という子供もいるので、子どもに合わせて小声で伝えたり、ゆっくり伝えたりなどの工夫も大事です。
本人のこだわりを尊重する
ASDの子供にはさまざまなこだわりがあります。そのこだわりを矯正しようとすると反発を招くだけなので、受け入れることが肝心。
子供の中には、「鉛筆じゃないと嫌」「この消しゴムじゃないといや」など特定のものに執着することもあります。それらを周囲が受け入れてあげられれば、子どもの勉強意欲も向上するでしょう。
指示や予定を明確に伝える
ASDの子供は、言葉以外から意図を把握するのが苦手な傾向があります。したがって、「計算問題を頑張ろう」と伝えるのはNG。「3ページから5ページまでの問題を解こう」と明確に伝えるのがおすすめです。
また、ASDの子供は想定外の物事に対応できない傾向もあります。あらかじめどのような勉強をするのか、予定を決めて伝えておきましょう。
「なぜ?」に丁寧に答える
ASDの子供は、細かな部分まで気になる傾向があります。「なぜ?」と思うことが多く、その疑問が解消されるまで苦痛で不安やイライラが募るといったことも少なくありません。
子供に「なぜ?」が発生した場合は、丁寧に答えましょう。マンツーマン系の塾など先生に質問できる場合は、すぐに質問して疑問を解消させるのがおすすめです。
自習および宿題など、すぐに質問ができない場合は、問題に目印をつけるなどしたりメモをしたりして、あとで先生に質問させましょう。
予習に力を入れる
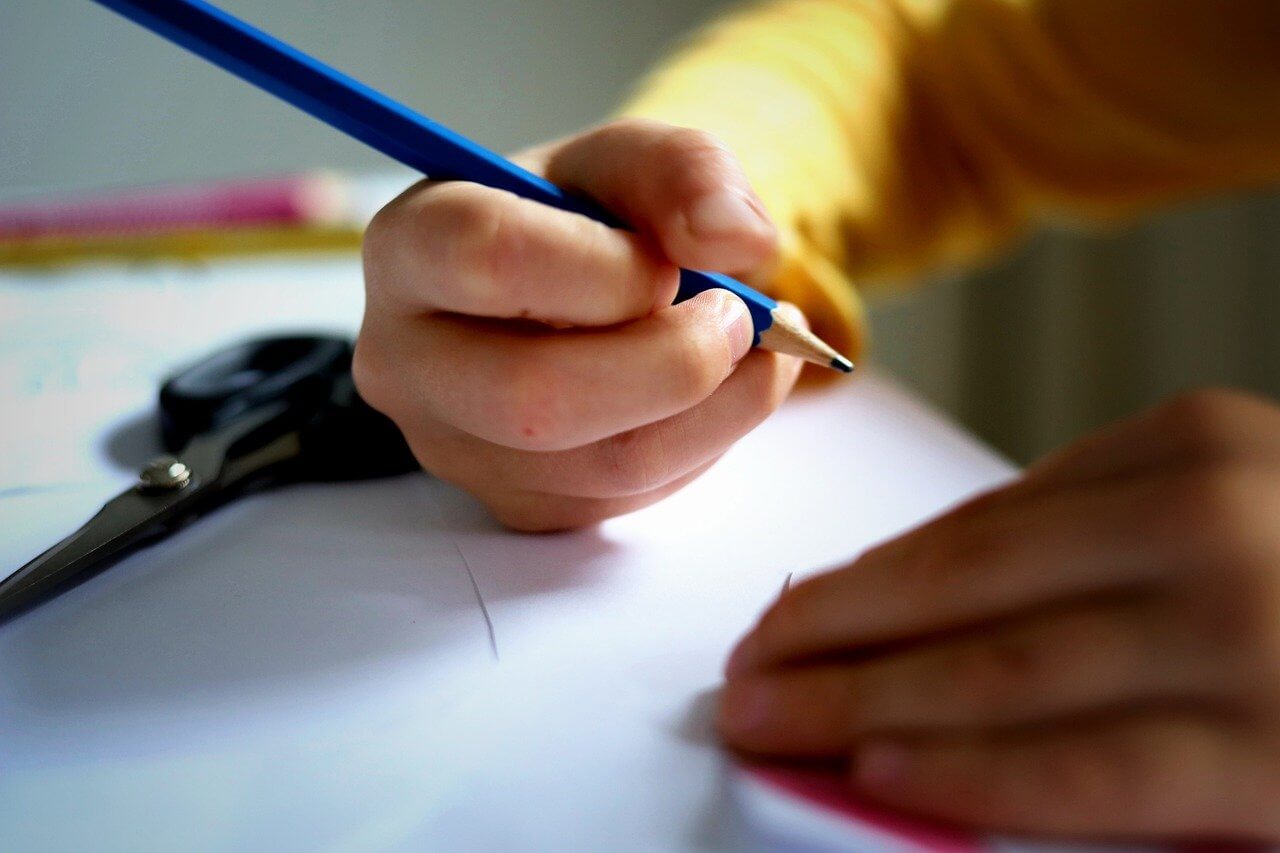
ASDの子供は、変化や新しい情報が苦手とされています。授業で新しいことを習うと混乱し、何も考えられなくなるケースも珍しくありません。そうなると周りから取り残され、勉強がつまらないものになってしまいます。
そこで重視してほしいのが、予習に力を入れるということ。教科書やテキストの予習をおこなうことで、学校が塾でおこなわれる勉強にもより対応できるようになります。未知の内容に対する不安も和らぐため、勉強への意欲も湧くようになるはずです。
まとめ
ASDの子どもの学力が向上する勉強方法をご紹介しました。
ASDの子供にも個人差があり、どの勉強方法がマッチするかはわかりません。さまざまな勉強方法を試し、どの方法がもっとも良い結果になるのか確かめてみることが大事です。
家庭教師のグッドは、これまでに多くのASDの子供の学力を向上させてまいりました。勉強の仕方からやる気を出させる方法、勉強に集中できる環境の作り方なども指導させていただいております。
家庭教師のグッドの講師は経験も豊富で、ASDの子供の特性も理解しております。無料体験授業もおこなっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。