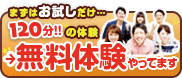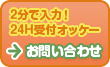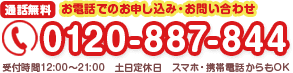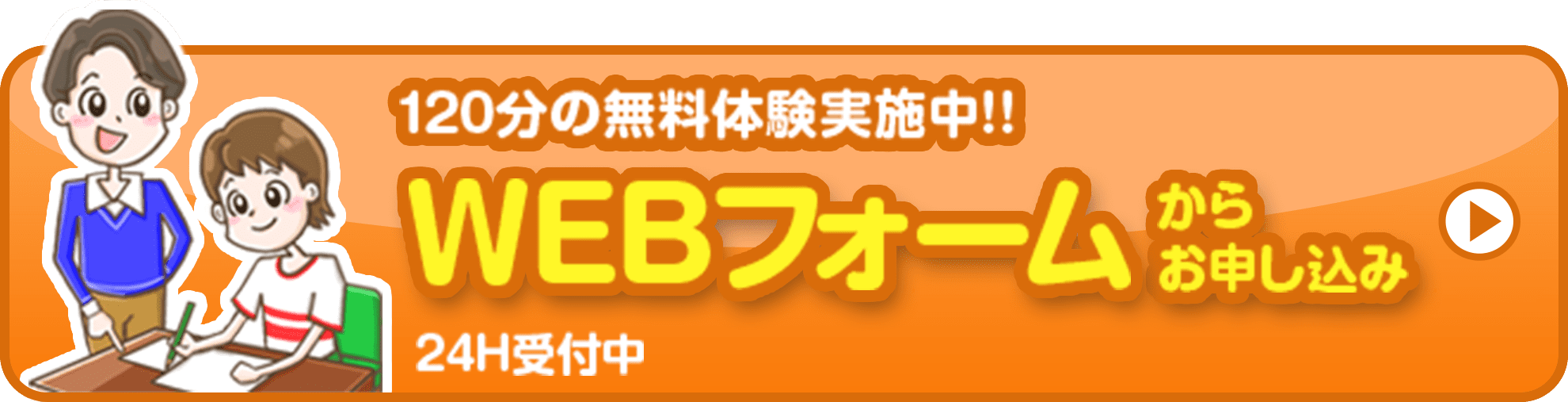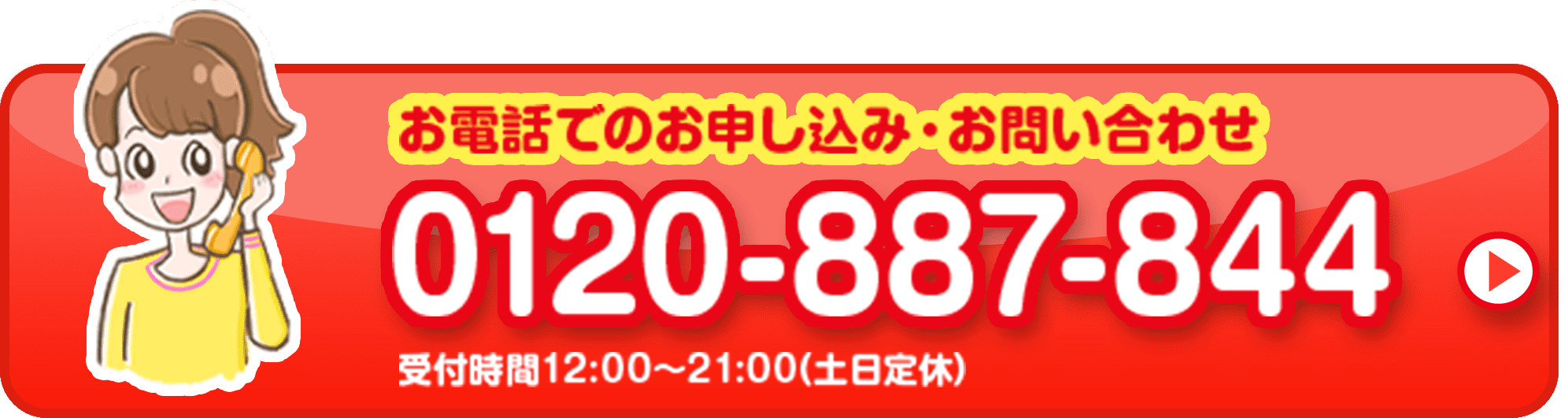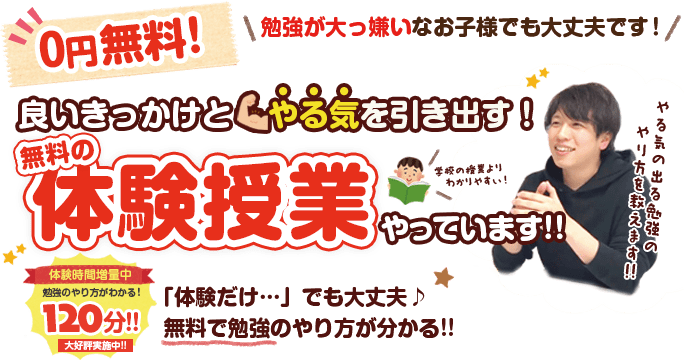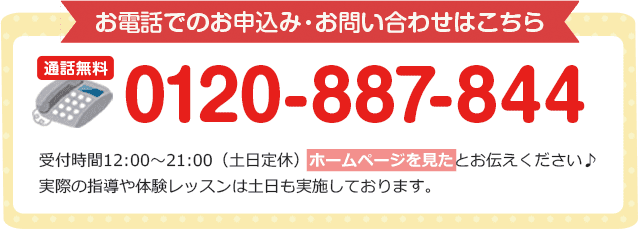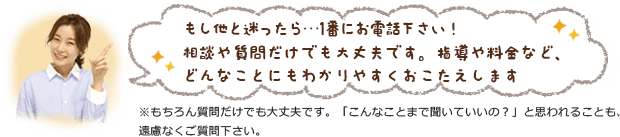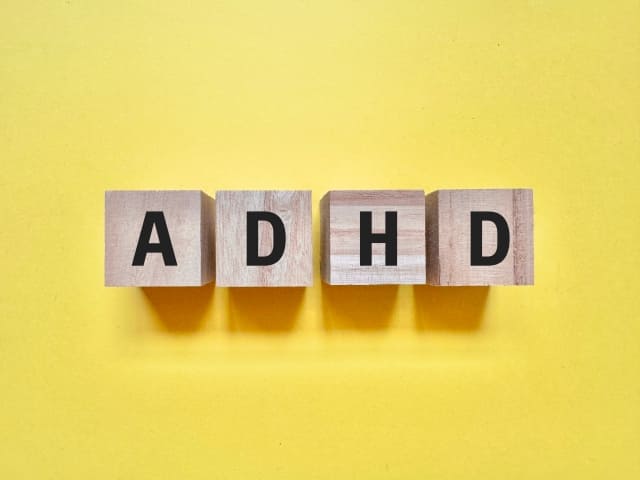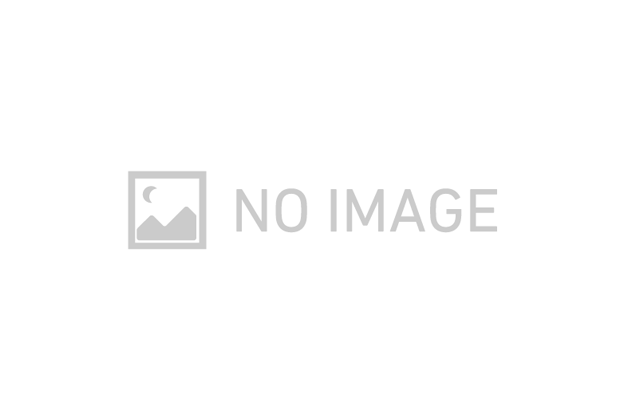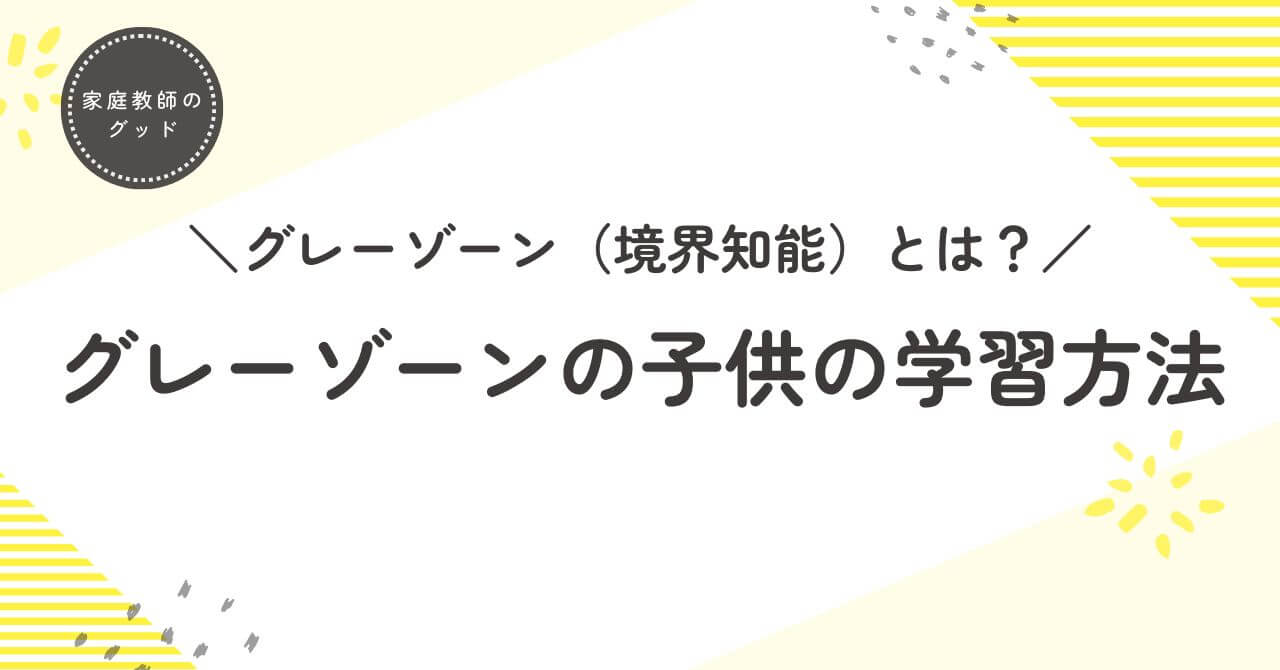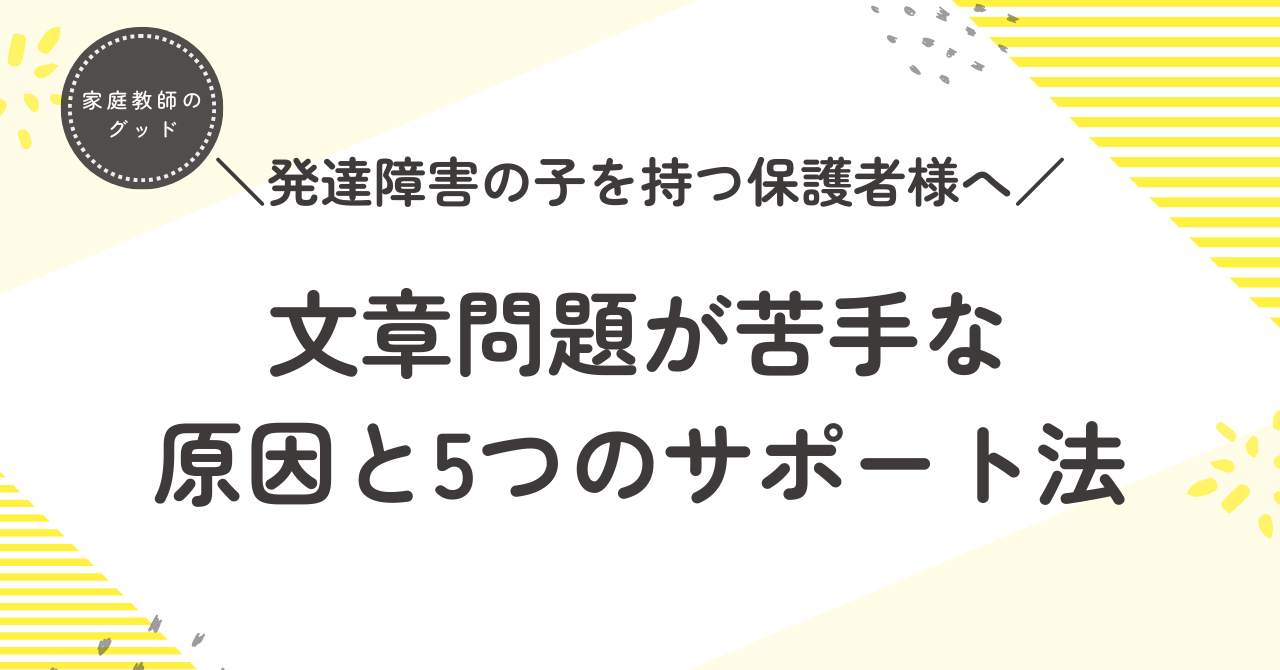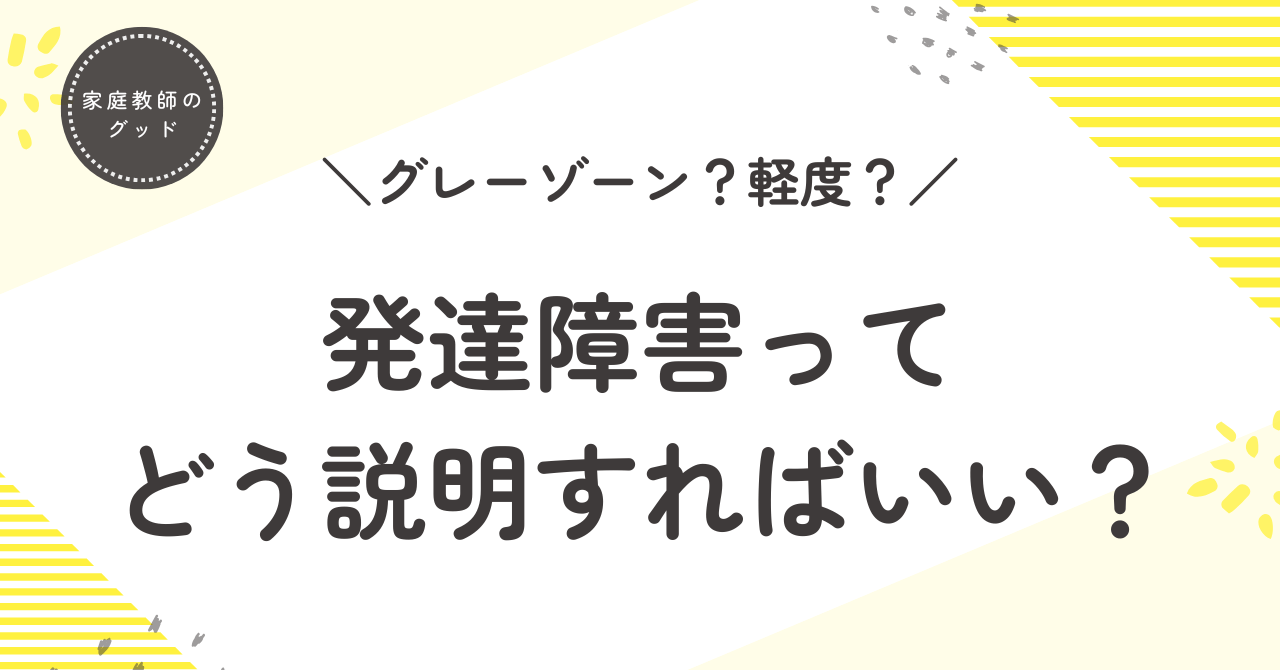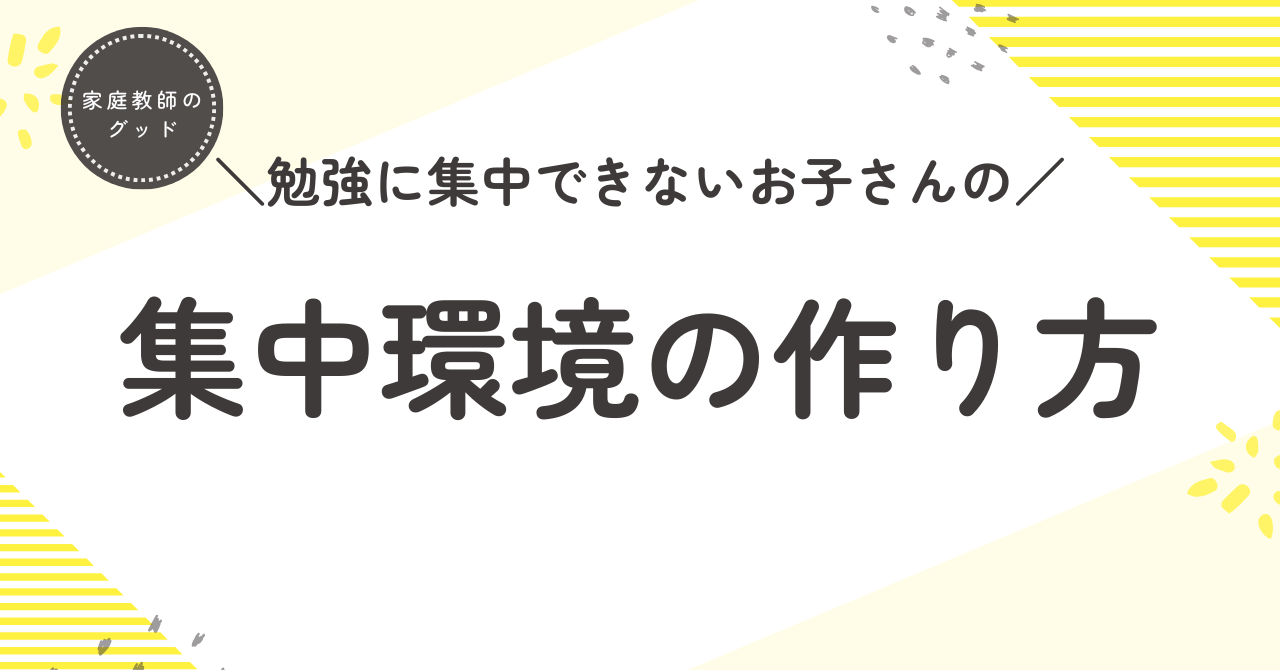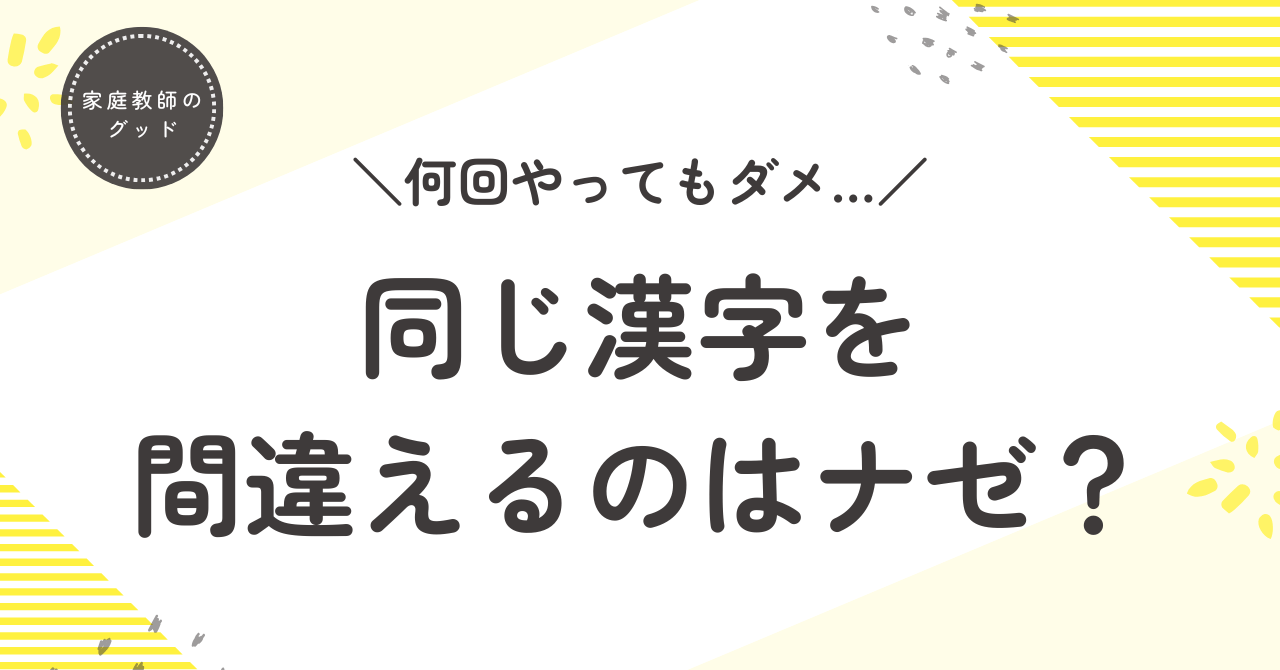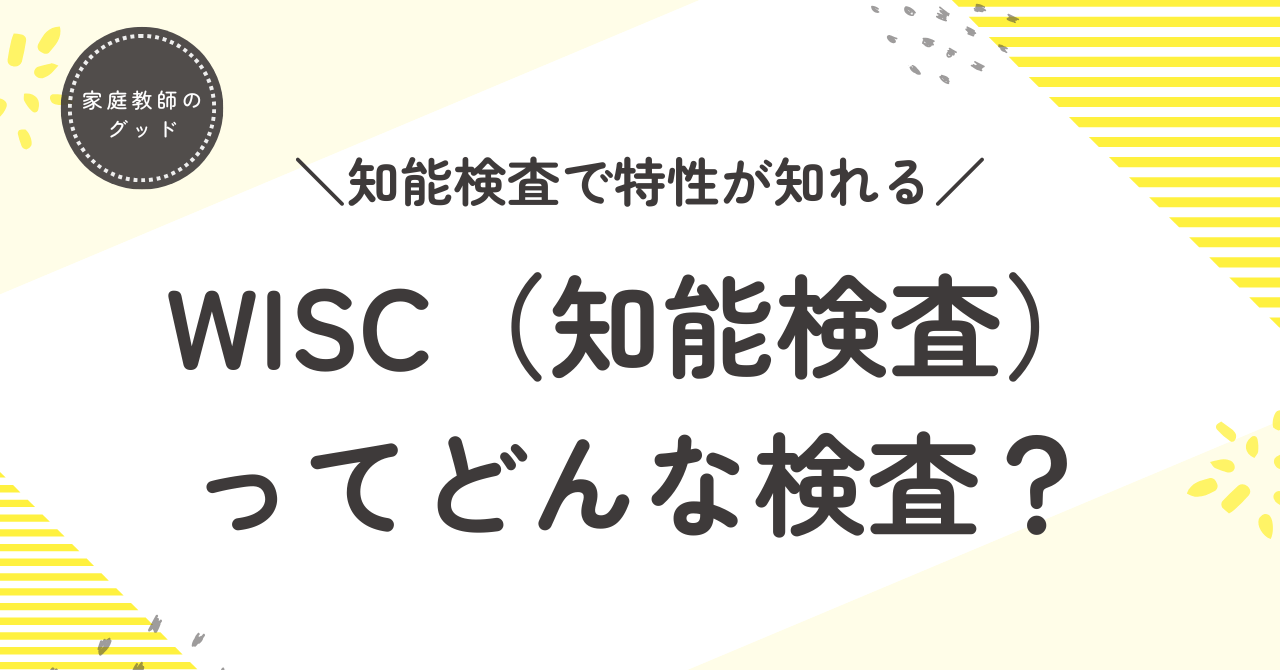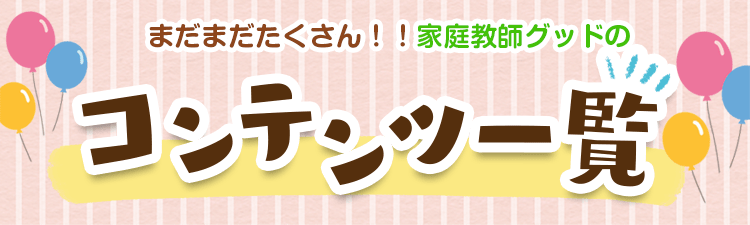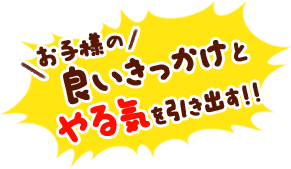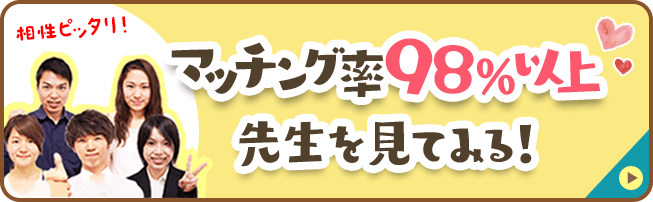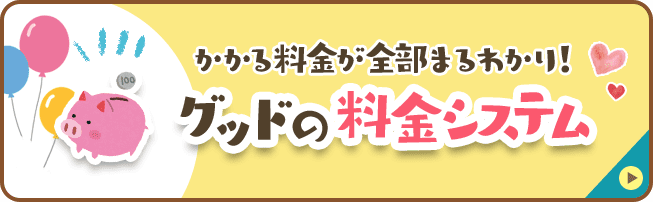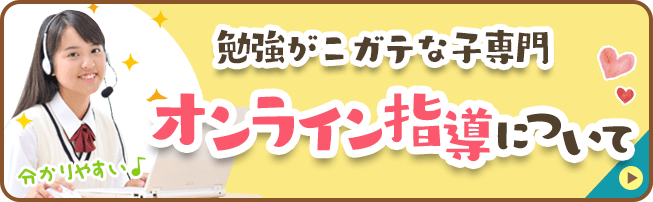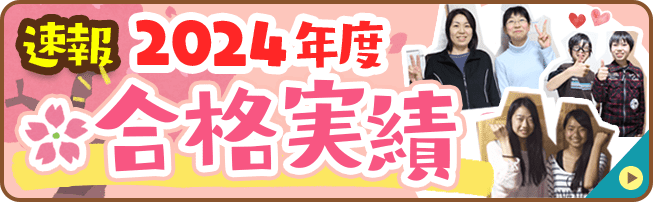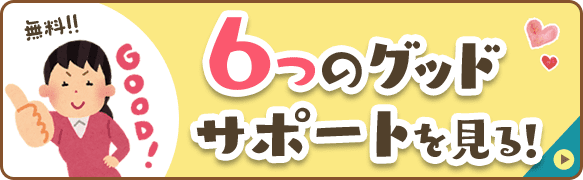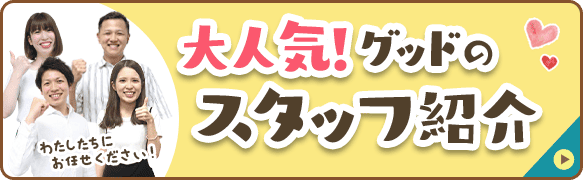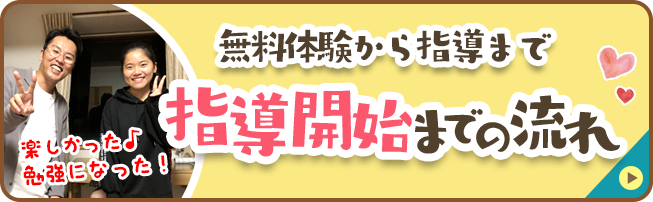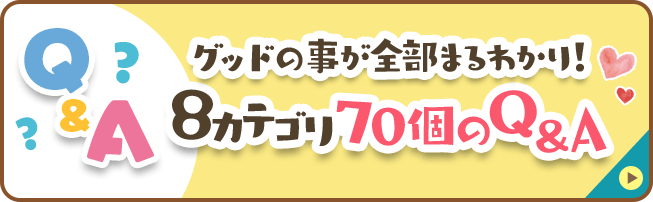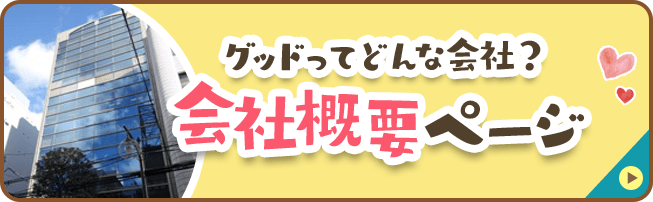ASD(自閉スペクトラム症)とは?ASD児 がやる気になる勉強法6つもご紹介!
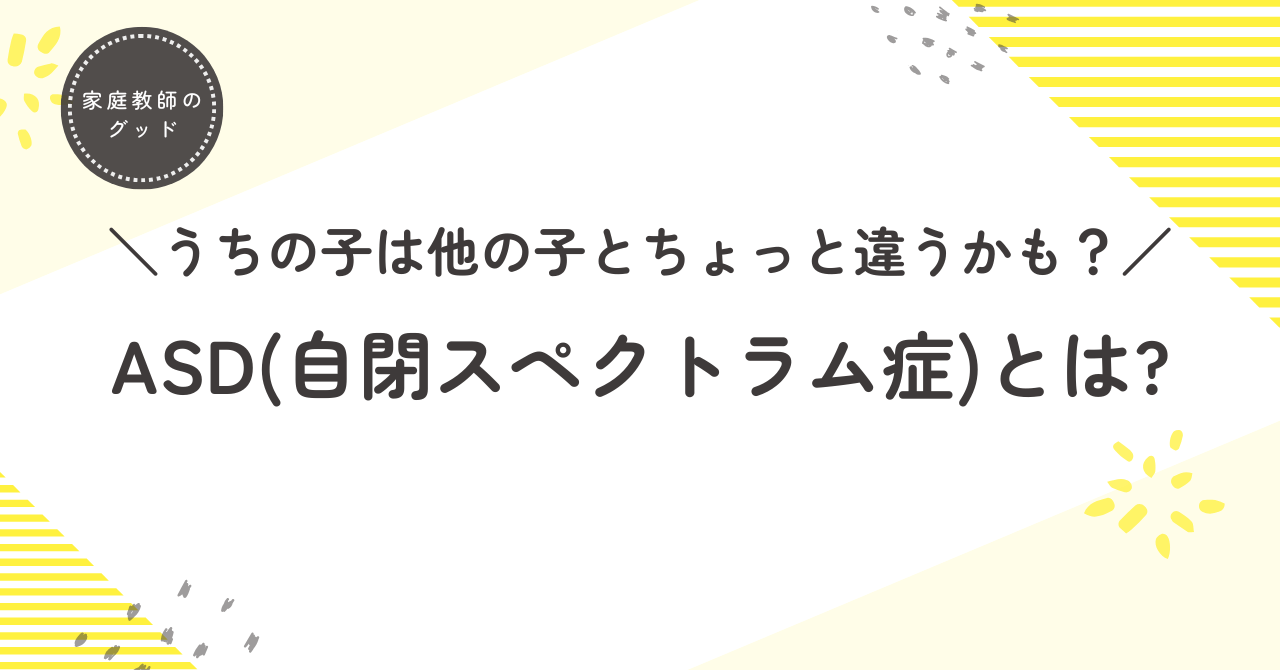
「子どもがASD(自閉スペクトラム症)で勉強に集中してくれない」
「ASD児でも学力向上する勉強法が知りたい」
お子さんがASD(自閉スペクトラム症)で悩んでいる方は多いと思います。ASDだと勉強に集中できず、周りの子どもに勉強で置いていかれることも少なくありません。
しかし、諦めることはありません。ASD児にはASD児にマッチした勉強法があります!
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)とは何かを解説し、そのうえでASD児がやる気になる勉強法もご紹介します。ASD児の学力についてお悩みの方は、ぜひじっくり読んでみてください。
ASD(自閉スペクトラム症)ってなに?
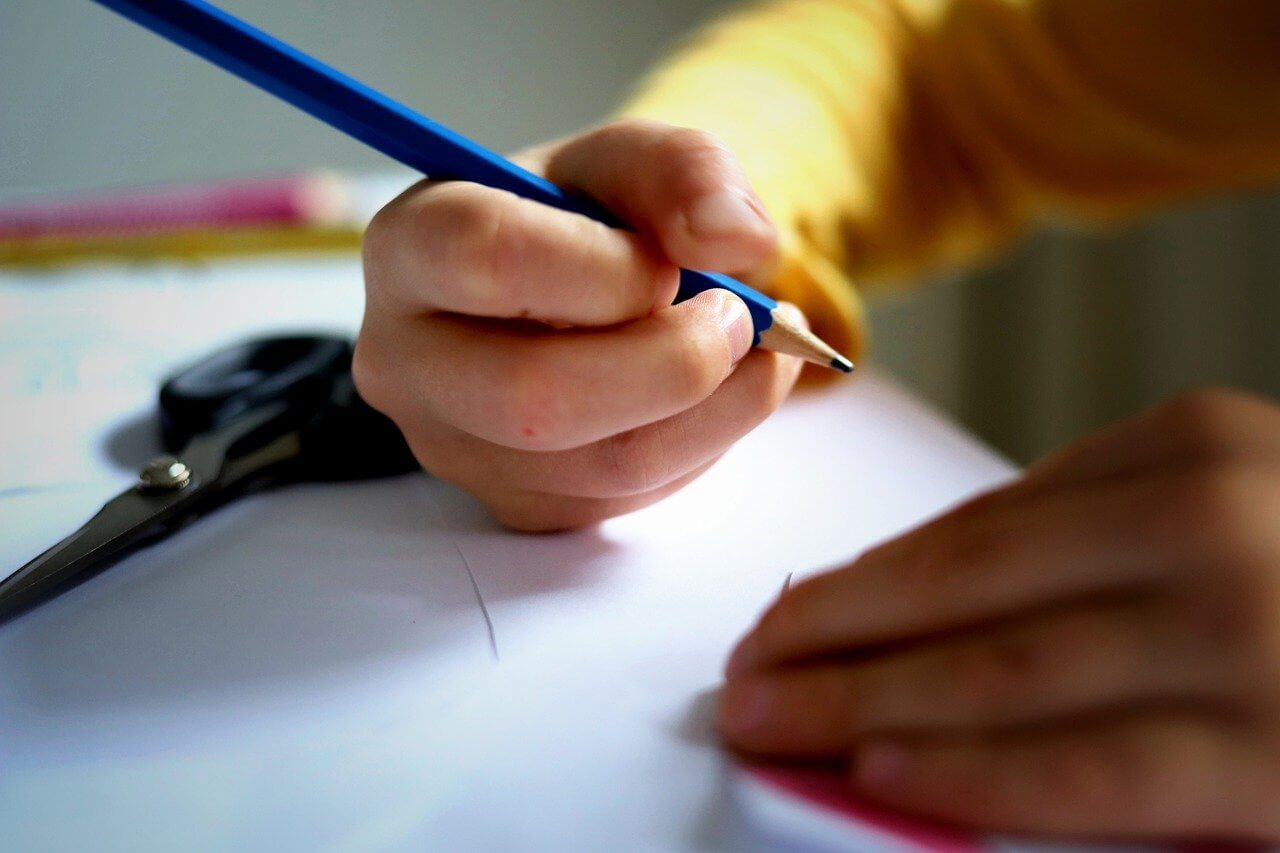
ASD(自閉スペクトラム症)とは発達障害の一種であり、対人関係が苦手であったり強いこだわりがあったりといった特徴を持っています。
近年では早期発見されるようになっており、早ければ1歳半のときにおこなわれる乳幼児健康診査や3歳児検診で指摘されるケースも増えてきました。
ASDの場合は知的能力障害(知的障害)を伴わないこともあり、言葉の発達が良好である場合は成人になってから初めて診断されることも少なくありません。
ASDの人の割合は、およそ20人から50人に1人とされています。男性に多く見られるのも特徴の1つであり、女性の約2倍から4倍といった研究結果もあるようです。
ASDの原因は不明とされていますが、近年では生まれつきの脳機能の異常による可能性が高いとされています。なお、育て方やしつけについては関係ないとされています。
ASD(自閉スペクトラム症)の症状例
ASDの症状には以下のようなものがあります。
- 視線が合わない
- 表情が少なかったり不自然だったりする
- 独り言が多い
- 話を展開するのが苦手
- 一人遊びが多い
- 食べ物の好き嫌いが多い
- 体を前後に揺すったり、くるくると回ったりする
- 特定のものに強い興味を示す
上記の症状例はあくまで一例であり、ASD児であったとしてもすべてが当てはまるわけではありません。
程度の強さも個人差があるので、正確な診断のためには専門の医師や心理士による観察や検査が必要不可欠です。
ASD(自閉スペクトラム症)の治療法
ASDは脳の障害と考えられており、現時点で完治させる治療法はありません。
病気と捉えるよりも持って生まれた性質(特性)と捉え、一人ひとりに合わせた教育的な方法で対処していくのが適切と考えられています。
ただし、攻撃性があったり不眠であったり、自傷行為に走ったり、パニックを引き起こしたりする例もあります。
そういった症状が出ている場合には、対処療法的に薬物が処方されることになるでしょう。
ASD児がやる気になるおすすめの勉強法6つ
ASDの特性がある子どもでも学力を伸ばすことは十分に可能です。
ただし、合っている勉強法と合わない勉強法があることも事実です。
ここでは、ASD児がやる気になるおすすめの勉強法を6つご紹介します。
- 勉強の予定を立てその通りに実行する
- 曖昧な指示はNG!明確に伝える
- 小さい疑問にも丁寧に回答する
- 繰り返し学習させる
- 図や絵を取り入れる(デジタル機器を導入する)
- 褒めて自信をつける
お子さんに合いそうなものがあったら、ぜひチャレンジさせてみてください。
勉強の予定を立てその通りに実行する

ASD児が苦手なのが、想定外の出来事です。混乱してしまい、思考停止に陥ってしまうことも少なくありません。
そこで実施してほしいのが、前もって勉強の予定を立てその通りに実行するというもの。
たとえば、20時から20時45分まで漢字ドリルをやって5分休憩し、20時50分から21時30分まで算数の問題集を解くと決めて実行します。
勉強をルーティン化すれば、ストレスなく勉強に取り組めるようになるでしょう。
曖昧な指示はNG!明確に伝える
ASDを持つ子どもにとって苦手なのが、曖昧な指示です。
たとえば、「計算練習を頑張ろう」と言われても、どう頑張ればよいのかわかりません。
何問解けばよいのかもわからず混乱することもあります。
したがって、勉強の指示を与える場合は「5つの計算問題を解こう」と具体的な内容にしてみてください。
指示を明確にすることで、余計な負担を与えずに済みますよ。
小さい疑問にも丁寧に回答する
ASD児によくあるのが、人が気にならない細かなことが気になってしまうというもの。
わからないまま進むことが苦痛となり、不安やイライラが募るケースも少なくありません。もし子どもから質問された場合は、1つずつ丁寧に答えましょう。
ただ、親御さんがすべての勉強の質問に答えるのは難しいと思います。
なので、塾や家庭教師の利用を検討しましょう。
繰り返し学習させる
学習を定着させるためにも、繰り返し学習させるのがおすすめです。
ただし、ASD児は長時間の学習が苦手な傾向にあるため、なるべく30分程度など短く区切ることをおすすめします。
図や絵を取り入れる(デジタル機器を導入する)
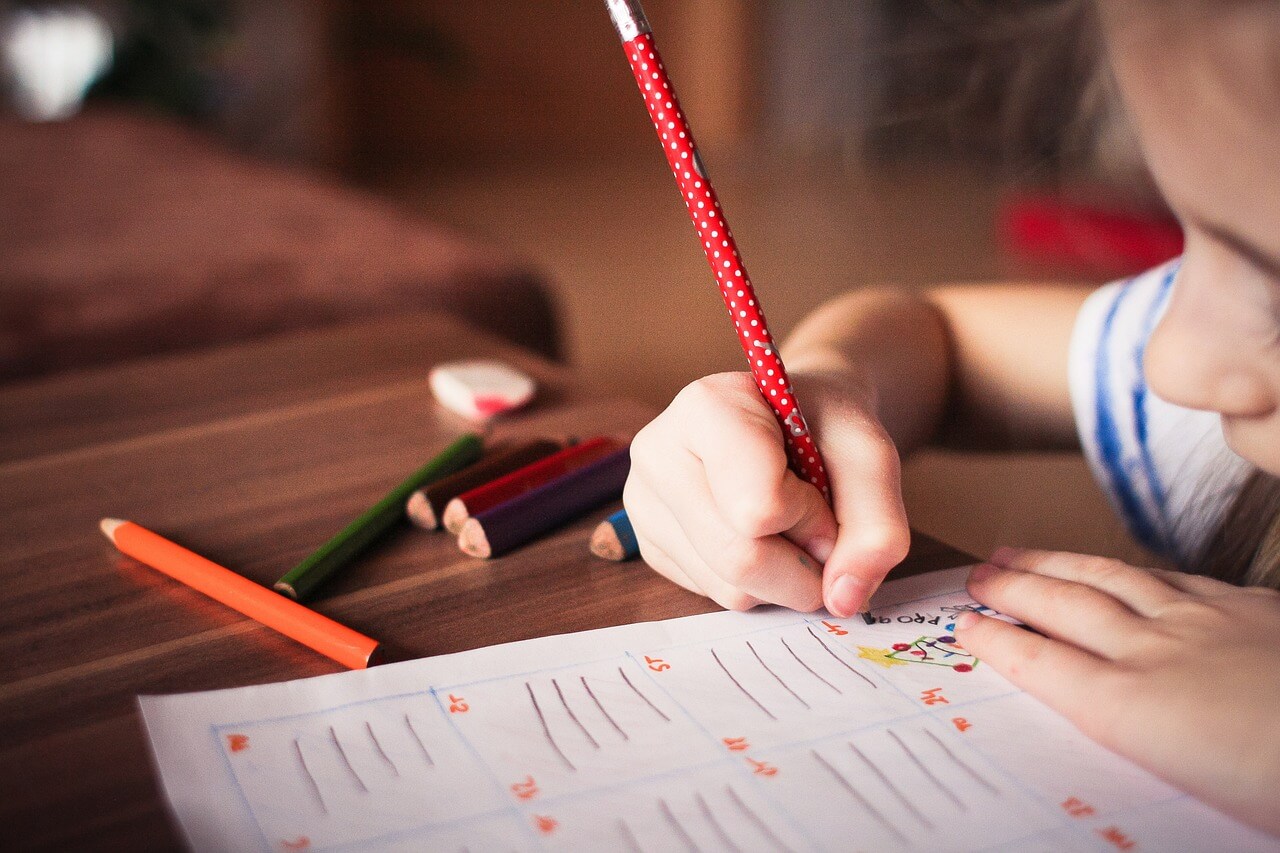
ASD児の特徴として、聴覚情報よりも視覚情報のほうが理解しやすいといったものがあります。したがって、図や絵などを学習に取り入れるのが有効です。
アニメや動画、デジタル教材の導入もおすすめであり、学習効率を高めてくれます。
ただ、カラフルな教材だと情報が多すぎて集中できない子どももいます。その場合は、白黒コピーを利用するなどして対応してみましょう。
褒めて自信をつける
苦手分野に取り組んでほしい場合は、できたらたくさん褒めてあげましょう。
好きなことには集中できるのがASDの特性です。
褒めることで、徐々にその勉強が好きになります。苦手分野がなくなれば、勉強の意欲もより湧いてくるでしょう。
まとめ
ASD(自閉スペクトラム症)とは発達障害の一種であり、こだわりが強かったり対人関係に問題が生じたりします(個人差あり)。
勉強に影響が出ることも多く、学習意欲を失うASD児も少なくありません。
家庭教師のグッドの講師はASD(自閉スペクトラム症)の特性を理解しており、子ども一人ひとりに合わせた指導をおこなっております。
勉強が大嫌いだった子どもが大好きになったといった実績も豊富です。
ASD児も多く利用しており、成績が急上昇したケースも珍しくありません。
家庭教師のグッドでは、無料の体験授業(120分)もおこなっております。興味がありましたら、ぜひ参加してみてください。