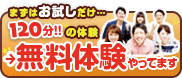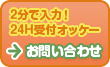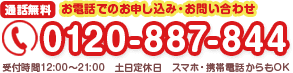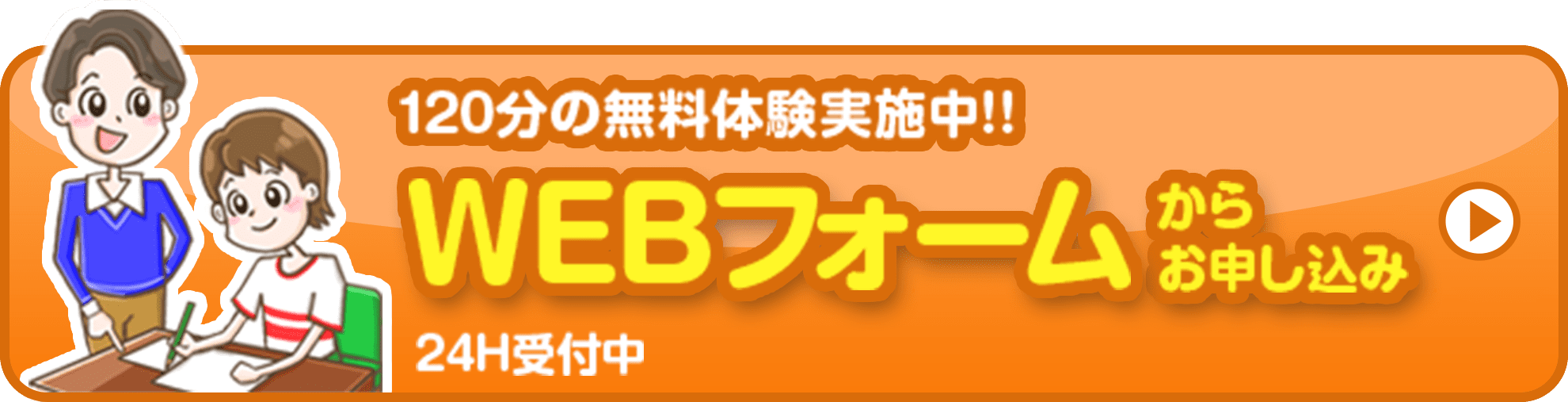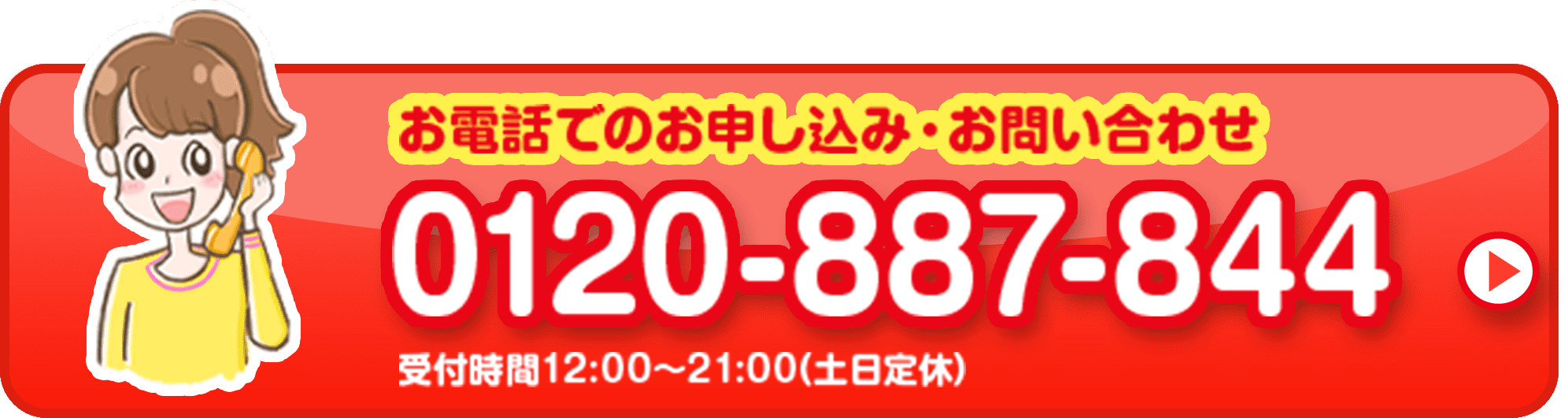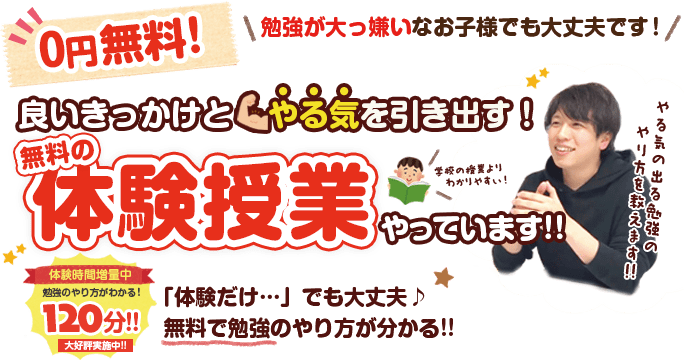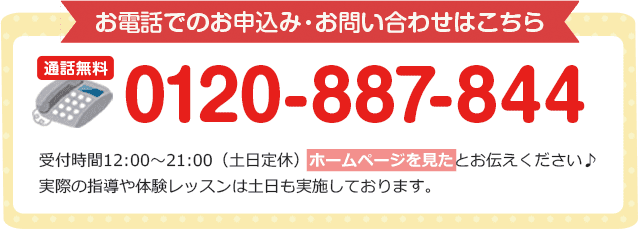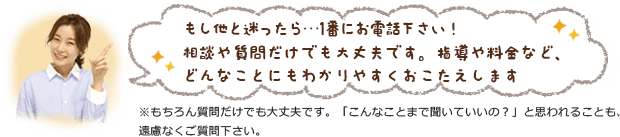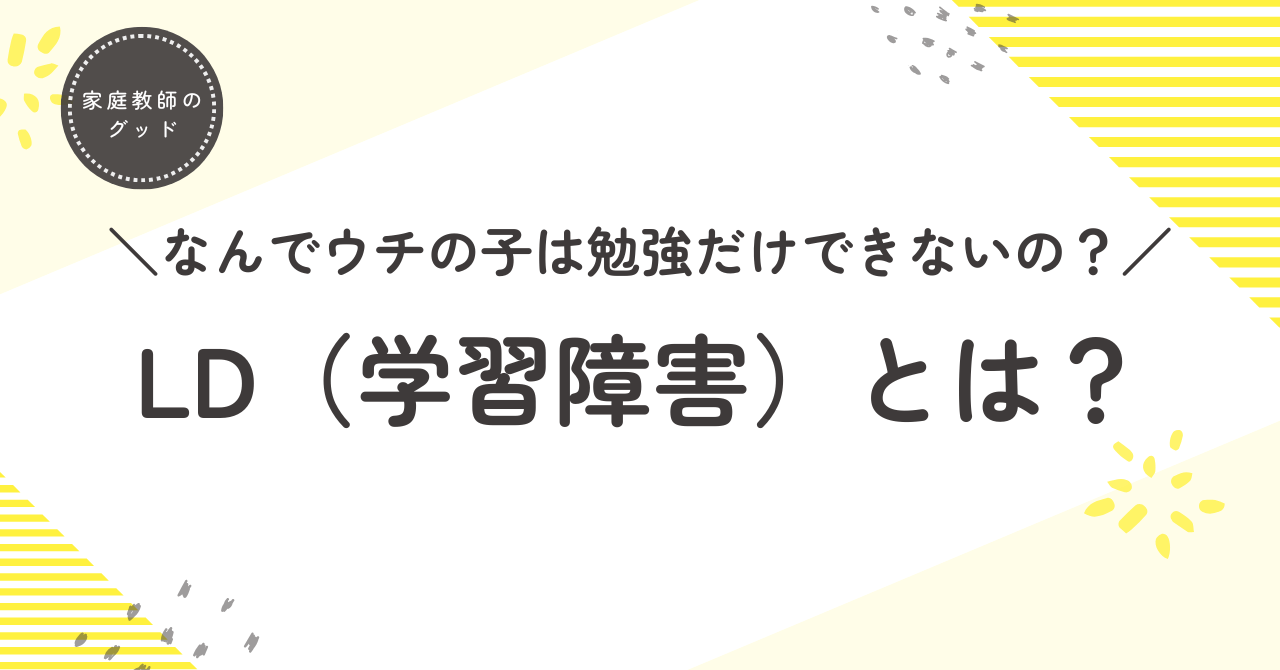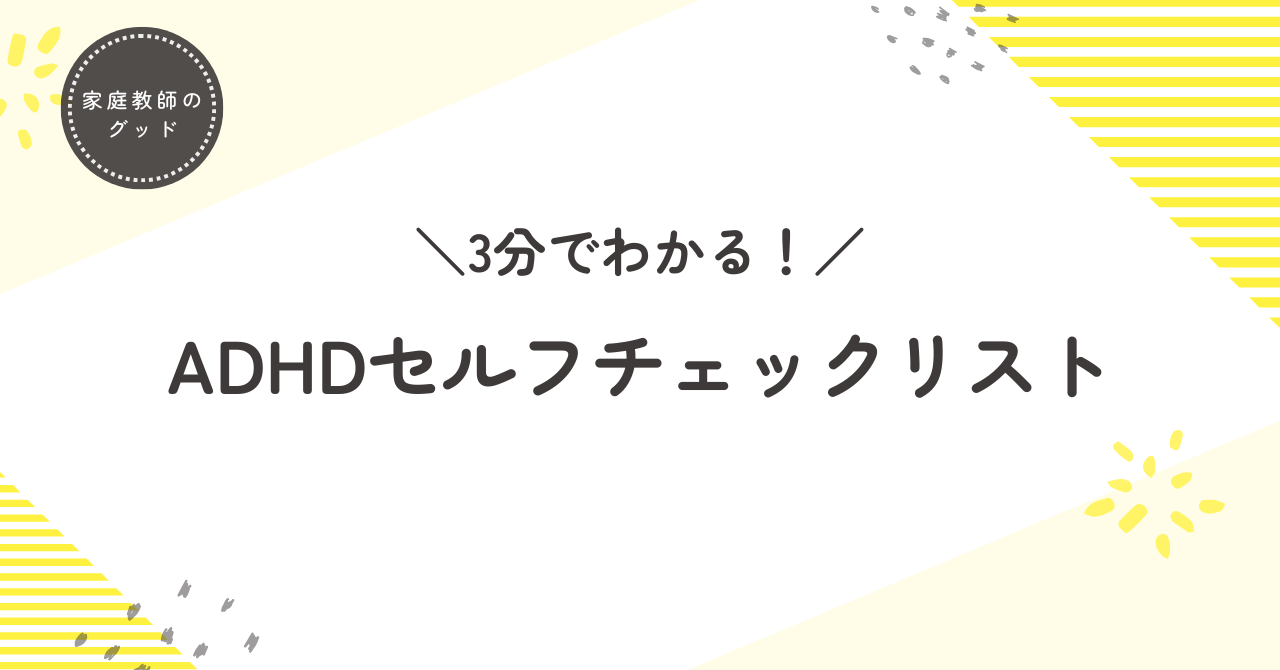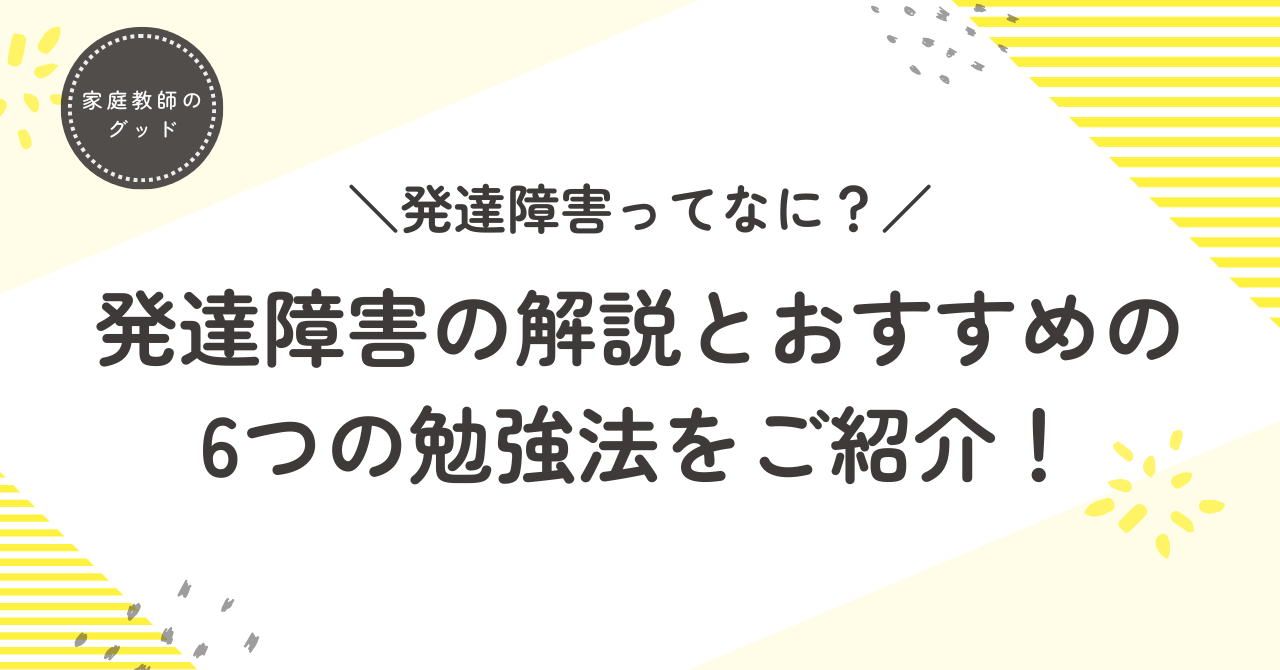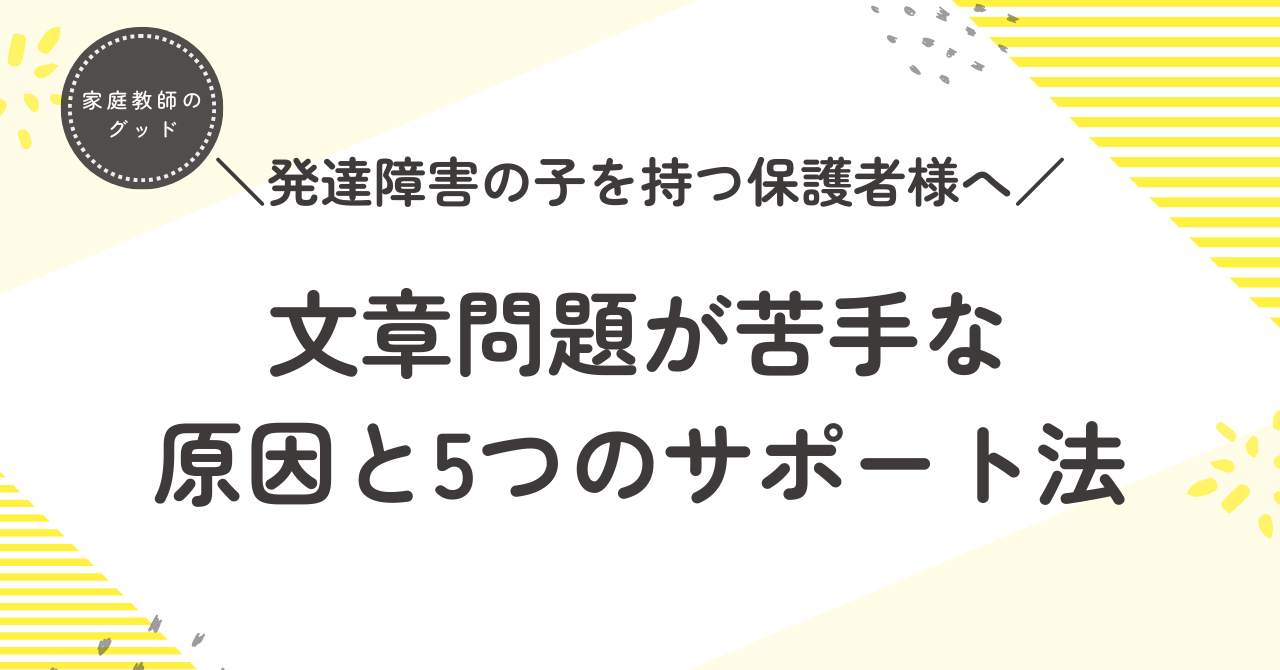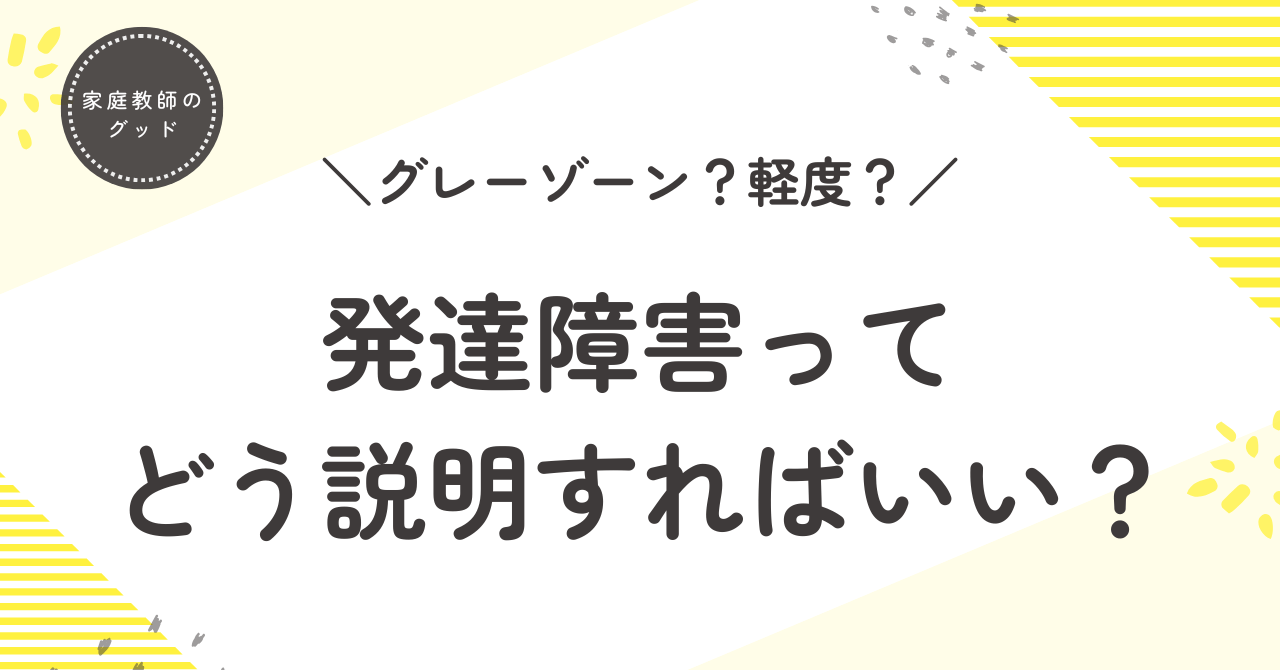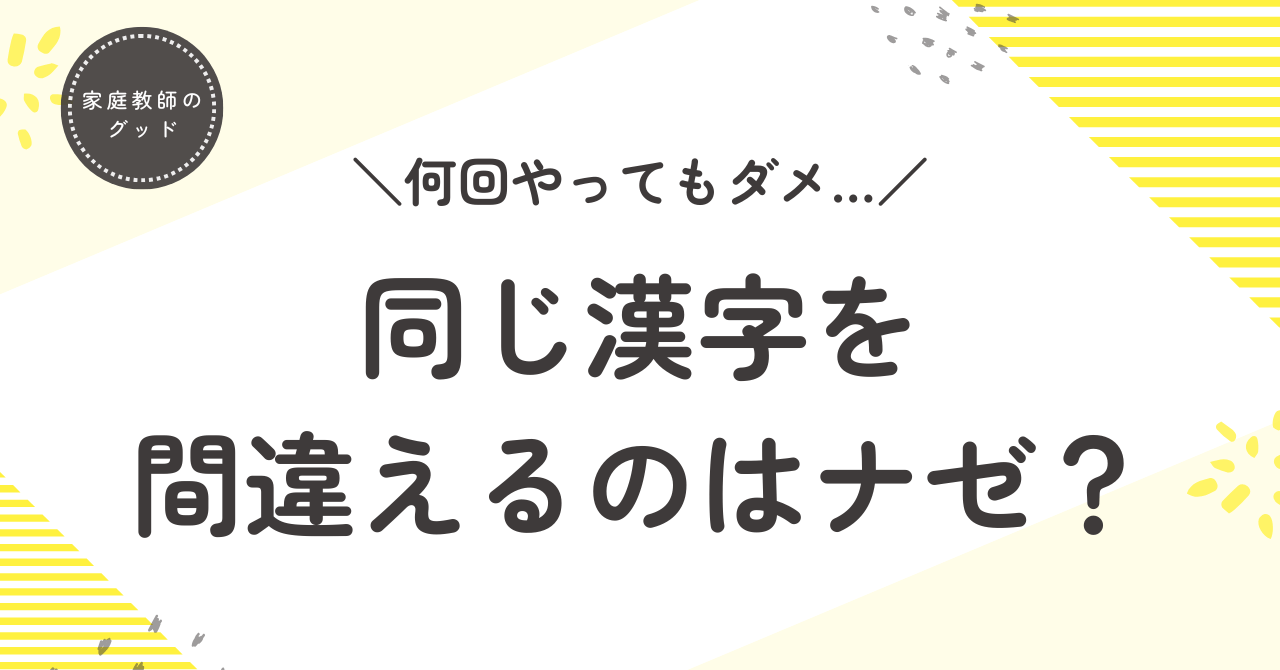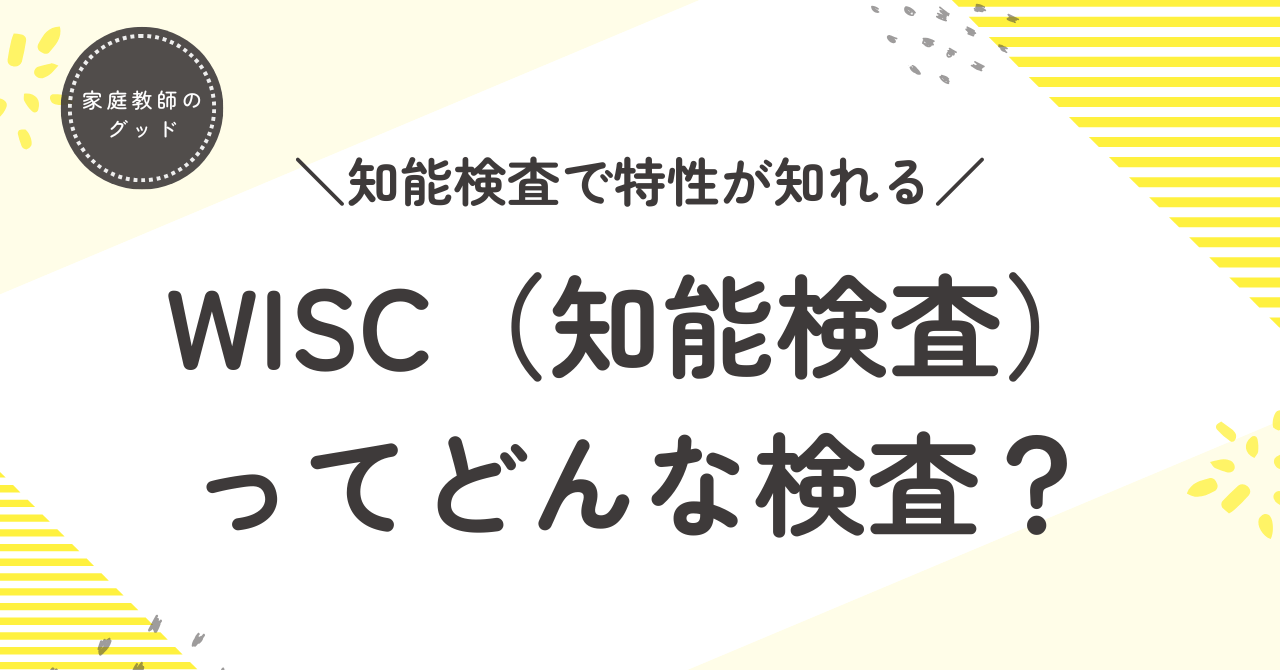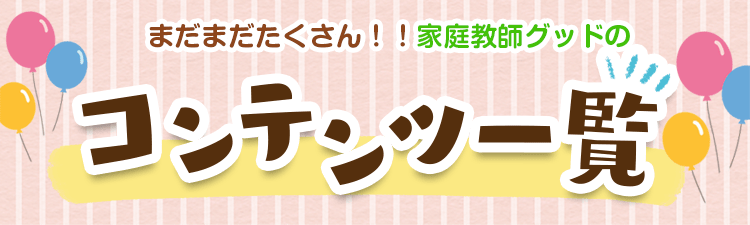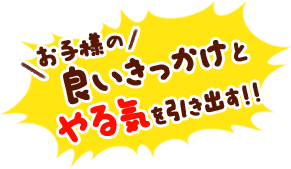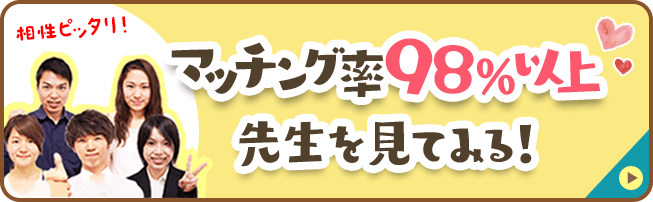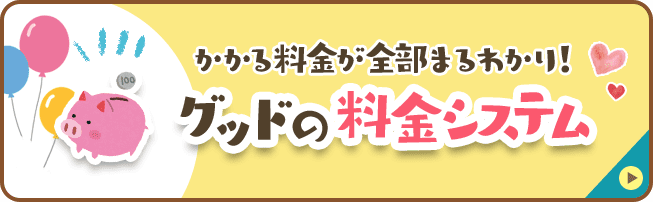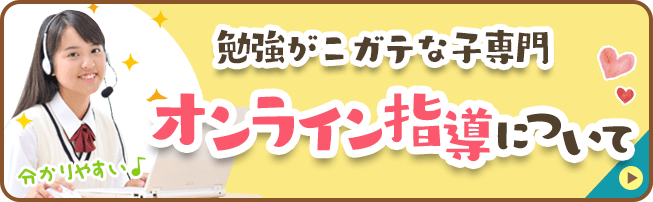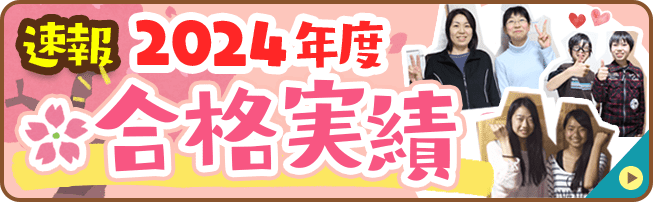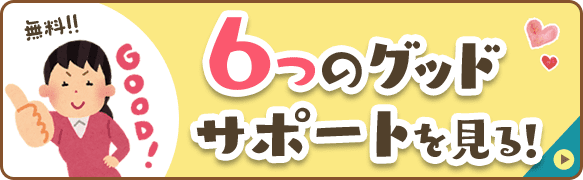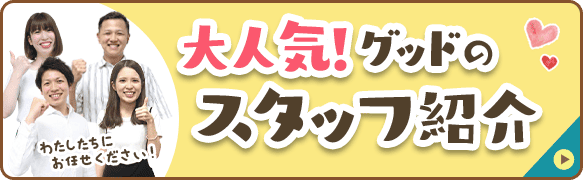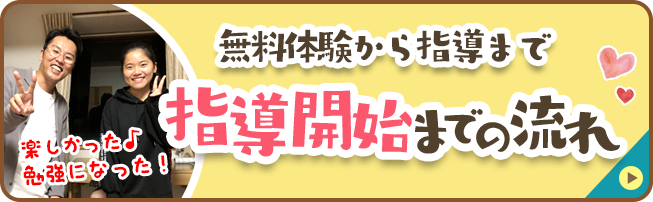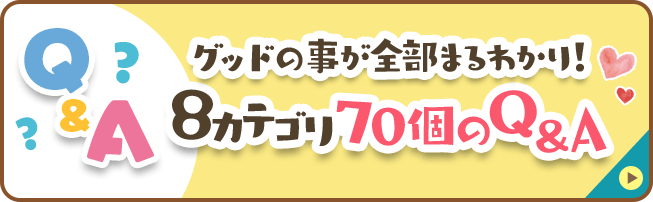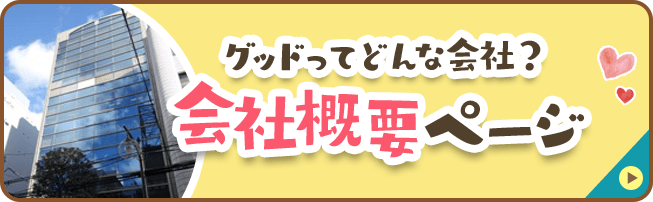勉強に集中できないお子さんの特性に合った集中環境の作り方
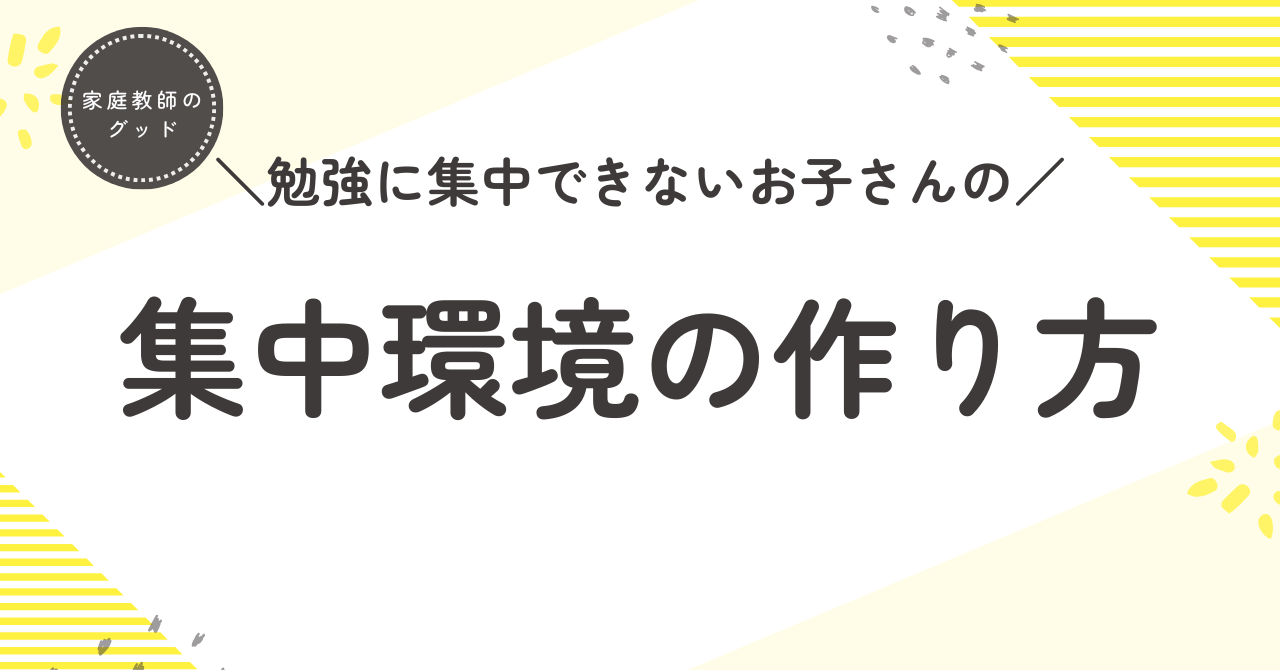
はじめに
「机に向かってほしいのに、すぐに立ち歩いてしまう」「ちょっとした物音で気が散ってしまう」──お子さんのそんな様子に、心を悩ませたことはありませんか?
とくに発達障害やADHDの特性をもつお子さんの場合、本人なりの理由や背景があります。
そしてそれは、努力不足ではなく、「環境の影響」によって大きく左右されることもあるのです。
この記事では、家庭でできる集中環境の整え方を紹介していきます。
集中できないのは「特性」のせい──まずは理解から始めよう

よくある集中の悩みとは
お子さんが勉強中に立ち歩いてしまったり、宿題にとりかかるまでに時間がかかったりするのは、決してめずらしいことではありません。
また、物音や視界の変化にすぐ気を取られてしまうといった場面も、日常でよく見られます。
こうした様子を見ると、つい「やる気がないのでは?」と感じてしまいがちですが、
実は脳の働き方や感覚の受け取り方に特性があるからこそ起きている場合も多いのです。
「できない子」ではなく「やりにくい子」
ADHDや感覚過敏の特性をもつお子さんは、集中する力がないわけではありません。ただ、続けるのが難しい状況があるというだけなのです。
「できない子」ではなく、「今のやり方ではやりにくいだけ」という視点で見てみると、親の気持ちも少し楽になります。
そして何より大切なのは、集中力の差は性格や育て方の問題ではないということ。
脳の特性や感覚の違いに応じた“方法”や“環境”を工夫することで、ぐっと楽になることがあります。
まずは親が「安心」することが第一歩
お子さんの集中できない様子を見ると、親として焦りや不安、イライラが募ってしまうこともあるでしょう。
でもまずは、「この子にはこの子のやり方がある」と受け入れることが大切です。
環境が子どもの集中力を左右する
脳は「気が散るように」できている
人間の脳は、外の刺激に反応するようにできています。音、光、匂いなどの刺激を受けとり、必要な情報を選別していますが、
感覚が鋭いお子さんの場合、すべての刺激を強く受けてしまうため、集中が難しくなってしまうのです。
特にADHDの特性を持つお子さんは、注意のコントロールが難しいことが多く、
目や耳に入る情報が多いほど、集中がそれだけ分散されてしまう傾向があります。
自宅は意外と集中しづらい?
おうちの中は安心できる場所である一方で、意外と刺激の多い環境でもあります。
テレビの音やきょうだいの声、ごはんのにおい、外から聞こえる車の音など、
お子さんにとっては集中を妨げる要素がたくさん潜んでいるのです。
学校ではある程度決まった空間で学習できますが、自宅では自由さゆえに集中しづらいことも。
だからこそ、「自宅で勉強できない=本人の努力不足」とは言い切れないのです。
「できない」ではなく「やりにくい」だけ
お子さんが集中できないとき、親はつい「どうしてできないの?」と思ってしまいます。
でも実際は、「今の環境ではやりにくい」というだけのことが多いのです。
たとえば、視界に色々なものが入りすぎていたり、座っている椅子の感触が落ち着かなかったり。
ちょっとしたことが、大きな違いを生んでいる可能性もあります。
今日からできる!家庭での集中環境づくりの工夫

場所を変えてみる:勉強は机じゃなくてもOK
机での勉強にこだわらず、お子さんが安心できる場所を一緒に探してみましょう。
たとえば、ダイニングテーブルのほうが落ち着くお子さんもいれば、
ロフトベッドの下を秘密基地のように使って集中できるというケースもあります。
中には、押し入れの中に布をかけて“こもりスペース”を作り、
その中で学習に集中できるようになったお子さんもいます。
「机じゃなきゃダメ」と決めつけずに、お子さんと一緒に試してみるのもおすすめです。
視界の情報を減らす:シンプルにするだけで変わる
勉強机の上にたくさんのものがあると、視界から入る情報量が多くなり、
それだけで集中が乱れてしまうことがあります。
筆箱やノートなども、できるだけシンプルな色や形のものを選ぶと効果的です。
また、壁に貼ったポスターやおもちゃが目に入らないようにするだけでも、
目の疲れや注意の散漫を防げる場合があります。
環境をすっきりさせるだけで、お子さんの集中がぐっと高まることもあるのです。
音と光を味方に:五感にやさしい工夫を
耳から入る音や、目に入る光も、集中力に大きな影響を与えます。
テレビの音や生活音が気になる場合は、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを試してみましょう。
また、日中の光が強すぎると感じる子には、遮光カーテンを使ってみるのも効果的です。
タイマーの代わりに砂時計を使うなど、時間の経過を視覚的に感じられる工夫も、
安心して学習に取り組むための支えになります。
環境づくりは「親が頑張りすぎない」ことがコツ

「うまくいったこと」に目を向けよう
「また集中できなかった」とマイナスの部分に目が向いてしまうのは自然なこと。
でも、「今日は10分座っていられた」「昨日より取り組みが早かった」など、
うまくいったことに注目して声に出してあげるだけで、子どもも前向きになれます。
試行錯誤の時間も「学び」
環境づくりは一度で成功するものではありません。
今日はダイニングで、明日はベッドの下で…というように、試してみて初めて「うちの子にはこれが合う」とわかることもあります。
失敗しても、それは大切な“発見”です。
お子さんと一緒に実験するような気持ちで向き合うことが、親子の信頼関係にもつながります。
完璧じゃなくていい、60点でOK
「もっと良い方法があるかもしれない」と、親御さんはつい完璧を目指してしまいがちです。
でも、完璧な環境をつくる必要はありません。
今よりちょっと落ち着ける、ちょっと集中しやすい。
そんな60点の状態でも、お子さんにとっては十分な前進です。
どうしても難しいときは、第三者のサポートも

家庭教師や支援サービスも選択肢のひとつ
「どうしてもうまくいかない」「親子だけでは限界を感じる」そんなときは、
家庭教師や学習支援の専門家に頼るという選択肢もあります。
第三者の視点が加わることで、お子さん自身の自己肯定感が高まり、
学びの習慣が自然と身についていくこともあります。
親が一人で抱え込まないことが大切
一生懸命なお母さんほど、「もっと自分が頑張れば」と考えてしまいがちです。
でも、頑張りすぎることで心に余裕がなくなってしまったら、それはお子さんにも伝わってしまいます。
親御さん自身が、頼れる場所を見つけるのも大切です。