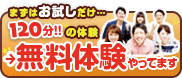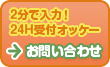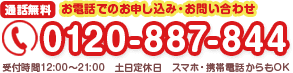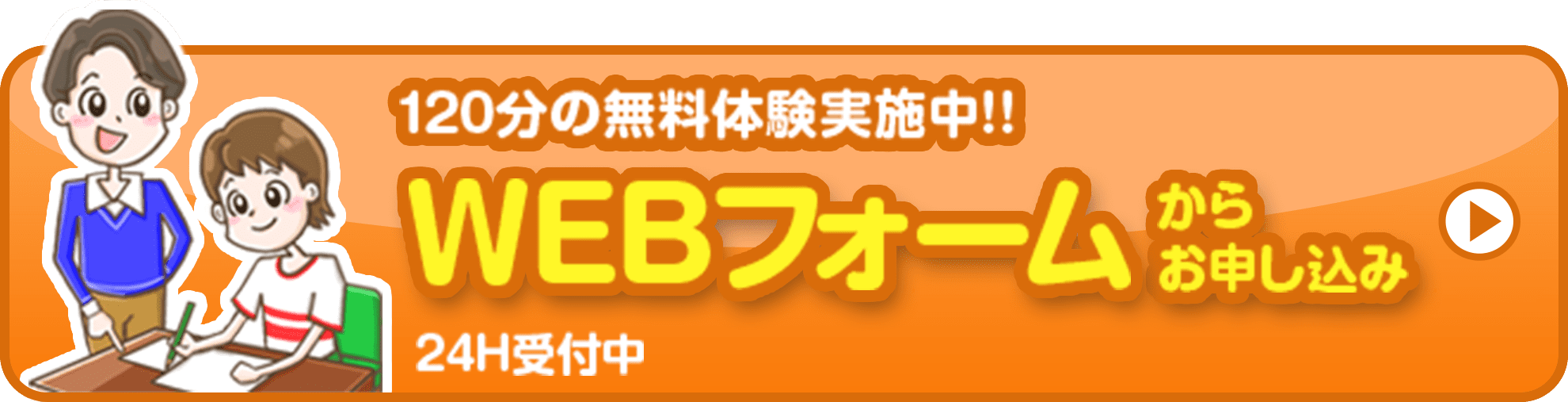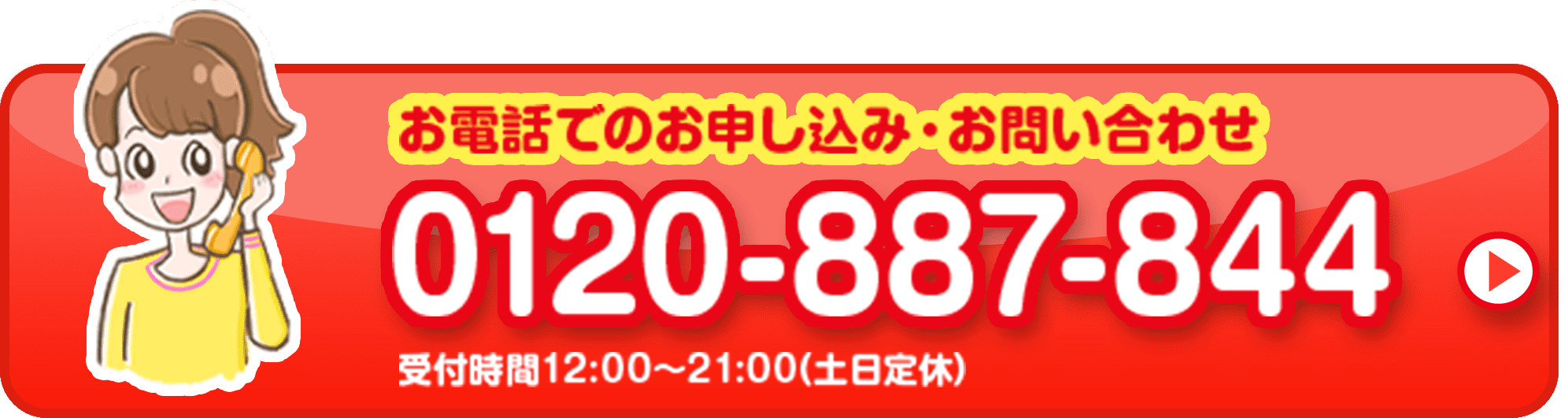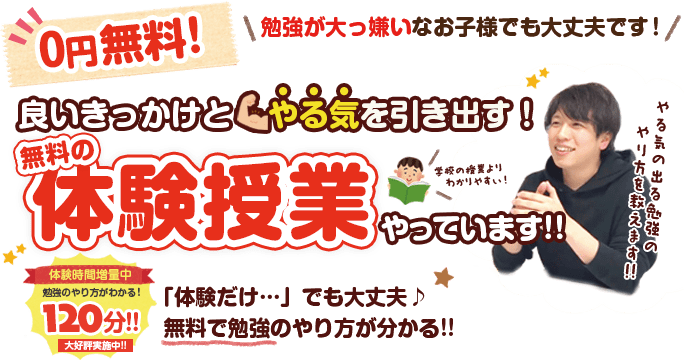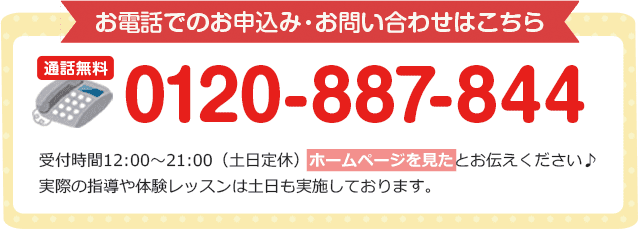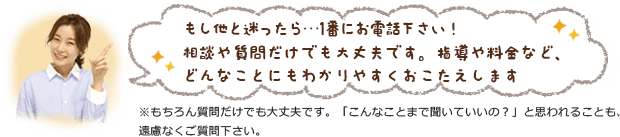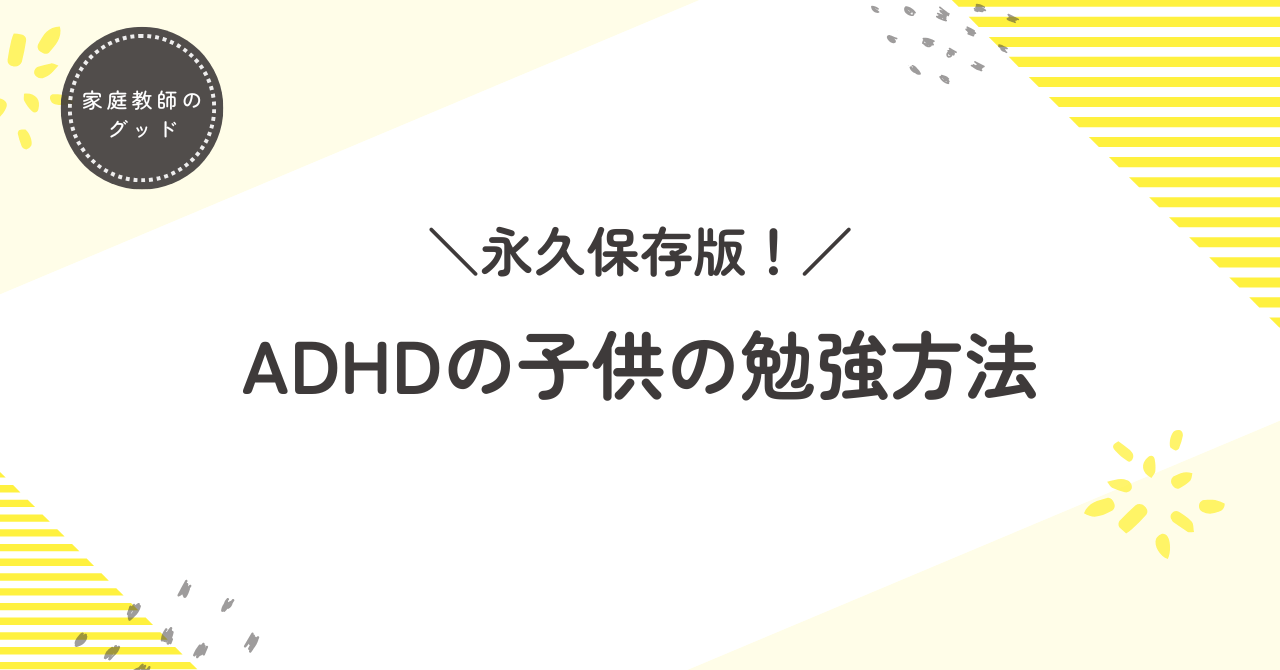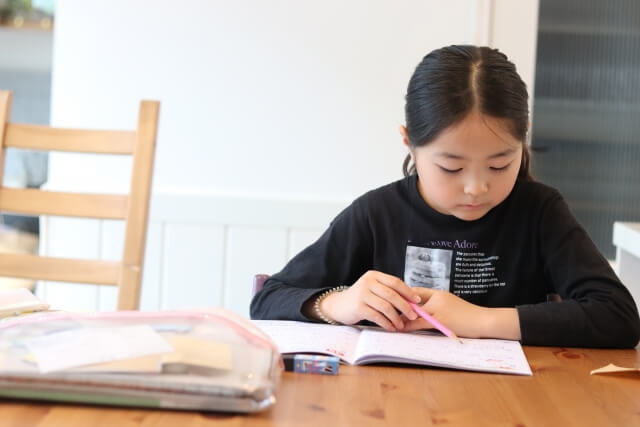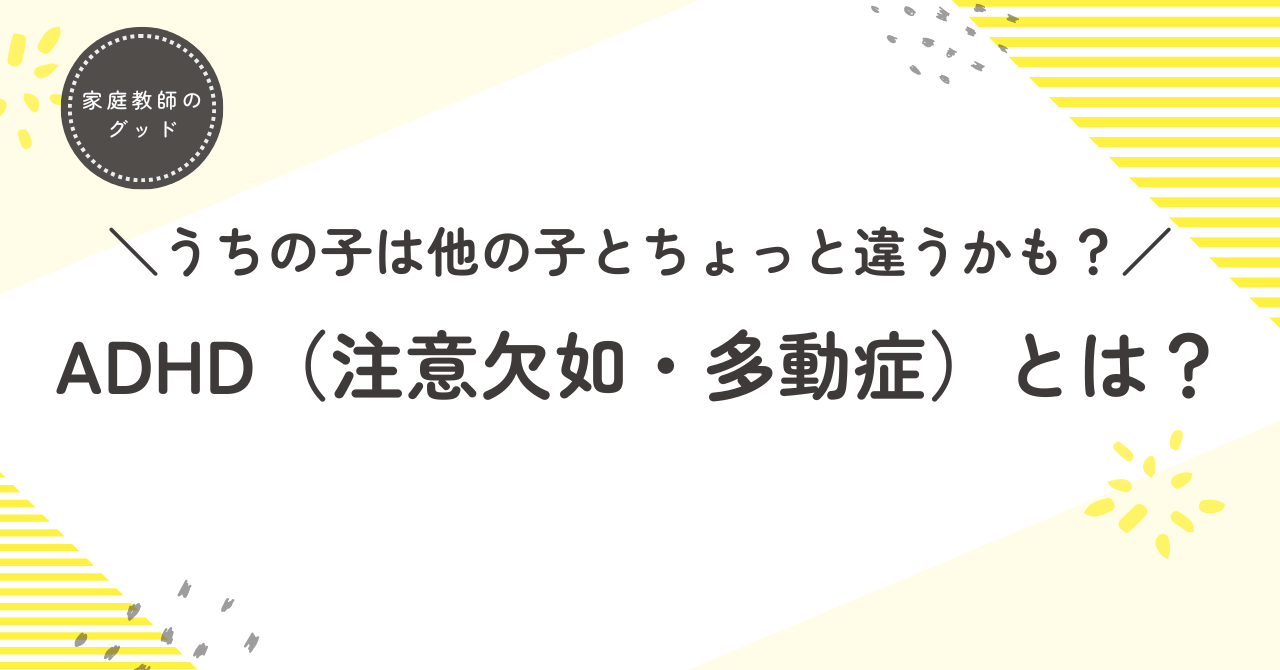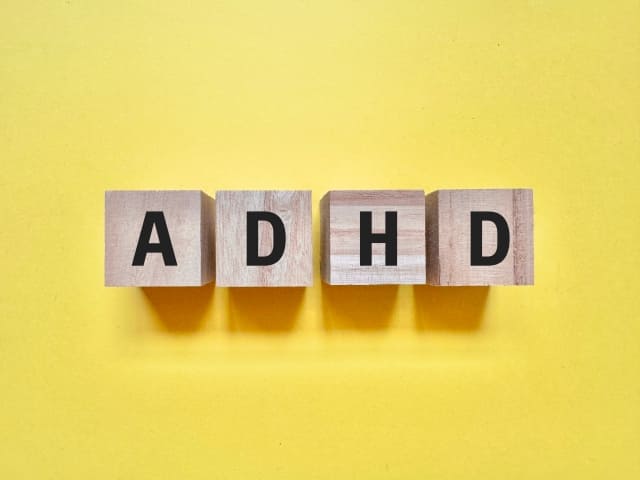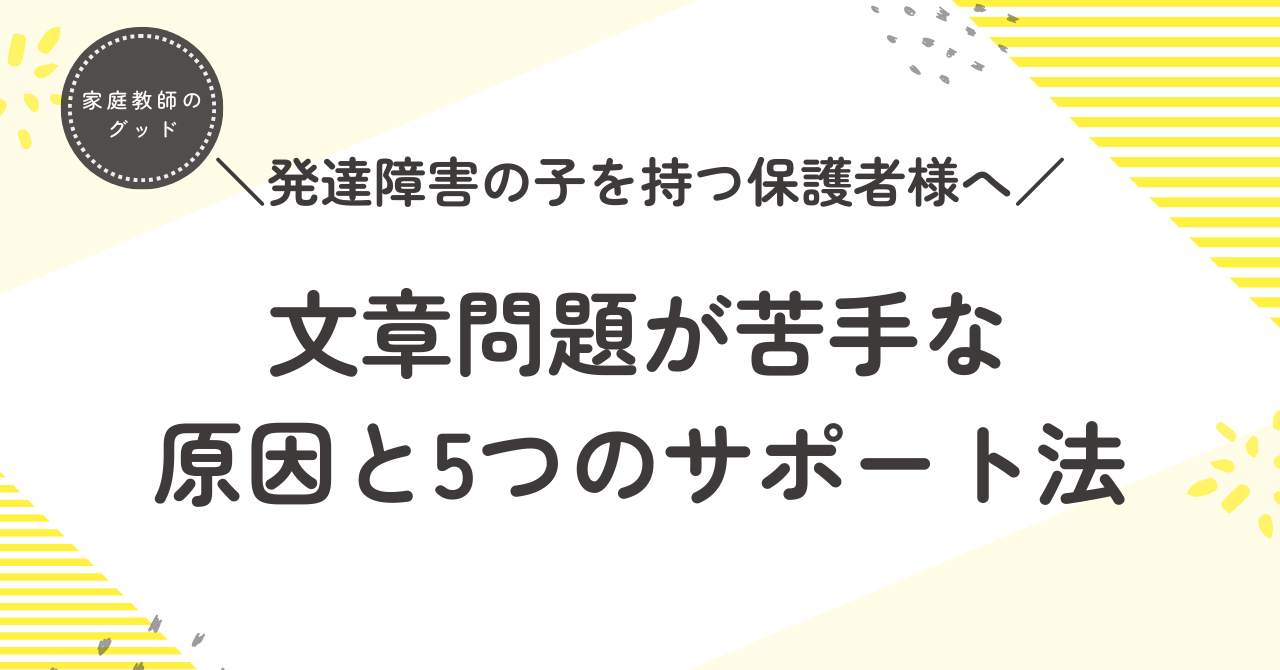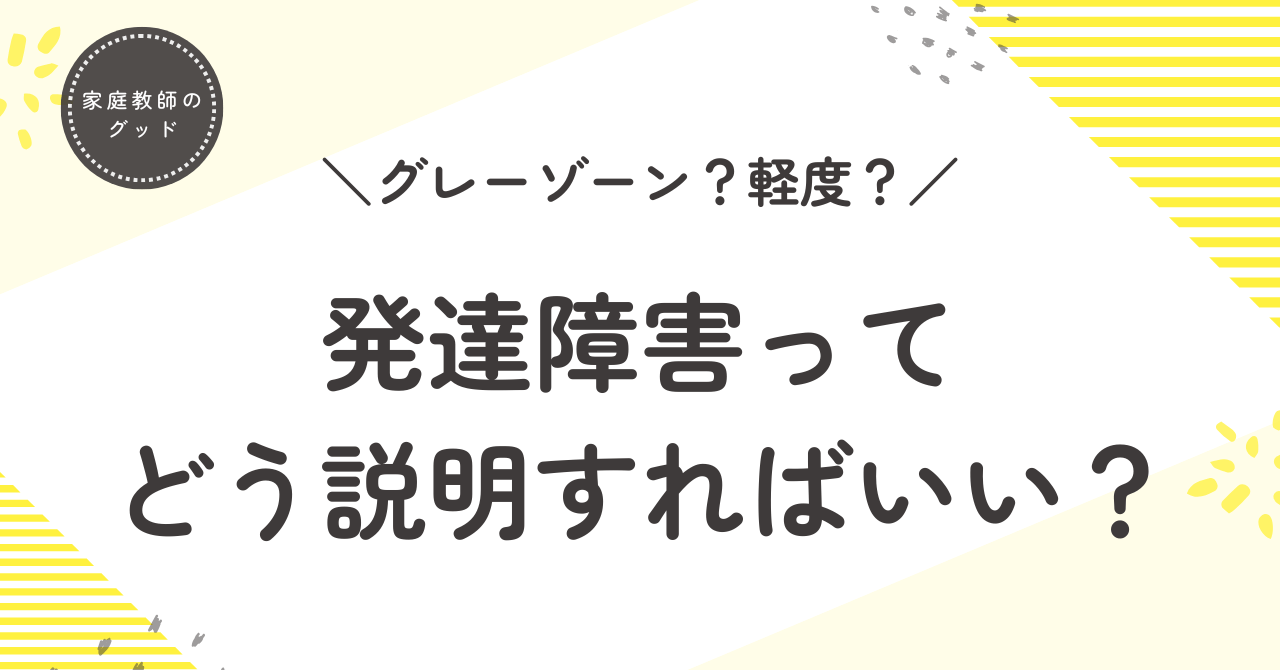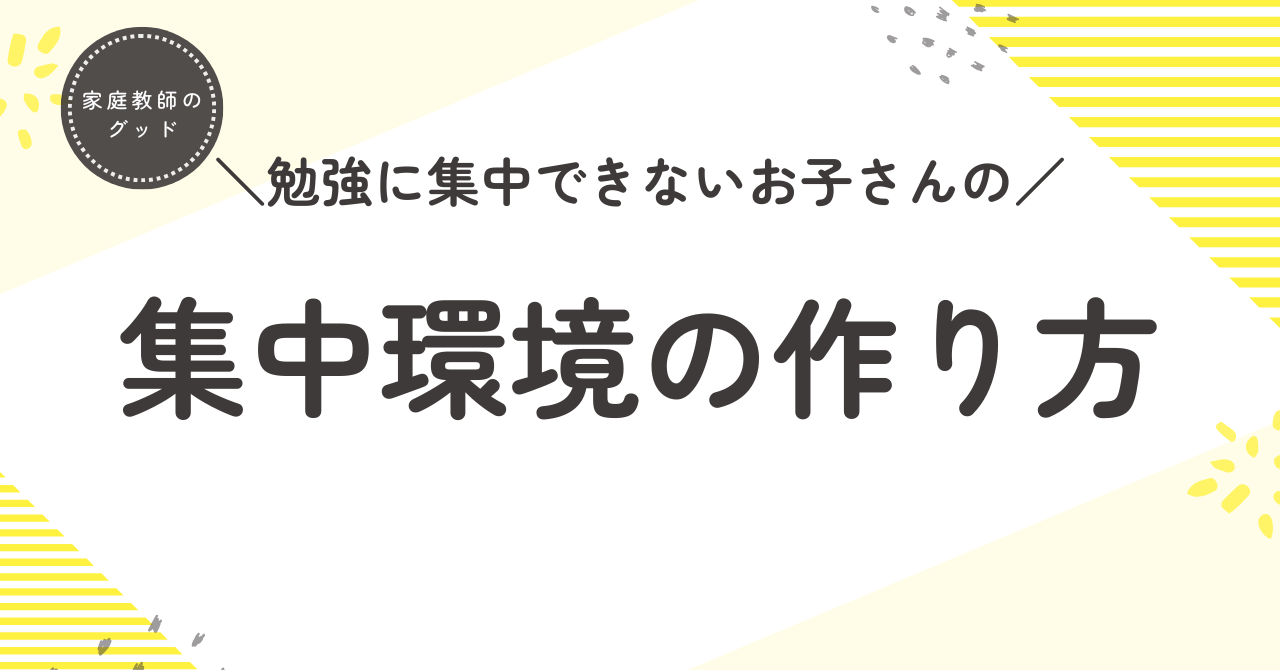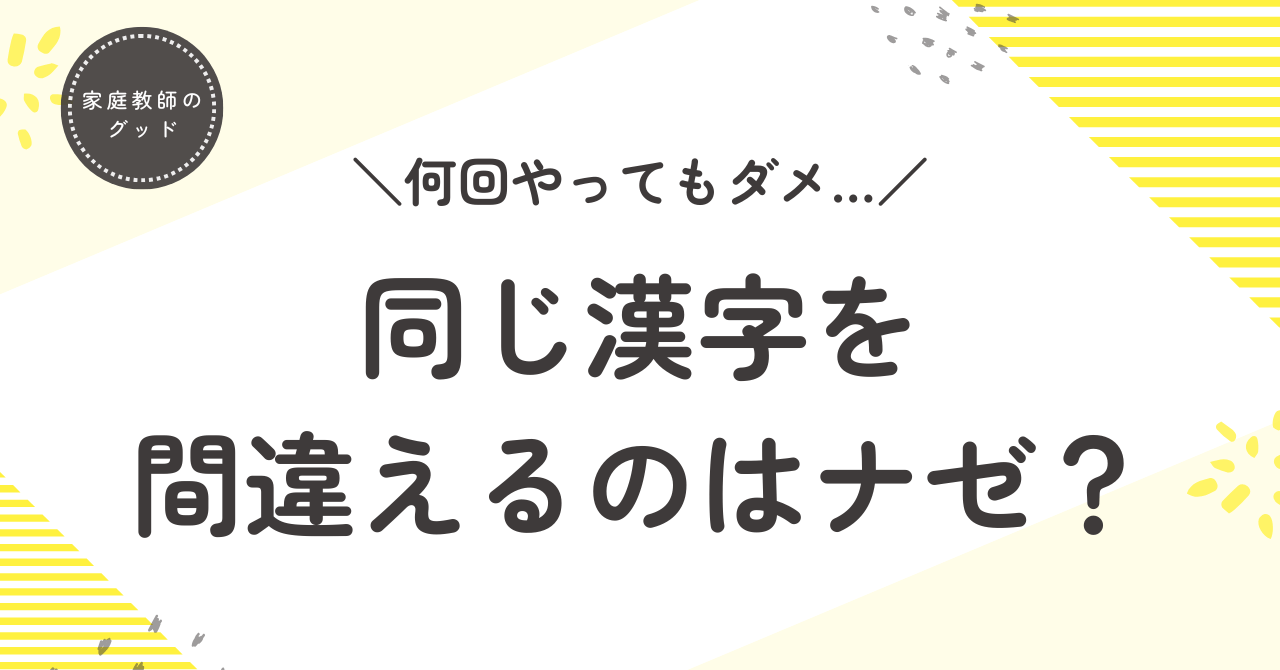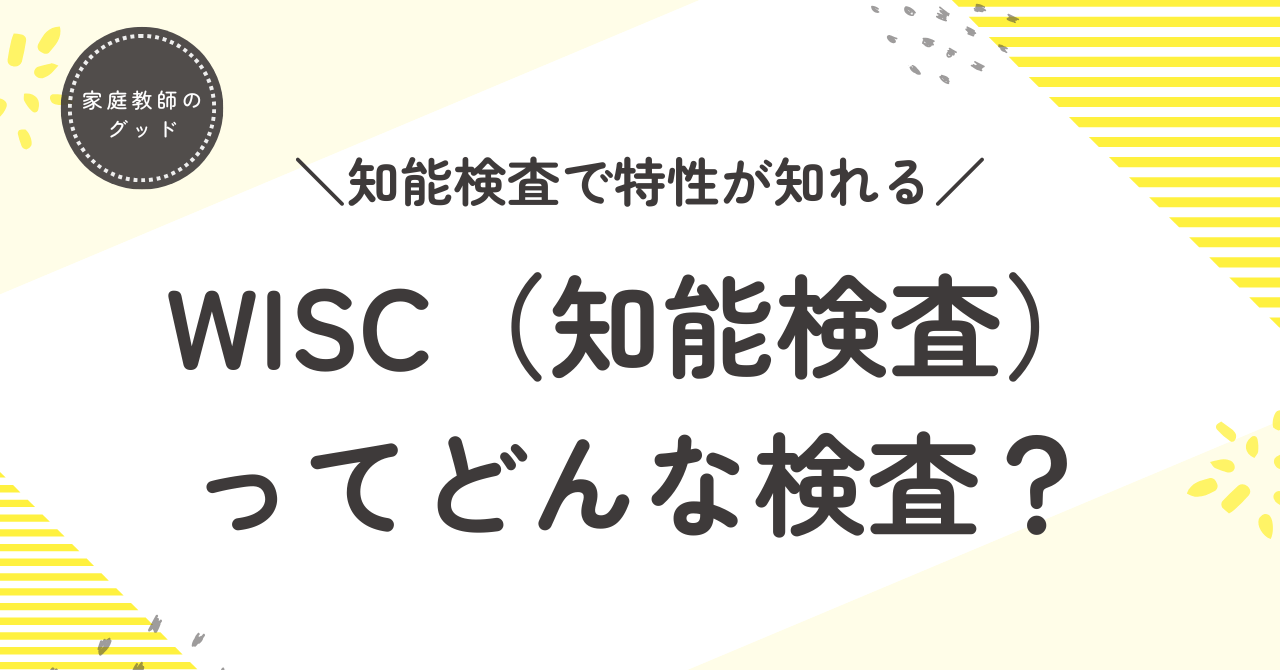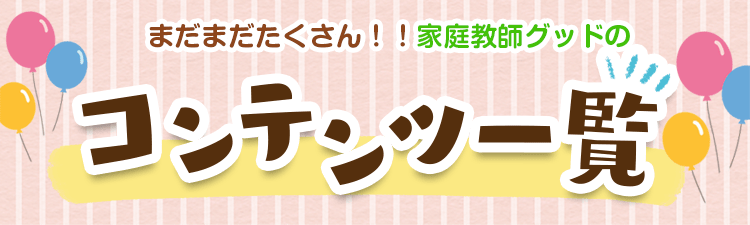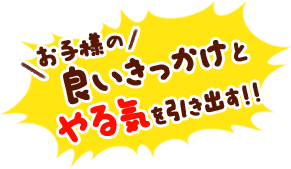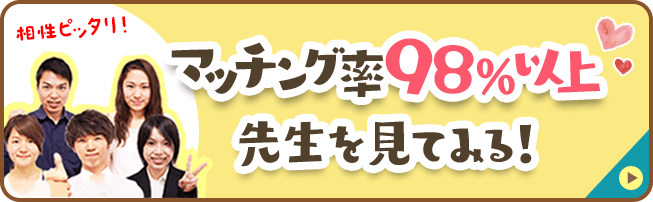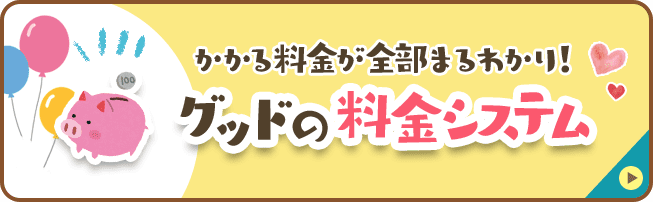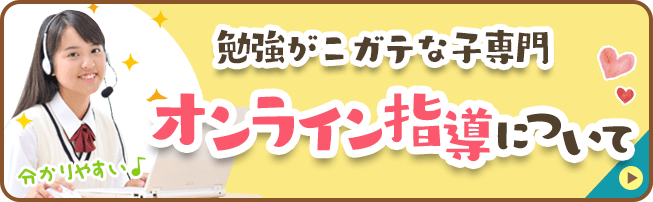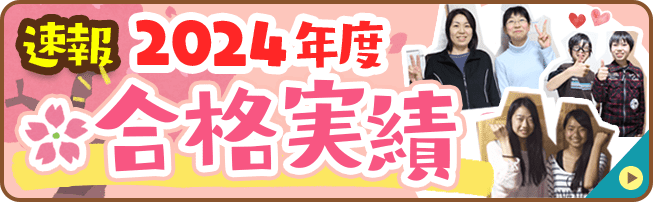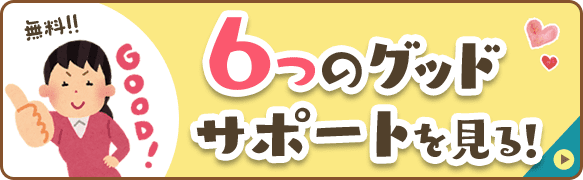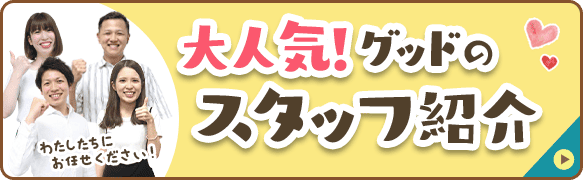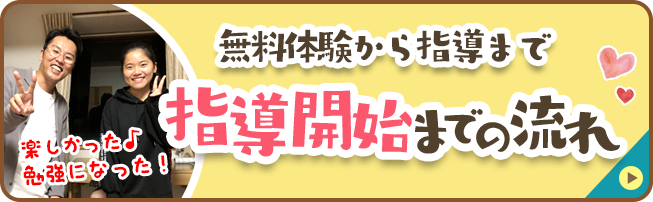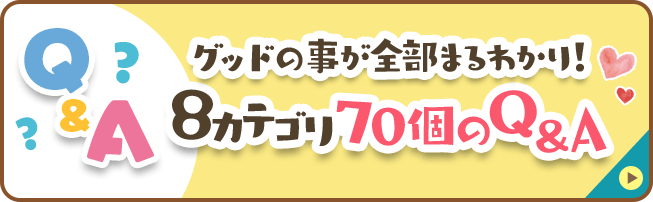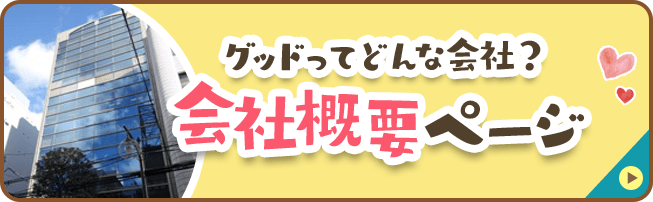LD(学習障害)とは?
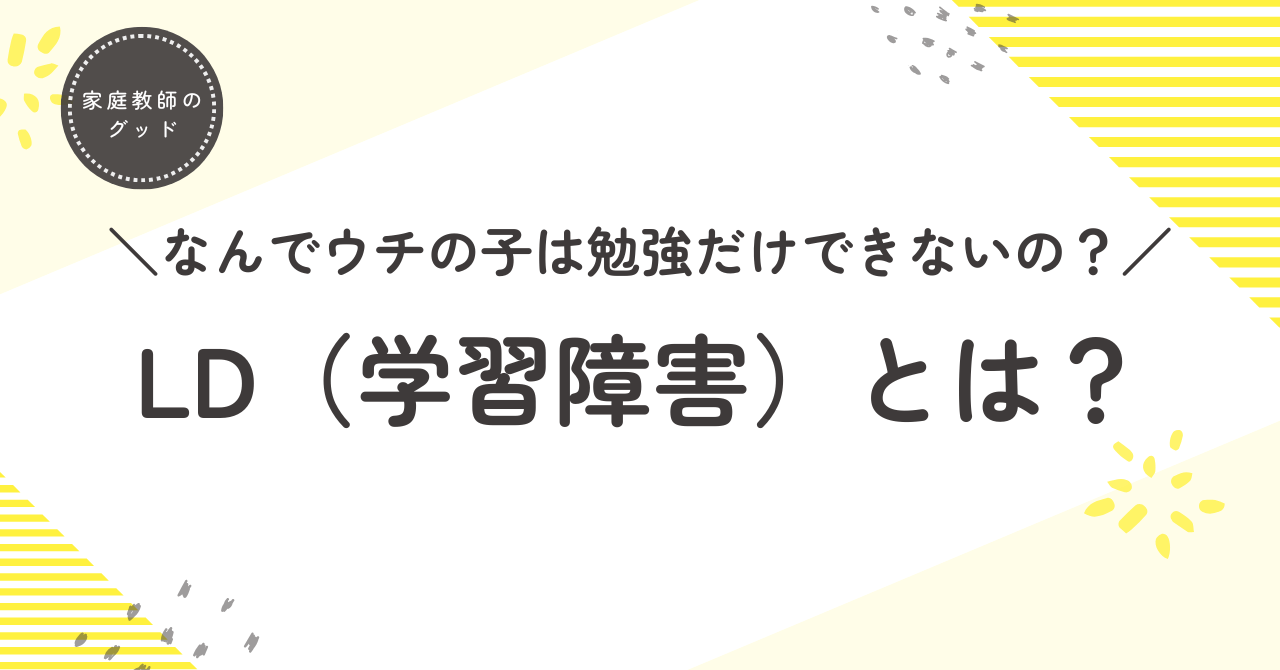
学習障害とは、全般的な知能の遅れはないものの、読み・書き・計算といったある特定の領域において学習の困難さが生じている状態です。
幼稚園や保育園など、本格的な学習が始まる就学前の段階では気付かれないことも多いのですが、小学校入学後に授業を受けたりテストを受けたりする中で、徐々にその特性が明らかになってくることがあります。
子どもでの学習障害の有病率は5~15%程度と言われており、各クラスに2~3人はいる計算になります。有名な映画にも数多く出演しているハリウッド俳優の人が実は学習障害を持っていて、お付きの人に台本を読んでもらってセリフを覚えているということを公表し、話題になったことがありました。
この例でも分かるように、学習障害を持っていたとしても適切な環境を整えたり、本人の特性に応じたサポートをしたりすることで、本来の能力を発揮することも可能ですし、支障なく日常生活を送ることができます。
学習障害には、主に
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
という3つの種類があります。それぞれ単独で出現することもありますし、いくつかの障害を同時に持っているという場合もあります。
また、学習障害だけでなく、
注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)といった発達障害を併発しているケースもあり、人によってその特性は様々です。ここでは、それぞれの学習障害の特徴と、その対応やサポートの仕方について説明していきます。
読字障害(ディスレクシア)
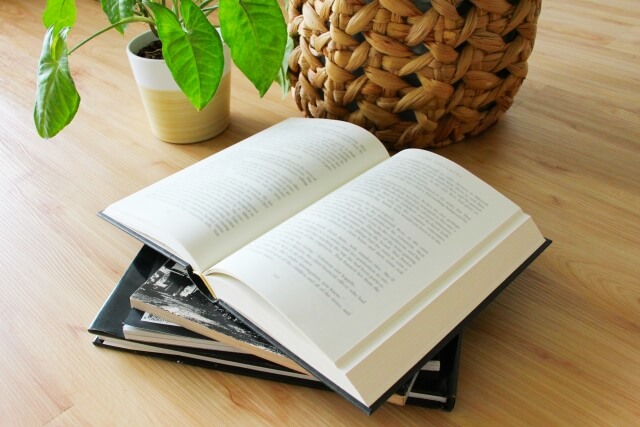
特徴
読字障害では読むこと全般に困難が生じ、文字がにじんだり、揺らいだり、かすんで見えたりしますが、視覚的な異常によるものではありません。
また、まとまりとして認識する力が弱いため、単語のまとまりを見分けたり、自分で文を区切ったりすることが苦手だったりします。
注意して読んでいても行を読み飛ばしたり、小さい「つ」や「ゆ」が認識できなかったりします。中高生では、小学校で習った漢字が読めなかったり、英単語が覚えられなかったりということが起こります。
対処法
読字障害があると、一般的に仕事や学校のお知らせで使用するような明朝体やゴシック体で書かれた文章は、読みにくいと言われています。
そこで「UDデジタル教科書体」という、読字障害のある人でも読みやすいフォントで学習プリントを作成すると、格段に読みやすく問題を解きやすくなるという場合があります。
ただし、読字障害の人の文字の見え方は本当に人それぞれですので、全員に当てはまるという訳ではありません。お家で試してみて、もし本人にとって効果がありそうであれば取り入れてみるというのも良いと思います。
また、マーカーで読むべき場所を目立たせたり、厚紙などを使って一行だけが見えるような窓つきのシートを作成し、読む部分を目立たせたりという工夫も効果的です。まとまりを認識する力が弱いお子さんには、区切る部分に赤ペンなど見やすい色でスラッシュを書いてあげて、意味のまとまりを分かりやすくするという方法もあります。
最近ではスマホにも「読み上げ機能」がついていて、読まなくても聞いて読書をすることができます。どうしても読むことが難しい場合には、保護者の方が読んで聞かせることで、理解を促すのでも良いと思います。
無理に読ませようとするのではなく、便利なツールを利用することで本人のできることを増やし、自信をつけさせてあげることが、学習意欲の向上に繋がります。
書字障害(ディスグラフィア)

特徴
小学校低学年のうちは漢字ノートの1マスが大きいのでなんとかその枠の中に入り切る文字を書くことができていても、学年が上がるにつれ、1マスが小さくなっていきますよね。
書字障害があると、そういった時に複雑な漢字を1マスに入り切るように書けなかったり、文字の大きさやバランスがバラバラだったりします。また、書き順や書き始めが毎回バラバラで独自のものだったり、板書をするのにとても時間がかかったりします。
他の学習面では問題ないにも関わらず、中高生や大人になってもひらがなで分からない文字があったり、カタカナで書けない文字があったりして、周囲を驚かせることがあります。
対処法
書字障害がある人の場合、目からの情報を取り入れることが苦手なため、触覚を使って学習を促すようにすると記憶が定着しやすいと言われています。砂に指で文字を書いて触覚を感じながら漢字を覚えたり、持ちやすい三角鉛筆やグリップを使用したりといった方法も効果的です。
また、低学年向けの大きなマスの漢字ノートを引き続き使わせてもらうというのも一つの方法です。
板書が苦手な子の場合、今はタブレットが一人一台貸与されている自治体も多いですので、タブレットで黒板の写真を撮って家での学習に使うことができます。
大人になってからは文章を作成するにも、パソコンを使って書くことが多いですよね。手で書くことが苦手でも、キーボードのタイピングは得意という人もたくさんいます。早いうちからキーボードでの文章の書き方を覚えることで、文章を書く楽しさが身につくかもしれません。
算数障害(ディスカリキュリア)
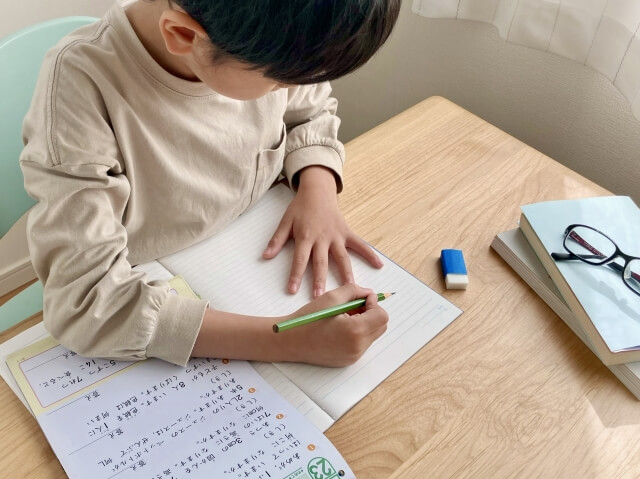
特徴
算数障害があると、小学校高学年になっても指を数えないと計算ができなかったり、極端に文章問題の理解ができなかったりします。
また、繰り上がり・繰り下がりの計算のやり方が理解できなかったり、筆算でどうしても最後まで数を合わせることができなかったりします。
また、大人になってからも時計を読むのに時間がかかったり、九九を思い出せなかったりということが起こります。
対処法
文章問題や応用問題、図形の問題が極端に苦手なお子さんの場合には、そういった問題を減らして、できる問題を丁寧に解かせてあげるようにすることが大切です。
理解できない経験が積み重なると学習意欲も低下して、自信もなくなってしまいます。時間を設定して早く溶けるようにする、という形式も、焦りに繋がって本来の能力が発揮できない可能性があります。落ち着いた環境でゆっくりと課題に取り組めると良いかと思います。
また、九九は口に出して覚えるよりも、表に書き出して視覚的に覚える方が得意な場合もあります。
歌にしてリズムで覚えた方が身につくというケースもありますので、お子さんの得意な方法で、少しずつ覚えていけると良いですね。
計算自体が重要でない場合には計算機の使用を許可する等、補助ツールを使えるように担任の先生と相談してみても良いかもしれません。
その他の対処法
ADHDのような発達障害の場合、あまりにも多動・衝動性が強かったり集中力の持続に困難があったりする場合には医療機関を受診して、お薬を処方してもらうこともあります。それによって学校生活における本人のストレスが軽減されるようであれば、服薬も一つの選択肢となります。
ですが学習障害の対処の基本は教育的な関わりや、本人にとって学習のしやすい環境を整えてあげるといったアプローチが中心となります。文字の読み書きが苦手だったり、算数だけ突出して苦手だったりするのは、決して本人が怠けているからとか本気で取り組んでいないからといったことが原因ではありません。
耳の聴こえに困難のある人が補聴器を使うように、学習障害を持ったお子さんが必要な補助ツールを利用することは、適切な学習環境を整える上で必要不可欠なことです。そういったお子さんに対して配慮をすることは、今は学校では義務となっています。
環境調整をする上で必要なツールの利用については、是非ご遠慮なく担任の先生にも相談して頂けると良いのではないでしょうか。大切なのは、本人が「できる」経験を重ねて自信をつけていくことです。
そのためには、「なんでもっと気をつけなかったの」「もっと頑張ればできるでしょ」とできないことを無理にやらせようとするのではなく、適切なサポートをすることで本人の学習意欲を少しでも上げていくことが重要となります。
まとめ
家庭教師のグッドでは、こういった勉強面での苦手を抱えたお子さんに対し、それぞれの特性に応じた個別の指導法によって学習をサポートしています。
学習障害の特徴というのは本当に様々で、本人の状態に合ったサポートが必要となります。
グッドではそういったお子さん達にも学習意欲を持って勉強に取り組んでもらえるよう、しっかりとした対応をしていきますので、是非学習面で苦手があったり勉強のやり方が分からなかったりといったお困り事がありましたら、お気軽にご相談くださればと思います。