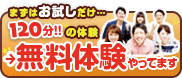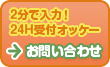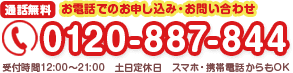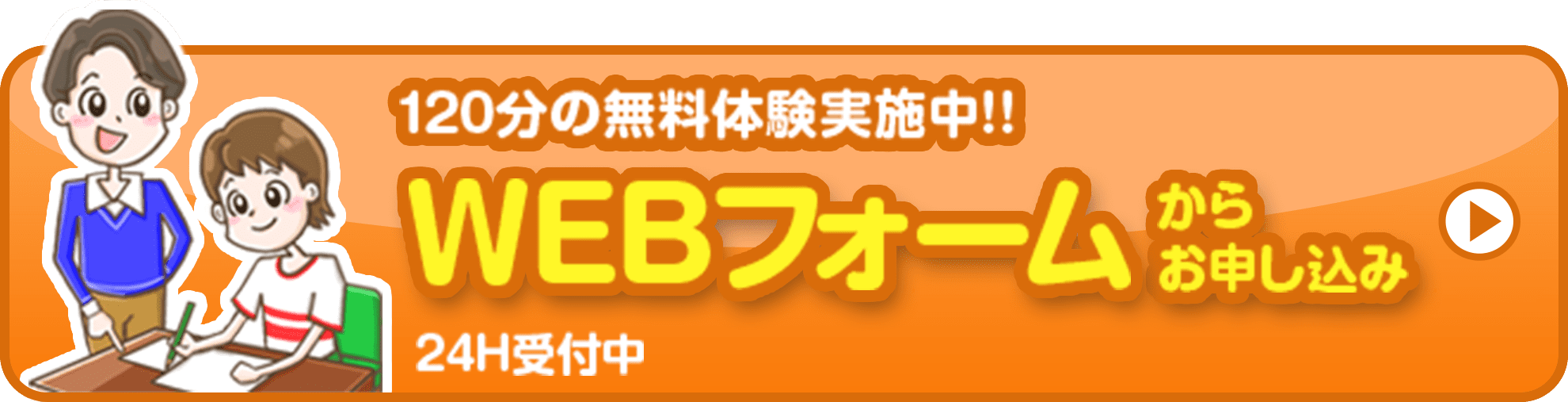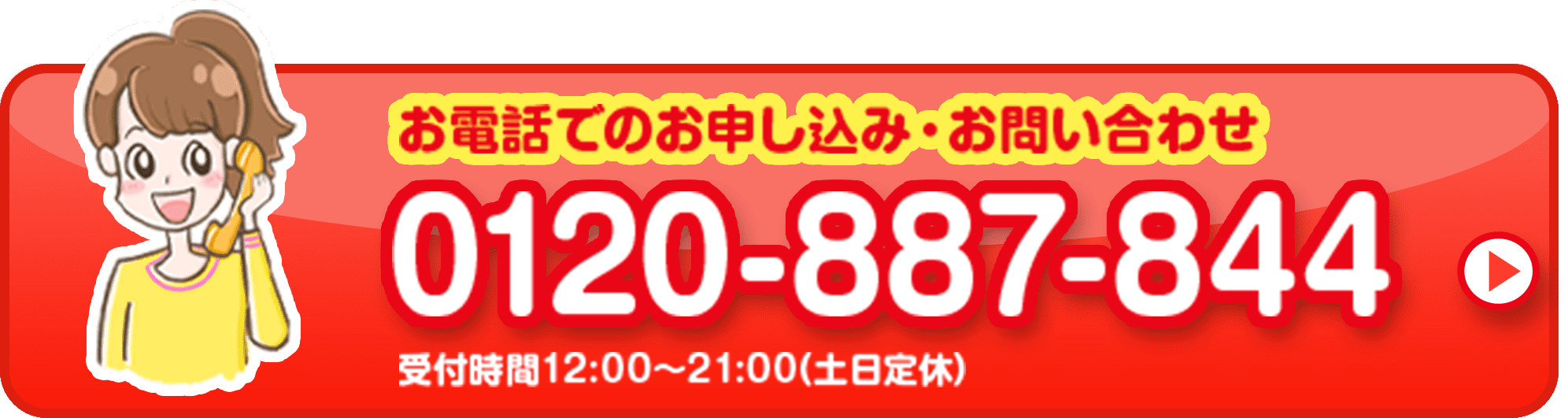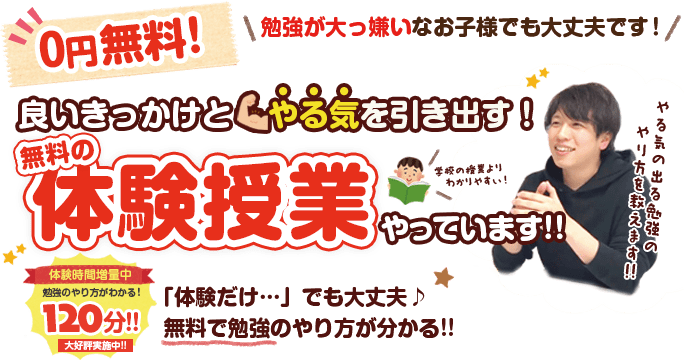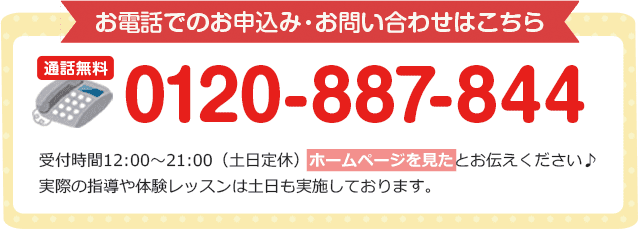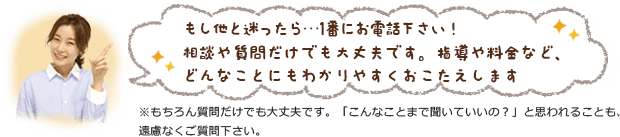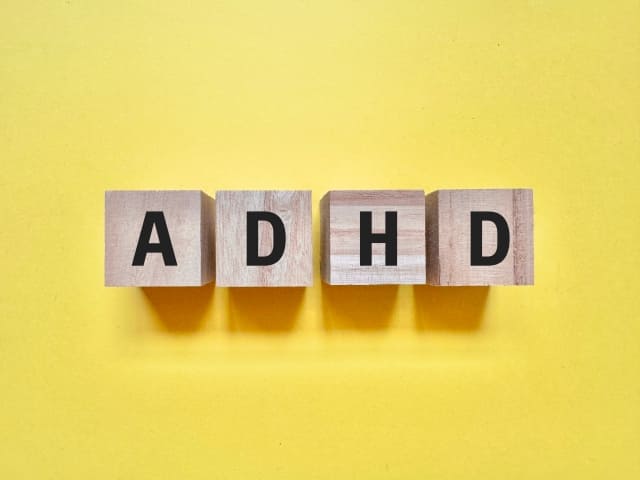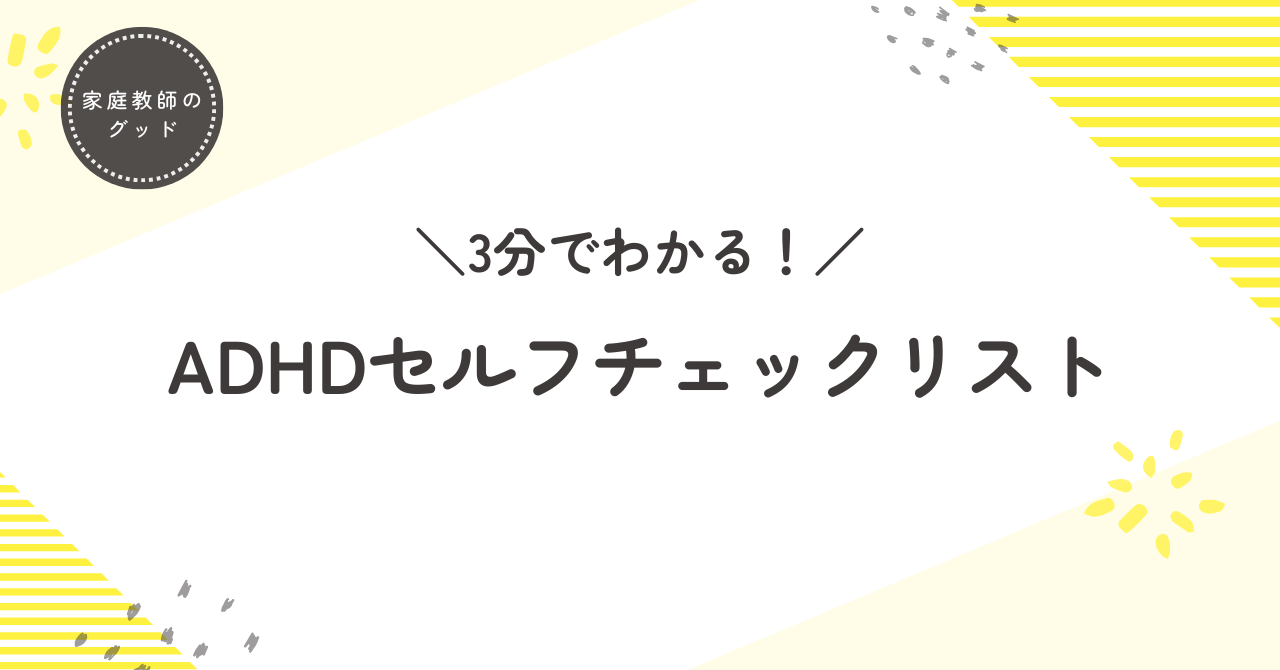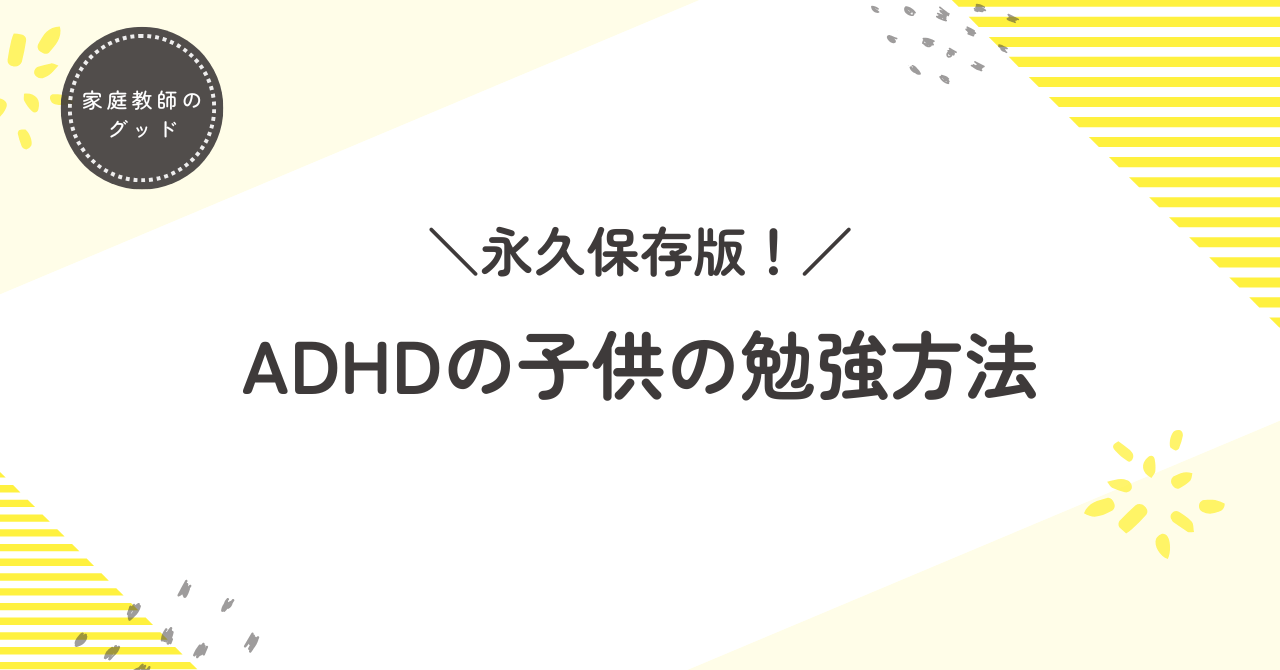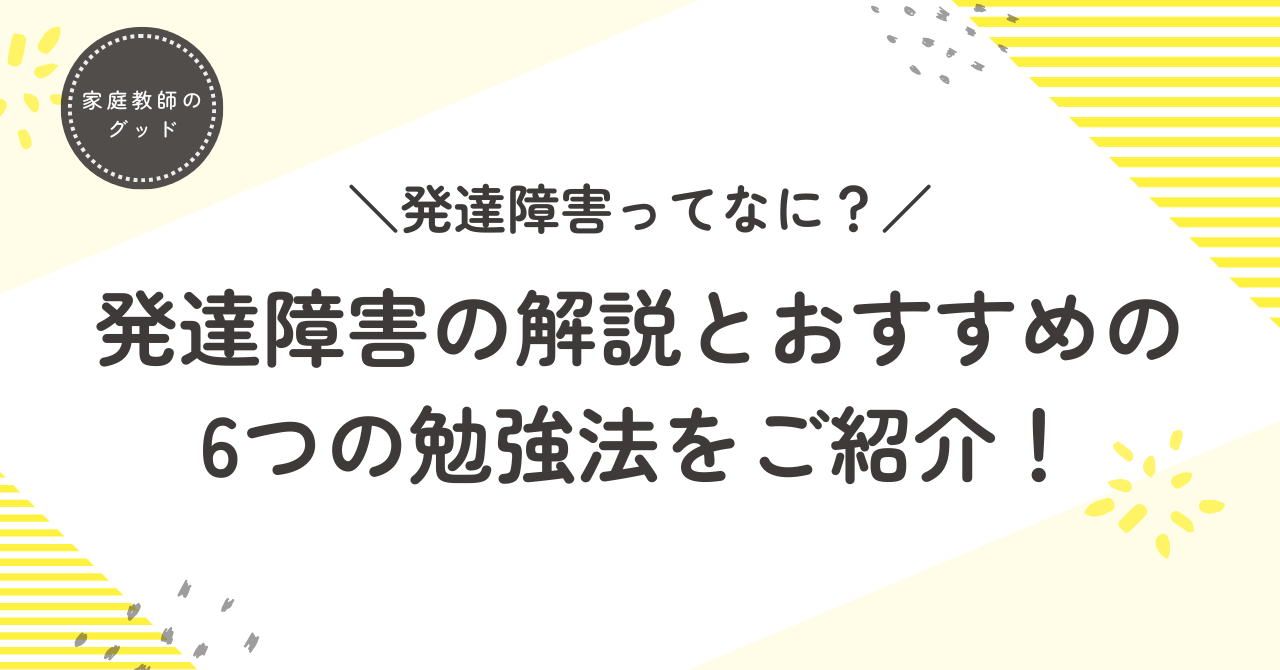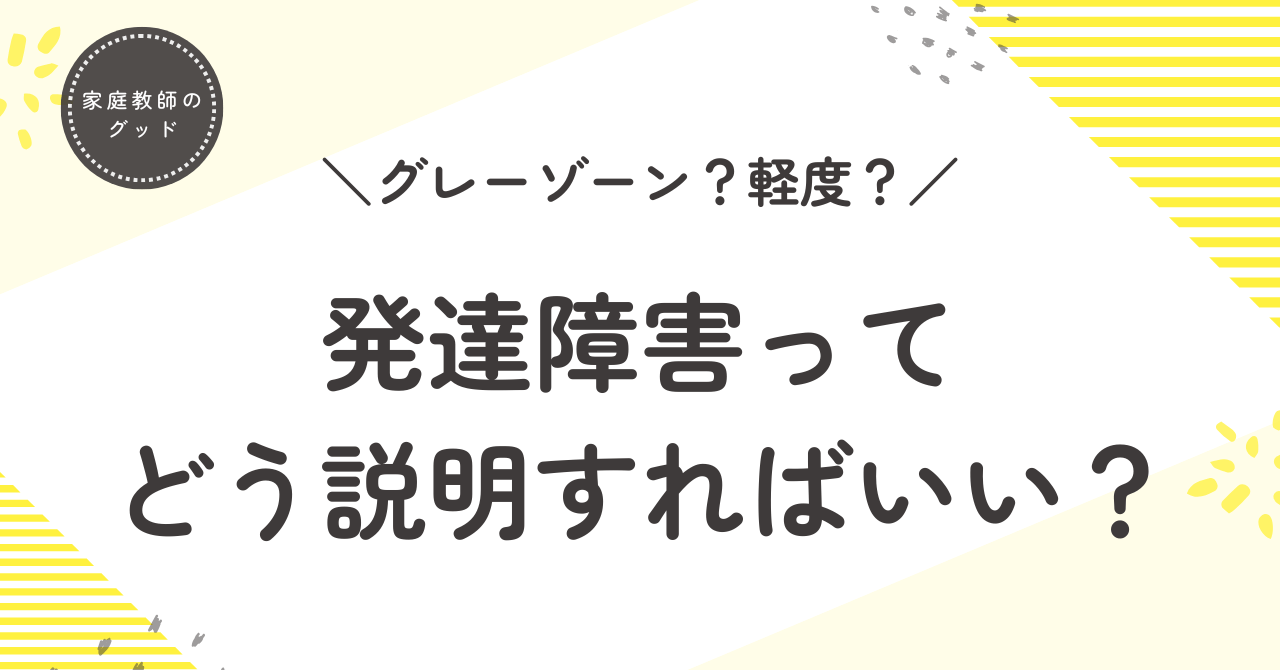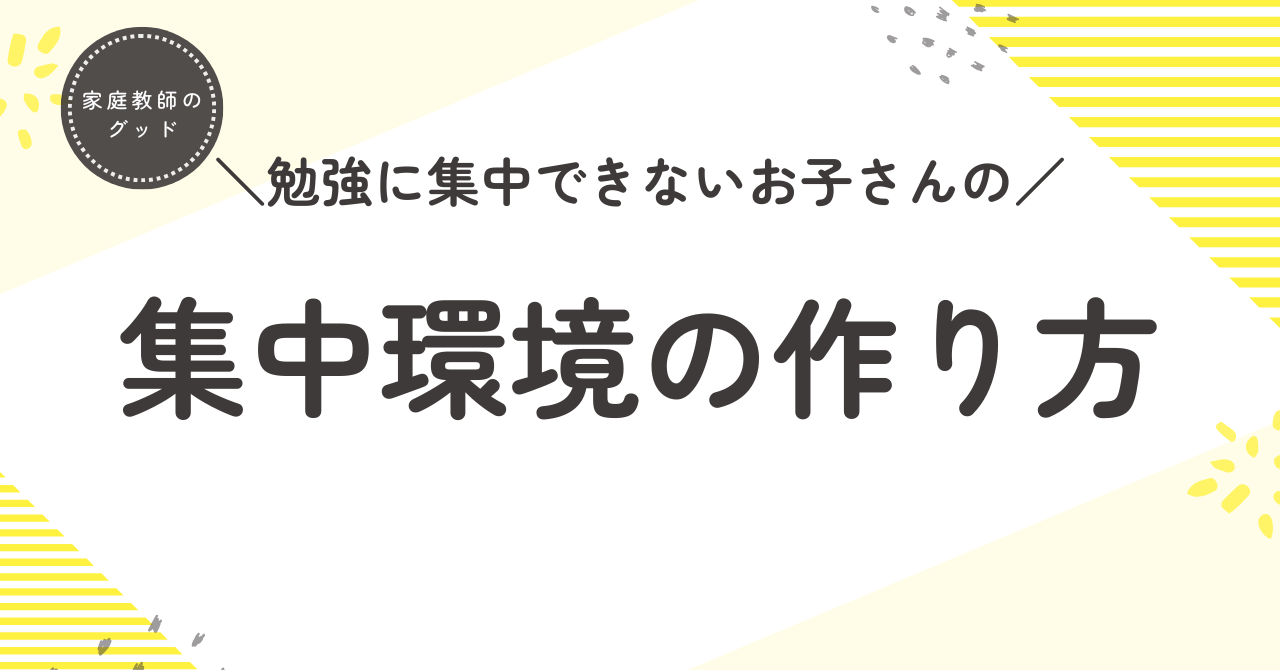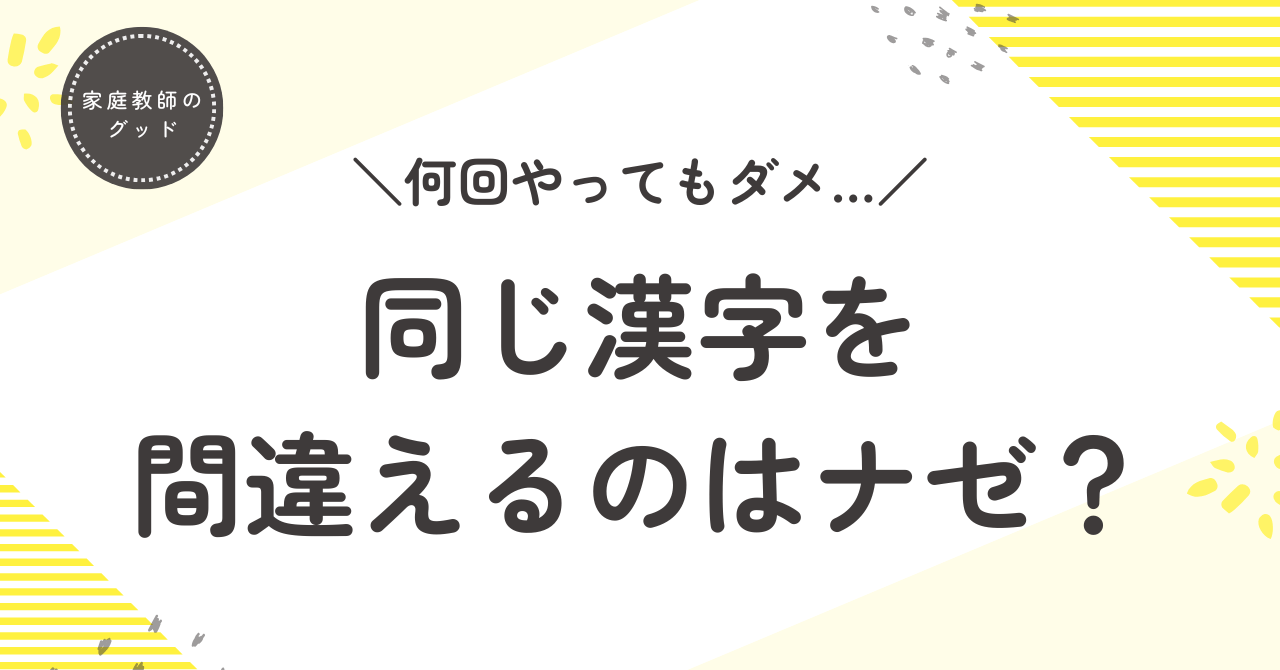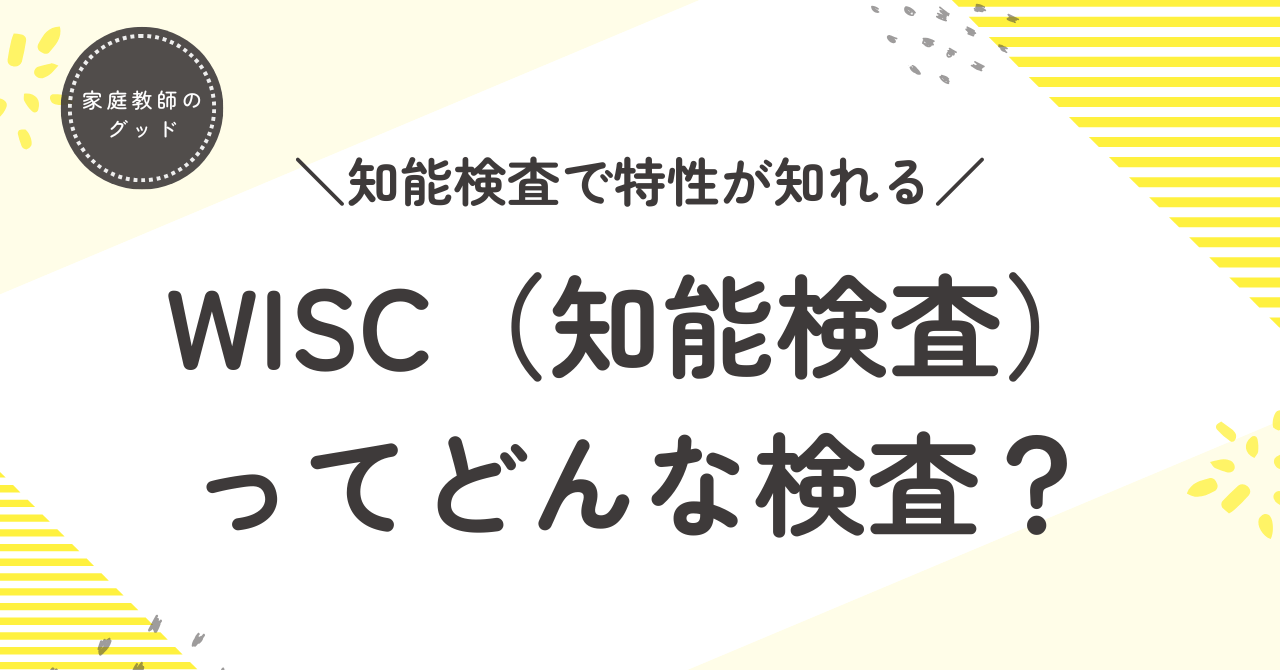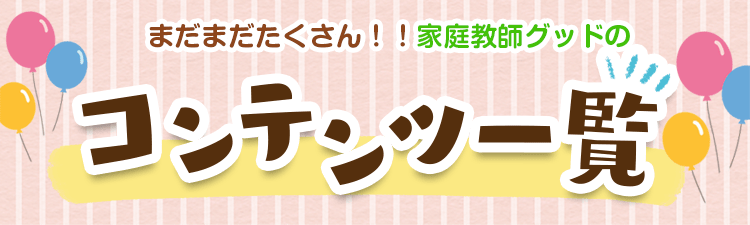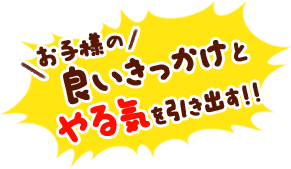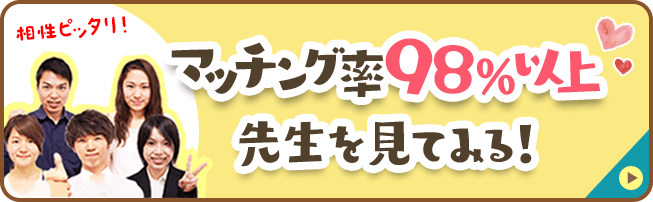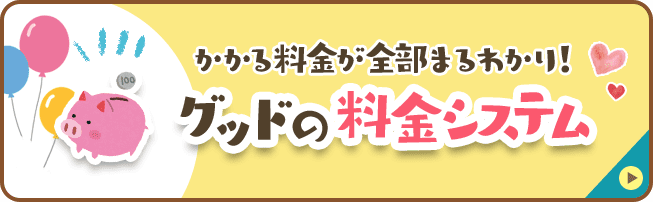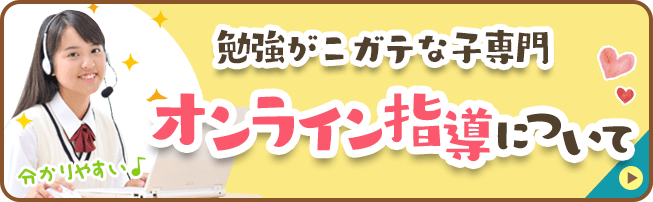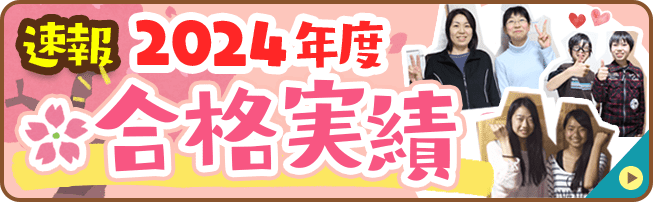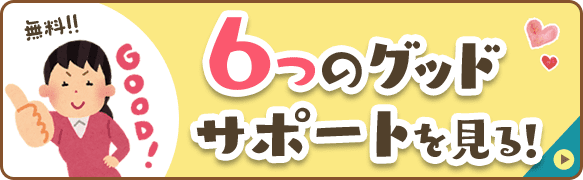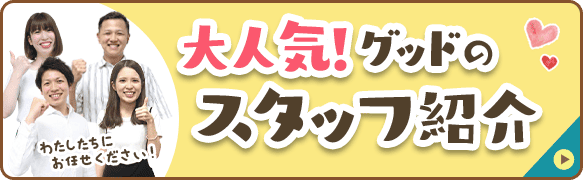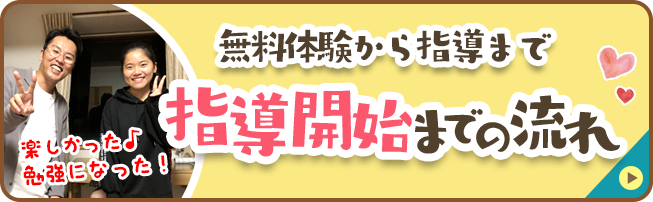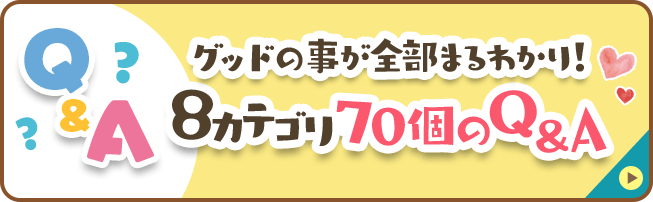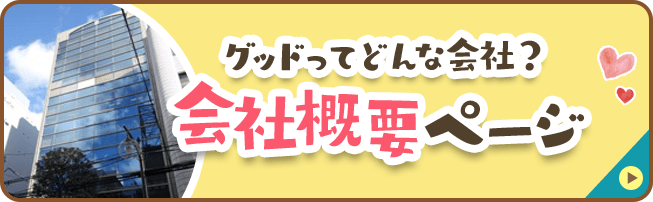【保存版】文章問題が苦手な子どもの原因と家庭でできる5つのサポート法
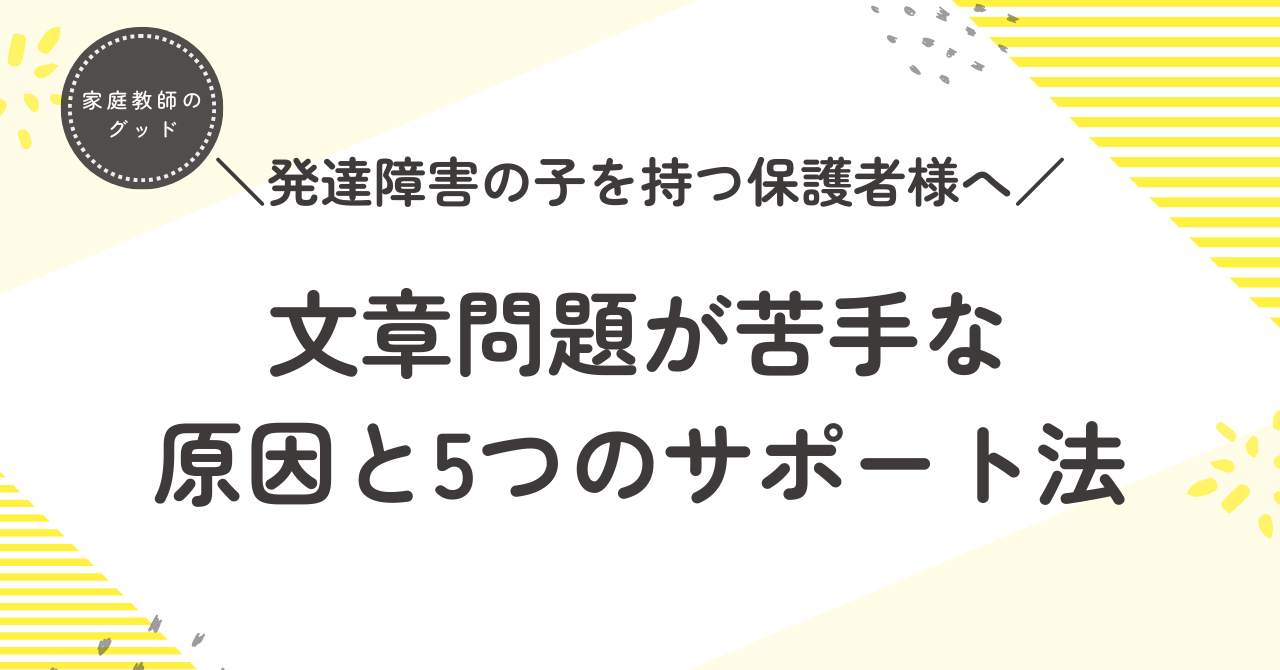
「計算はできるのに、文章問題になると急に手が止まってしまう…。」お子さんのそんな姿を見て、「どうしてだろう?」「うちの子だけ?」と不安になる親御さんは少なくありません。
でも、どうか知っておいてください。文章問題が苦手だからといって、考える力がないわけではないんです。つまづいてしまう原因とポイントを知り、サポートの仕方を変えてあげるだけで、「わかった!」「できた!」がぐんと増えていきます。
ここでは、文章問題でつまずきやすい理由とご家庭でできる具体的なサポート方法をまとめました。「うちの子のペースで大丈夫」と安心できるきっかけになれば幸いです。

文章問題が苦手な子は多いって本当?
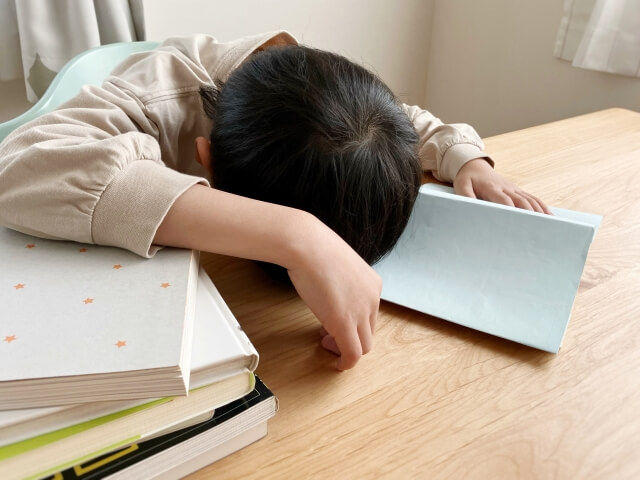
なぜ計算はできるのに文章題でつまずくのか
足し算や引き算の計算そのものはできるのに、文章問題になると解けなくなる子はとても多いです。それは、単純に「計算力」だけではなく、文章を読み取って情報を整理し、何をどう計算するかを自分で組み立てる“総合力”が必要だからです。
特に発達障害のあるお子さんの場合、一度に複数のことを処理するのが苦手だったり、文章の中から必要な情報を抜き出すのに時間がかかることもあります。
発達特性による読み取りの難しさ
例えば、文字を追うのが苦手だったり、途中で話が飛んでしまったりするお子さんもいます。文章問題は、ただ読むだけではなく、「何を問われているのか?」を読み取らないといけません。
読み取る力、整理する力、計算する力。この3つを一度に使うため、お子さまの特性によってはつまずきやすくなるのです。
「うちの子だけ?」と悩まなくて大丈夫
「うちの子は考える力がないのでは?」と不安になる気持ちが出てきて、不安になりませんか?でも大丈夫です!文章問題が苦手なお子さんはとても多く、それは能力ではなく“考える練習の仕方”を変えるだけで、できるようになることが多いのです。
少しの工夫でお子さまの「できた!」を増やしていきましょう。
文章問題が解けない子に共通する3つのつまずきポイント
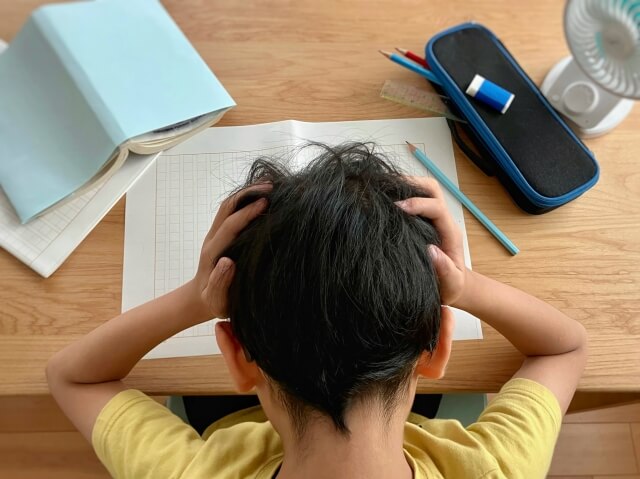
読解力のハードル
まず一つ目の壁は“読解力”です。問題文が長くなると、どこに注目したらいいのかわからなくなってしまう子も多いです。
文章中の数字を見つけても、どの数字をどう使えばいいかヒントがつかめなくて、問題が解けないことがあります。
情報整理が苦手
二つ目は“情報整理”の難しさです。文章問題は、情報を頭の中で整理して、順序立てて考える必要があります。
「お菓子を10個買いました。3個食べました。」この2つの文章から「残りはいくつ?」と情報をつなぐステップがありますが、この“つなぐ”作業が苦手なお子さんは、どうしても問題を解くのに苦戦してしまいます。
そういうお子さんには、一緒にヒントを探してあげると整理がしやすくなります。
数字と文章を結びつけるのが難しい
三つ目は、“数字と文章の結びつき”です。数字はわかるけど、その数字が何を意味しているのかが頭の中でうまくイメージできないことがあります。
問題を図にしたり、絵を描いて見える形にするとスッと理解できる子も多いですよ。
家庭でできる!今日から試せるサポート方法

問題を短く分けて読んでみる
いきなり長い文章を丸ごと理解しようとすると、お子さんにとってはハードルが高いです。
まずは1文ずつ区切って読む。意味がわかりにくいときは、「つまりどういうことかな?」とお子さんとゆっくり言葉を交わしてみるのが効果的です。
図や表を使って整理する練習
頭の中だけで考えるのが難しい子には、紙に図や表を書いて視覚化してあげるとわかりやすくなります。
例えば「どれが増えて、どれが減ったのか」「どこからどこまでが必要な情報か」を線で結んだり、絵にしたりすると「あぁ!」と何かに気づいて、問題が整理しやすくなったりします。
親子で一緒に考える「対話」のポイント
一人で解かせるのではなく、「どう思う?」「ここは何を言ってるかな?」と一緒に考える時間を作るのが大切です。
お子さんが考えたことを言葉にしてあげることもとても大切です。言葉にすることで頭に問題が入っていき、理解が深まりやすくなることで、自分で整理する力がつきやすくなります。
子どもの「できた!」を増やす声かけのポイント

正解よりも過程を褒めよう
結果よりも、「ここまで自分で考えたんだね」「わからないところを聞けたね」という“過程”を褒めてあげてください。
お子さんの自己肯定感が育ち、「次もやってみよう!」「聞いたらできる」と前向きになります。
間違いの中にあるヒントを探す
間違えたときも、叱らないで大丈夫です。むしろ逆効果になることもあるので、あまり叱らない方が良いですね。
「どこまであってたかな?」と一緒に答えを見直すことで、つまずいたり、わからなかったポイントをお子さん自身に気づかせてあげましょう。小さな「気づき」が次につながっていきます。
自信をつける言葉を
「大丈夫」「一緒にやろう」など、お子さまが安心して問題に取り組める言葉をかけてあげましょう。
焦らず、ゆっくり、リラックスして向かい合えるように、お子さんのペースを大切にしてあげてくださいね。
まとめ 〜おうちでできることから始めてみよう〜
文章問題が苦手だからといって、お子さんに考える力がないわけではありません。大切なのは、苦手である理由を知って「どこでつまずいているのか」を一緒に見つけることです。
読解、情報整理、数字と文章のつながりを少しづつで良いので練習すれば、「わかった!」の瞬間が増えていきます。
そして何より大切なのは、お子さんが安心してチャレンジできる環境をおうちの中に作ってあげることです。正解することだけがゴールではなく、「どう考えたか」「どこまでできたか」を一緒に喜んであげてください。
親御さん自身も、一人で抱え込まないでくださいね。困ったときは学校の先生や支援機関に相談しながら、無理のない範囲でお子さんのペースに寄り添っていきましょう。
小さな「できた!」の積み重ねが、お子さんに「自分はできるんだ」という自信を育ててくれます。今日からできることを、少しずつで大丈夫です。